| 2017年11月11日(土) |
| アンサンブル・リーダーより、ノン・ビブラートについての意見をいただきました。 |
|
武蔵野室内アンサンブルのノン・ビブラート双方について、私が思っていることを改めてみなさんにお伝えしたいと思います。
1.どうしてノン・ビブラートなのか
武蔵野室内アンサンブルは、私がリーダーをさせていただいたときから、基本的にノン・ビブラートで演奏しよう、という方針を続けています。その目的は、室内オーケストラとしての美しい音色、純正調の透明なハーモニー、ビブラートに頼らない幅広い表現力を目指すということです。
この方針は、すでに10年以上続けているので、かなり浸透しているとは思うのですが、新しいメンバーも増え、また、毎回何名ものエキストラをお願いしているという事情もあり、あまり理解されていない部分もあると思います。
2.ビブラートの歴史
その昔、古典派から前期ロマン派までの間、オーケストラの演奏ではビブラートをかけていなかったそうです。ところが、ワーグナーなどの後期ロマン派以降、息の長い旋律が多くなり、弦楽器は音を長く持続させるためにビブラートをかけるようになったと言われています。ところが、最近は、特に古典派や前期ロマン派の音楽を演奏するときには、当時のノン・ビブラート双方を見直す傾向が見られます。これは、ピリオド楽器だけではなく、モダン楽器のオーケストラでも行われています。指揮者ではアーノンクール、ノリントン、ブリュッヘン、スダーンなどが有名です。
3.ノン・ビブラートのメリットと効果
そのような演奏を聴いてみてまず感じるk十は、オケの音色の透明感です。ビブラートは、弦楽器の場合、音程を揺らす奏法ですから、複数の奏者が同じ音を弾く場合にビブラートをかけると音程に幅が生じるため、音色はハーモニーが濁ってしまいます。ノン・ビブラートはこの濁りをなくす効果があります。さらに、ビブラートをかけないことによって、より音程に気を付けるようになり、また、弦楽器で言えばボウイング、管楽器で言えば息の吹込み方で音楽により豊かな表情を付けやすくなります。
4.これからやりたいこと
武蔵野は、今までこのような演奏を目指してきましたが、これが今の武蔵野らしさを作っていることは確かであり、これからも更に良いものにしていきたいと思っています。そのために今後やっていきたい3つのことを提案します。
①音階、ハーモニーの基礎練習:毎回、曲の練習前に、10分程度、練習する曲と 同じ属性の音階、ハーモニーを練習する。
②曲の中で、特にノン・ビブラートが重要な個所の徹底:必要に応じて、事前または 練習中に楽譜上で指示する。
③音楽の起伏をより大きく表現する練習:パート練習、分奏のなかで徹底する。
以上です。(アンサンブル・リーダー)
|
|
|
|
| 2017年7月9日(日) |
| アンサンブル大会 |
|
団内アンサンブル大会@やよい会館 でした。 晴れた昼下がり、弦楽系4グループ、管楽系4グループの計8グループの発表です。
色々な作曲家の曲が取り上げられていました。 Hugenin、ロッシーニ、田中久美子、メンデルスゾーン、Bozza、バッハ、コレルリ。 といった面々。
どのグループも きれいな音 を紡ごうと、そんな想いが伝わってきた気がします。
コレルリ(イタリア出身の作曲家)の合奏協奏曲では、 Nアンサンブルリーダー曰く、『音符の並びはそんなに難しくないのだけど、 ハーモニーの良さが聞きどころ』。
古典の良さを感じられる曲で、確かに、普段の練習とはちょっと違う 違いをあじわう、そんなひとときでした。
…カルテットやトリオをなぜやるのか。 筆者を始め、重い腰が中々あがらない方も多いと思うのですが、 カルテットの楽しさを知っている人(実際にこうしてアンサンブル大会に出ている人)の演奏を目の当たりにすることで、何か糸口が見つかることも。 一緒に室内楽を組むことで、その人がどんな人なのかが一段と分かった(普段のオーケストラ活動だけではあまり知れなかった)、というのも アンサンブルをやる意味だと話してくれた方もいました。
中には、『オーケストラに参加するのは、一緒に室内楽を組むメンバーに出会うため』といった名言を放つ人も。 そんな豊かな仲間が集まる武蔵野。 次回もこのような場を必ず用意する、とアンサンブルリーダーからありました。
今回参加を見送った方々とも、次回ご一緒できることを楽しみにしています。(Va:Maho)
|
|
|
|
| 2017年5月14日(日) |
| 選曲会議とブラームス |
本番1か月前となりました。弦楽器のお手伝いの方が増え、合奏の音に厚みが出て来たのが嬉しいです。その一方で、冷静に細かく練習すればできるのに、音楽にノッて通して演奏するとあれ??な箇所がいくつもあり・・・うーん。ブラームス独特のうねりや温度感はとても気持ちがいいのですが、冷静さとのバランスを、自分の中でどうとるか。悩みます。
練習の後、次回の演奏会のための選曲会議がありました。誰でも出席可能、というオープンな会です。今回は、練習が少し早く終わったこと、同じ場所を引き続き使わせてもらったことにより、思いがけず大勢の参加となり、活発な意見が交わされました。やっぱり、こうじゃなくちゃねー。
メインの候補は、ベートーヴェン、ドヴォルザーク、シューマン、シベリウス、メンデルスゾーン・・・など。それと組み合わせる曲として、ハイドン(複数)、イベールのコンチェルトも。みんな、好きな曲はあるのです。でも、難しい曲はやりたくない。「難しい」かどうかは、個人の技術的な側面と、合奏で合わせるのが難しいという側面と、ふたつあります。トロンボーンが必要な曲か。ハイドンやモーツァルトなどの古典は、クラリネットがあるかどうか。曲の演奏時間の長さによって、2曲か3曲かがかわってきます。そしてプログラムとしての全体のバランスも大事。考えることがイッパイあって、たいへん。「これ、どんな曲だっけ?」というと誰かがyoutubeで音源を流してくれて「ああ、こんな曲ね。」便利な世の中になりました。
最後は多数決? うーん、挙手した人数が多い曲になるというよりは、推す声が大きい(?)曲になる傾向があるかなぁ。でも、今回は管弦打バランスよく出席者がいるので、多数決でもそれぞれの事情や都合、好みを反映できるかなぁ。というわけで、さまざまな議論と挙手の結果、メンデルスゾーンとハイドンの組み合わせに決定しました。いや、決まってしまえば、腹をくくって練習しますよ。ええ、難しくたってね。(Cb:なおちゃん) |
|
|
|
| 2017年4月30日(日) |
| フラッシュモブとブラームス |
4.29今回の指揮者、加門さんのご紹介でご依頼頂いた「池袋フラッシュモブ」に参加して参りました。 池袋Sデパート屋上庭園での第九フラッシュモブと聞き、娘(小4)が「出る!」と即決。授業中常に手を挙げ続けている彼女は、世の中ヤリタイコトいっぱい!です(^^;)。
と言うわけで母娘で参加させて頂きました。
世界中で色々なフラッシュモブが行われていますが、数回の練習を重ねてゆくと、仕掛け側も何とか群衆をアッと言わせたい的な願望が出てくる訳です。 オケは事前に譜面台を置いてバミったり、サプライズ的な演出は難しかったのですが、そこへいくと合唱隊はモブの醍醐味を感じられたと思います。 連休ごった返しの買物客の中、隣にいた普通のオジさんがいきなり「フロイデ!」と大声で歌い出すのですから。 ソリストが腹底から歌声をあげると、その瞬間もはやただのオジさんではなくなります。 50名ほどの合唱隊がその様に群衆から闊歩してくる様は、弾きながら見ていてまさにフラッシュモブ!でした。 世界中で戦線緊迫している中、にわかにベートーベンの第九「喜びの歌」が世界平和を願い唱われているとニュースで見ました。本当に平和が1番ですね。
さて、我がオケの定演本番はもうすぐそこまでやってきています。
ブラームスの3楽章、かの有名な冒頭のフレーズ。 実際弾いてみると、何故でしょう。。。あんな風になりませんみなさまスミマセン。 最初の3小節だけを何百回弾いていますでしょうか。。
ため息ばかりです。 自分の先生にも手ほどき受けましたが、何ともブラームスっぽいコツがあるようです。 ねっちりとして、でも重たくない運弓と、フレーズの取り方。
因みに私、先日大人になって初のソロ発表会♪を頑張ってしまい、左腕が腱鞘炎の状態です。ハイポジになると指板を抑える力が激減します。 腱鞘炎は動かさないと治るとか。
でも練習しなくて良いのか。 どなたか教えて下さい(*´Д`*) (Vc:U子) |
|
|
|
| 2017年4月23日(日) |
|
5年ぶりに、武蔵野室内アンサンブルに戻ってきました。 まず、快く迎えてくれたオーボエの方々、気さくに声を掛けてくれた団員の皆様に感 謝です。
今日は、加門さんの指揮で、ブラームス3番の4楽章から。 初めは緊張して音が出ませんでしたが、しばらくすると曲に入り込んで音も少しづつ 出てきました。
やっぱり、武蔵野の合奏は楽しい!何と言っても、武蔵野で吹く距離感が自分には心 地良い。 指揮者との距離、管楽器との距離、弦楽器との距離、約5mくらいの中にすべての音
が溢れていて、 ひとつひとつの音が体に染み入る。慣れない関東に来て、少し疲れていましたが、 今日は久しぶりに至福のひとときを過ごさせていただきました。
初見でしたので皆様にご迷惑をおかけしましたが、本番に向けて少しづつ調整してい きたいと思います。 今後ともよろしくお願いします。(ObのT)
|
|
|
|
| 2017年4月9日(日) |
| 指揮者と、そしてソリストと。 |
|
加門さんとの初合わせとなりました。これまでメンバーだけで練習してきましたが、本番の指揮者だと音楽の流れ方が格段に生き生きした音になるのです。当たり前といれば当たり前ですが。
そしてソリストの田中さんも、中学校入学式前の春休みに一時帰国をしての初合わせでした。豊かな音色と堂々とした表現は、とても12歳とは思えません。本番までの2ヶ月半の間に、さらに色々なことを体験し吸収して、成長していくのでしょう。若いっていいなあ。。。いやいや、私たちも頑張ります。(Cb:なおちゃん)
|
 |
|
|
| 2017年2月12日(日) |
| モーツァルトのヴァイオリン協奏曲 |
|
久しぶりの更新です。
次の演奏会では、モーツァルトのヴァイオリン協奏曲第3番をとりあげます。ソリストは、シンガポール日本人学校小学部チャンギ校の小学校6年生(演奏会の時は中学部1年生)の田中友梨さん。先月行われた第70回全日本学生音楽コンクールの東京大会で、バイオリン部門小学生の部で1位を獲得した方です。
そんな将来有望な若手が、なぜうちの楽団に?実は・・・去る10月に武蔵野はシンガポール在住のボーイソプラノとの演奏会を行ったのですが、そのマイキー・ロビンソンくんのお母様と田中友梨さんのお母様がいわゆる“ママ友”。「マイキーがオーケストラと一緒に演奏したのだけど、とっても良かったから、友梨ちゃんもどうかしら?」なんていう会話があったのかどうかはわかりませんが、コンサートが終わって間もなく、マイキーくんのママから友梨さんのママを紹介されたのでした。ヴァイオリン協奏曲なら、定期演奏会のプログラムに組めば実現しやすいかも?とのことで、早速6月の演奏会で弾いていただくことになりました。
なぜ、シンガポール??・・・武蔵野室内アンサンブルには、なぜか、シンガポール駐在歴をもつメンバーがかなりいます。ここ十数年の間に、増えたり減ったりはしていますが、団員名簿上で3割前後はいるでしょう。(友達が友達を誘って、巻き込まれて入団して・・・という結果、結構な派閥を形成しているかもしれません。)国境をまたいだところで、狭いアマチュア音楽家の世界。友梨さんのヴァイオリンの先生は、シンガポール駐在時代に、アマチュアオケのコンサート・ミストレスやソリストを務めていたW・雅子さんだそうです。偶然が運んできた今回の共演、どんな音を響かせることができるのか、とても楽しみです。(Cb:なおちゃん)
|

(1月22日の新聞より) |
|
|
| 2016年11月27日(日) |
| ここ1カ月ばかりのあれこれ・・・ |
|
すみません、1か月ほど更新をさぼっていました。気が付いたら、本番1か月前!!!!
11月の練習から、合奏を録音したものをmp3ファイルにして、webで共有できるようにしています。前回の演奏会のときに、FgのKさんが試みにやってくださったことですが、自分の音を客観的に聴くことが次の練習への工夫につなげられるということで、VaのJさんがyahoo!ボックスに武蔵野の音源をストックしてくれています。この練習日記をお読みの方で、練習の録音を聴いてみたいけれど、yahoo!ボックスのアドレスをご存じない方がいらっしゃいましたら、最寄りの団員までお声かけください。
そして、20日(日)の練習後は、第37回定期演奏会の選曲会議がありました。いつものようにアンサンブル・リーダーから「こんな曲はどう?」「この曲とこの曲とを組み合わせて、こんなプログラムはどう?」という提案がありました。今回、プログラム前半の曲ではヴァイオリン協奏曲がイチオシ。実は、水面下で、海外のソリストから共演のオファーがあったのです。協奏曲は、ソリストとのご縁とタイミングが大事。前向きに考えて、共演しようということになりました。前半がモーツァルトなら、後半は、シューマン?シベリウス? それともブラ―ムス?というのが提案。そこへ、「ドヴォルザークがやりたい」というメンバーからの発言が。曲の長さ、プログラムのバランス、管楽器の編成(今回は、4曲ともトロンボーンのある編成の曲)、練習の負担度合い(=難しさ)、などなど議論を重ねたけれど、最後は結局「この曲をやりたい!!」という好みに負うことになるわけで・・・ブラームスに決まりました。
27日(日)の練習後は、新入団員の歓迎会でした。前回からVaのお手伝いで参加してくださっているMさん、すっかり武蔵野を気にいってくれたようです。そこへ、うっかり間違って手渡されてしまったのが“団費袋”。いえいえ、入団を迫るつもりはなかったのですが、それがきっかけで気持ちを固めてくださったとのこと。今後ともどうぞよろしくお願いします。(Cb:なおちゃん)
|
|
|
|
| 2016年10月23日(日) |
|
10月23日(日)は、ベートーヴェン7番の1~4楽章をMさんの指揮で練習しました。
ベト7、1楽章236小節あたりの6/8の付点8分音符ノリズムと、254小節あたりの8分音符+16分休符のリズムとがあり、その演奏の違いを丁寧に練習しました。8分音符の場合は、1拍目に質の良い収め方をして、そこで完結するような8分音符を演奏すると、16分休符が聞こえやすくなるようです。最後30分でモーツァルトを通しました。
今回、人数が少なかったことで、弾き方・吹き方、各楽器の特性に違いがあり、アインザッツや音の収め方には様々なバラツキがあることが浮き彫りになりましたが、早めに各作曲家が求める音色、音符の特性をつかみ、なるべく指揮者の要求に添えるようにつとめると良いと思いました。(Hr:M.M) |
|
|
|
| 2016年10月22日(土) |
| ボーイ・ソプラノ演奏会 |
|
武蔵野室内アンサンブルとして依頼をうけての、ボーイ・ソプラノのマイキー・ロビンソンくんの演奏会が、神田キリスト教会で行われました。弦楽器のメンバーを中心に、パイプオルガンの助っ人を得て、弦楽だけ、オルガン独奏、そしてボーイ・ソプラノと弦楽とオルガン、というさまざまな音色を楽しんでいただくプログラムでした。5年前の震災の報道を見て、シンガポールに居ながら何かできないか、との思いでチャリティ・コンサートで歌っていたマイキーくんの、念願の日本での初舞台となりました。
教会の美しい響きと、神様からの授かりものと言われるボーイ・ソプラノの声。弦楽で参加していた私たちも、その響きにたっぷり浸った1日でした。歌っていないときの、お茶目な12歳の男の子の素顔もチャーミングでした。
・・・ここからは個人的なエピソードです。演奏会にはたくさんの裏方仕事があり、みんなで分担して運営しています。今回、それらを一手に引き受けた結果、当日朝に受付の文房具を用意しリハの流れを書いたプリントを刷り、録音録画機材を車に積み込み・・・会場入りしたら、いちばん大事な自分の楽器を家に置いてきてしまいました。リハーサルが終わる前になんとか開場についたものの、一世一代の忘れモノでした。(Cb:なおちゃん)
|

マイキーくんとVnソロのコラボ。

明るい光の美しい教会でした。 |
|
|
| 2016年9月25日(日) |
| 2ヶ月ぶりの更新です。 |
|
すっかりご無沙汰しています。いえいえ、ご無沙汰なのはサボっていた私だけ?(ごめんなさい)、武蔵野は8月末から今回の指揮者の森山さんを迎えての練習が始まっています。
打楽器を得意とする森山さんによる、リズムの権化である“ベートーヴェン7番”・・・生き生きとしたテンポ設定なのですが、うっかりすると追われている・急かされている的な雰囲気が出てしまうのは私だけ?(ごめんなさい) ベートーヴェン7番は、10年前にも武蔵野でやりました。その時の印象がとても強いので(実際、その時使った譜面を今回も使っています)、ここはfzを強調したところ、とか、ここの和音の変化を意識して表現したとか、当時の記憶が蘇ってきます・・・が、いかんいかん。そのときの音楽と今回の音楽とはまた別モノ。同じ楽譜を使っていても、指揮者や合奏する仲間が違えば、表現の仕方も少しずつ違うのです。同じリンゴを描いても、人が違えばリンゴの絵は違うわけだし、描く人が同じでも画材が違えば、絵の具と色鉛筆では違うリンゴが表現されるわけだし。
閑話休題。10月22日の依頼演奏会について、ここでちょっとご紹介します。武蔵野のメンバーの何割か(結構多いかも)は、シンガポールに縁があります。そのシンガポールつながりで、12歳のボーイソプラノ、マイキー・ロビンソンくんの伴奏を引き受けることになりました。いつもはピアノ伴奏で歌っているけれど、オケ伴奏でも歌ってみたい・・・というたってのお願いを、武蔵野で実現していただこうというわけです。パイプオルガンの助っ人を得て、弦楽で伴奏を引き受けました。出演者はほぼ決まりつつありますが、裏方のお手伝いや聴きに来てくださる方も大募集中。入場無料です。
10月22日(土)14時開演
神田キリスト教会(東京メトロ末広町駅より2分、JR秋葉原駅より7分)
ボーイ・ソプラノ:マイキー・ロビンソン
伴奏:武蔵野室内アンサンブル
パイプオルガン:井上紗和子
指揮:三好健夫
|
|
|
|
| 2016年7月10日(日) |
| ゲスト指揮者!! |
縁あって、武蔵野を振ってみたいと思ってくださる方があり、まだまだ譜読み段階の練習ですが、ゲスト指揮者として振っていただくことになりました。高山さんとおっしゃる女性指揮者です。
指揮者が前に立ち、構えてから振り出すまでのちょっとした間、ひと呼吸。そんなものが指揮者によって違うんだなぁと感じました。もちろん、楽団によっても違うのでしょうけれど。今日の高山さん、さっと構えてさっと振り下ろす。構えてからあれこれと指示は出さない。そして、私たちの出した音をまず受け止め、認めて、褒めてくださりつつ、「でも、ここはこんな風にするともっと良いのではないでしょうか?」との指示。初めての顔合わせなので気を遣ってくださっているのでしょうが、情熱をうちに秘めつつも、どう伝えていくべきか、と胸の内で内容を出し入れしている印象がありました。颯爽としたテンポ設定には「こんな音を求めていくなら、こんな速さになると思います」との根拠があり。管楽器と弦楽器が役割を交替しながら演奏する場面では、フレーズ感をそろえるためにはどうしたらよいか、とのコメントがあり。「本番を振ってくださるマエストロと、素敵な音楽を作り上げてください」とのメッセージをいただき、今日の練習は終了となりました。合奏練習1回だけでなく、何ヶ月かを共にして本番までご一緒できたら、高山さんの音楽をもっと深く知ることができたのかもしれません。
私たち、半年に1度の演奏会を行っていますが、本番前の3~4ヶ月程度に本番の指揮者を迎えての練習になるため、残りの2~3ヶ月はメンバー内で指揮者を立て、合奏や弦分奏・管分奏をしています。以前はもう少し少人数だったので、指揮者ナシで聴きあって、というのもやりやすかったのですが、人数が増え、自分も演奏しながら意見を言ったりダメ出しをしたり、というのがなかなか難しくなってきました。一方で、譜読み練習を振ってくださるメンバーの負担もありますし(指揮をすると自分は練習できない)、さらに楽器奏者はどうしても自分の楽器の音に注耳(注目ではなく)してしまうなぁ、と思うこともあります。そんな時期のゲスト指揮者だったので、安心して自分の演奏に集中することができ、楽団としては助かりました。ありがとうございました。(Cb:なおちゃん) |
|
|
|
| 2016年6月11日(土) |
| 本番前夜 |
今期もまた、この練習日記にお付き合いくださったみなさま、そして原稿を書いていただいたメンバーのみなさま、ありがとうございました。本来なら終演後に書くことですが、明日はきっと頭がぐるぐるしていて(酔っぱらって、ではなくて:笑)まとまらないと思うので、ひと足早く、今期のサマリーを。
ハイドンの交響曲第90番+メンデルスゾーンの交響曲第5番。演奏時間はそう長くはないものの、音の密度が濃いというか、楽譜が黒いというか。そして、前へ前へと進む加門さんの音楽。弦楽器の私には息つく暇もなく弾き続けるという感じの2曲です。(25m潜水ブレスなし一本勝負、って感じ・・・、いやいやそんな潜水無理だってば。)
今期のトピックのひとつは、練習の録音をメンバーで共有し始めたこと。毎回録音してくださったFgのK村さん、webに載せてくださったVaのK子さん、ありがとうございました。それぞれの事情でお休みした練習の日に、指揮者からどんな指示があったのかを知るために始めた録音ですが、自分が出席した練習の音を客観的に聴くことにも大きな意味がありました。「弾けてないのがバレバレ・・・」とか「けっこうそれっぽく聞こえてるからいいか」とか、「うるさすぎる」「聞こえなさすぎる」などのバランス問題etc、もちろん音程と和音の問題も。私は、通勤途中にスマホで聴いていました。平日は楽器になかなか触れないので、せめてもの脳内楽譜チェックと、あるべき姿のイメトレを・・・。
若手メンバーの子育て休団はやむを得ないのですが、正直なところ痛手です。今期は、子連れ本番で復帰してくれた夫妻がありました。今日のリハーサルにベビーが登場すると、ついついみんなの視線がベビーに集中。みんな笑顔になります。子育て終えた世代の元ママたち「私たちの頃は、奥さんは子育てで休団するけど、ダンナは好きなようにオケやってたのよねぇ。今は夫婦で休団するのが当たり前なのねぇ。」家庭人として、音楽仲間として、複雑な心境です。練習所で託児できれば一番よいのでしょうね。
運営面では、今期メーリングリストが稼働を始め、運営委員会の議事録などもデジタルで共有できるようになりました。練習の出欠を登録するソフトも定着したようです。少しずつですが、仲良く楽しく、美しい音楽のために、楽な運営方法で、団の活動ができるようにしていければと思います。(Cb:なおちゃん) |
|
|
|
| 2016年5月29日(日) |
| バランスって大事! |
|
まだまだ時間あるしー、と思っていたらあっという間に本番まで練習はあと2回! 今回は色々な事があり、ここに行き着くまでとても長かった様に思います。
バランスって大事だなぁ、と色んな場面で感じています。人が集まると集まった数だけの考え方が生まれます。発する音色も然り。
同じテンポ感で進んでいるつもりなのに、どうしてズレてるんだろう…。 pって書いてあるからピアノにしているのに、足りなかったり大きかったり…。
どちらも自分と周りとのバランスなのかな、と思います。 自分が正しいと思っている速さと、このpはこれ位だろうと思って発する大きさは、果たして周りと溶け合っているのか。特にpは×(かける)パート人数分の大きさに膨れあがる事まで計算しないといけないのに…反省点ばかりです(^^;;
私の頭を「思考改革」しないといけません。
今回はハイドンのシンフォニーが別々のソロ楽器によるバリエーションになっています。 その中でチェロの部分を弾かせて頂いていますが、毎回申し訳ないくらい気持ちよく弾かせてもらっております(^ ^) 。いつも個人レッスンをして頂く私の先生にも手ほどきを受け、色々な解釈の仕方も学びました。実際の演奏に生かせるのかは全く微妙ですが。
本番まで残りわずか。周りとのバランスを意識して励みます! (Vc.yuko)
|
|
|
|
| 2016年5月22日(日) |
| 選曲会議がありました。 |
先週から、午前中に4回の分奏が計画されています。先週は管分奏、今日は弦分奏。朝10時から練習して、昼食休憩を挟んで午後5時まで。分奏が上達に効果的なのは十分承知ですが、終わる頃には頭の中が音符でいっぱい・・・・。そして今日は、終了後に近くの朝日会館に場所を移して、次回の演奏会の選曲会議がありました。誰でも参加できる、というこの選曲会議、今回は12人が集まって意見を繰り広げました。この場を借りて、そのご報告を。
来る12月の演奏会については、会場と指揮者がすでに決まっています。この会場で、この指揮者ならば・・・ということで、アンサンブルリーダーから出された原案が、ベートーヴェン2つとブラームス。うーん、3曲も良い曲だけど、ブラームスはちょっと技術的にどうかなぁ。ということで、メインはベートーヴェンに固まりました。
中プロは、「いつかやりたい!!」と前々からあがっていたイベールのコンチェルトが話題に。いつかやりたい、は今回実現できるか? でも、「ヴァイオリンにもう少し団員が増えればばっちりなんだけど・・・」ということで、近い将来にやりましょう、と約束して見送り。今回の助っ人のみなさん、ぜひぜひ私たちの仲間になってくださいませ。・・・じゃあ、どうしようか、というところで出た案が、サンサーンス。えぇ~?動物の謝肉祭なら有名だけど、その曲は知らないなあ。マニアックな曲なのによく知っているねぇ。スマホからダウンロードした音源を、紙コップで音量をあげてみんなで聴いてみると、ほぼ全員が初めて聴く曲だけど、なかなか良い曲かもという印象。メインがベートーヴェン、中プロがサンサーンス、となると、トータルの演奏時間を考えると、前プロは短めの曲で・・・モーツァルトかな。有名な歌劇の序曲をやりたい、という声も聞こえてきましたが、今回は原案の中にあった曲が採用されました。こちらも、まぁ「マニアックな曲」かもしれません・・・。
こうしてプログラムが固まったところで、ライブラリアンが楽譜を借りたりダウンロードしたりして入手する手段を確保し(○○版、など色々あって面倒な曲もある・・・)、団長が指揮者に確認してOKがとれたところで、団員に公式発表になります。6月の演奏会のプログラムにも掲載され、また、本番の頃には楽譜も配られる手はずになります。お楽しみに。(なおちゃん) |
|
|
|
| 2016年5月8日(日) |
|
|
本日は武蔵野が誇るマエストロ、シャルル・ミヨシ先生によるフランス語講……・・・リハーサルでした。 これまでやってきたことを確認しながら全体を通し、音楽をブラッシュアップ。また何故か若者が急増し、活気のあるリハーサルになりました。シャルル先生、ありがとうございました。
ところで今回のリハーサルでも、カウントが話題になりました。超基礎的な事ですが、どこのアマオケでも永遠の課題だったりしますよね。譜面には丸一つしか書いてないのに、これを8だの16だのでカウントしなければ、音楽が噛み合わない。この丸一つが怒涛のキザミの後にでてきちゃったりするもんですから、そりゃまぁ丸一つ見た瞬間、人は安心して、カウントをやめるんですね。そして気づけば次のフレーズが始まってて、あらヤダ私ったらまだ全音符だわ、なんて事が起こったりするワケですね。実に難しい!
でも最近、これこそアンサンブルの原点と感じるのです。近頃、アンサンブルとは「みんなで一緒に数えること」に終始する気がしています。普段は淡々と数える、でもメロディが唄ったら、伴奏もそのカウントにスッと合わせて一緒に数える。そうやって互いを尊重しながら、みんなで一緒に数えて行くと、自然と一体感が生まれてくる。気がします。いや、わかりませんが。やめやめ。酒ー。
とりあえず、我々は武蔵野室内アンサンブルですから、立川の狭い部屋の中で一緒に数えるのです。あら陰気。本番まであと1ヶ月!頑張って数えましょう!
さて、話は変わります。 N沢人材派遣サービス㍿はこの度、武蔵野に4名の素晴らしい人材を派遣しましたので、この場を借りて簡単にご紹介します。
まず、アマオケ界が誇るナイスキャラ、U松くん(ストバイ)。彼の辞書にディビジという言葉はありません。 続いて、スーパードライバー、Sキくん(セコバイ)。彼のジェントルな運転に女性はメロメロです。
さらに、我らがアイドル、Nエさん(セコバイ)。各方面から引っ張りダコなのですが、宗教改革に魅かれご快諾!セコバイは晴れマークです。 最後に、スポーツ万能才女、Mカミさん(ビオラ)。なんとU松くんと同じ高校出身。ナイスキャラも絶賛継承中。
以上!!お手柔らかにどうぞ! Tomo.N
|
|
|
|
| 2016年4月24日(日) |
|
|
前回の練習にに引き続き今回も、加門先生からの細かい指摘について、音を出しながら確認していくという、地味ながら時間の経つのを忘れるような充実した練習でした。何となく勢いで、若しくは耳で覚えている大雑把な感じで演奏してしまったところも、よくよく譜面を見たら作曲者自身からの指示がしっかりあったりして、もっと意識を高めなくてはいけない、と痛感しました。
今回のメンデルスゾーンの曲は35分程度の曲ではありますが、お客さんを飽きさせずに、最後までじっくり聴いてもらう演奏をするのはとても難しい曲だと感じています。選曲の際には、特に以前演奏したことのある複数の団員から、是非また演奏したい、との強い推薦があったのですが、この曲に馴染のない私としては全くピンときませんでした。今回取り上げることが決まってから、YouTubeでのhr-Sinfonieorchesterの溌剌たる演奏(特にCl
1stの女性奏者が素晴らしいです。有名な奏者なんでしょうか)を何度も繰り返し聴いたり、誰も知人のいない別のアマオケでも、この曲を演奏会で取り上げると知るや聴きに行ったりもしたのですが、自分自身が途中で飽きてしまって、曲としてどうなんだろう、との思いが拭えませんでした。でも、いざ練習となってようやくわかりました!
この曲は、演奏する側に回ると燃える要素が多分に含まれている、でも、細かい部分から緻密に組み上げて、奏者全員が普段よりも相当に感覚を研ぎ澄ました演奏をしないと、お客さんの耳には印象深く残ることなく消え去ってしまう曲だと。あと6回の練習の中で、演奏に関わる全ての面で精度を上げていければ、と思います。
ハイドンは溌剌且つ壮麗に、でも余裕を持ってといきたいところですが、その前に自分の技術が…。でも、YouTube で観る限り、ベルリンフィルのシュヴァイゲルトさんだって結構必死に吹いているようなので、既に開き直りの心境です。
あと、今回の練習を通しての自分の課題は、スラーのかかった後ろの音の表現でしょうか。テンポの速い遅いにかかわらず、短めにしてしまう傾向があるようなので、ゆっくりの部分ではしっかり鳴らして、でも平板にならないように、早い部分ではあまり跳ねた感じにせずに、でも推進力を失わないように、を心がけたいと思います。でも、息のコントロールやリードとの兼ね合いの要素も多いので、なかなか難しいところです。(Fg:
T.K.)
|
|
|
|
| 2016年4月10日(日) |
|
|
桜の満開の時期が過ぎ、新たに入団された方、産休から戻ってこられた方、 大学の研究のために海外に旅立つ方、それぞれの新しい年度が始まりました。
6月の本番まであと2か月となり、いよいよ中盤の練習です。
今日も指揮者からたくさんの緻密な指示をいただきました。 今回から、練習中に指摘・要望した内容を、休んだ人にも次の練習までに今まで以上に 徹底することになったため、いつも以上に楽譜の書込みに真剣モードです(笑)
特にハイドンは、音符が少ないのに(少ないから)、楽譜に簡単に表記できないことがありすぎて、 やはり古典は、当たり前のことを涼しい顔してやるっていう力が試されるわぁ、と改めて痛感。
試しに録音してみたのを後で聞いたら更に深く反省、、。 音の強弱、音程、リズム、旋律と伴奏のバランス、全て基礎中の基礎です>< やってたつもりが・・・うーん、思った以上にできてない。
頭でわかっても体がその通り動くとは限らず、そこは訓練しかないので、 ゆっくりメトロノームに合わせて音程を確かめながらの個人練はずーっと必要ですね。
軽快で流れるような音楽目指して、あと2か月頑張りましょう。(Va.K.U.)
|
|
|
|
| 2016年3月27日(日) |
| 指揮者よりのメモ(練習日記の付録) |
|
団員MLでアンサンブル・リーダーよりお知らせされた内容ですが、お試しに練習日記の付録として転載します。 3月27日の練習で加門さんから全体及び1stVnに対し
指示があった主な内容をまとめてみましたのでパート譜への 書き込み、確認等お願いします。 各パートごとの加門さんの指示はそれぞれのパートで確認し共有をお願い
します。
<メンデルスゾーン>1楽章 冒頭のテンポは4分音符=60、
Allegro con fuocoのテンポは2分音符=120
46,47小節2分音符はテヌート気味に
50,51,73~76小節も同様にテヌート気味に
86小節からの8分音符は硬めに
118小節はフォルテ1個、全体にFFとFは違いを出すこと
119,123小節2分音符はテヌート気味に
126,130小節はフォルテ1個 Dから4小節間はFFを持続
436小節4つ目の4分音符から新しく始める
515小節付点2分音符と8分音符の間を切って弾く
2楽章 101小節のsemple PPをキープ
4楽章 Allegro vivaceのテンポは付点4分音符=70
Bの前はクレシェンドでBから急にP
63小節からのテンポは二分音符=80で2つ振り
75小節はFひとつ 79小節は突然FF 111小節はFひとつ、
117小節はFF、 141小節はFひとつ
157小節2つ目の4分音符からF Gから長いクレシェンド
185小節3拍目から急にP
187小節からクレッシェンドをたくさん
189小節3拍めで急にP
198小節4つ目の8分音符からFF、クレシェンド削除
207小節2拍目からFひとつ 242小節3拍目の2分音符からpiu F
<ハイドン>3楽章 21,22小節はdim
55小節の装飾音は16分音符で Trioはのんびりと
4楽章 35,36,37小節の1つ目の8分音符と次の16分音符は分けて弾く
58~61小節の8分音符と16分音符の間を空けて弾く
以上です。よろしくお願いします。 (アンサンブル・リーダー)
|
|
|
|
| 2016年3月27日(日) |
| アンサンブル大会のご報告&ご挨拶 |
3月13日に毎年恒例アンサンブル大会が開催されました。当初は参加団体数が少なく、開催が危ぶまれましたが、当日は8団体のエントリーがありました。
少人数での演奏は、大人数での合奏と比べて個性が際立つので、普段とは異なる一面が見れたりします。
今大会は、新しいメンバーとの演奏もあり、また老若男女問わず多くの方の演奏もあり、充実したものになりました。少人数でのアンサンブルの経験を大人数での合奏にも生かしていけたら良いですね。
また、私はいつもはVnを弾いていますが、今回はVaにも挑戦してみました。いつもと違った楽器での演奏で苦労も多かったですが、内声部として普段とは異なる視点から演奏でき、新鮮でした。
私事になりますが、来月から海外に長期出張することになっており、長期休団となります。海外でも楽器は持っていって、演奏できたらなぁと思っています。3年後にまたこの場で皆で演奏できることを楽しみにしています!
(M.S) |
|
|
|
| 2016年2月28日(日) |
|
|
6月のコンサートへ向けて今日で3回目の練習である。だいぶ楽譜には慣れてきたものの、まだまだ細かい部分は十分練習できていないのが現在の状況。3月27日の練習には本番指揮者の加門さんが来られるので、全員がしっかり個人練習することが大事だ。
ところで3月13日には毎年恒例の団内アンサンブル大会が開催される。これは外からお客さんをお呼びすることはない、団内のミニコンサートであるが、メンバー同士のアンサンブル向上と親睦(飲み会?)を目的として毎年この時期に開催しているのだが、なぜか今年はエントリーするグループが少なくて困っている。簡単な短い曲でもアンサンブルの楽しみは十分得られるし、お互いのレベルアップにも役立つので、今からでもぜひエントリーをお願いします。
それからもうひとつ、前回のコンサートでベートーベンのピアノ協奏曲第4番の素晴らしいソロを弾いていただいたピアニストの鷲宮美幸さんがラベルの傑作、「ピアノ協奏曲」を演奏するコンサートの案内を鷲宮さんご本人からいただいた。日時は5月20日(金)18:30開演、場所は東京芸術劇場コンサートホールで、指揮は新田孝さん、オーケストラはニッポンシンフォニー(優秀なプロ奏者で構成されているそうです)で、他にモーツアルトのフルートとハープのための協奏曲、ショパンのピアノ協奏曲第2番、ベルディのオペラアリアなどが演奏される贅沢なコンサートである。ぜひ大勢で聴きに行きたいと思うので、チケットの申し込みをよろしくお願いします。(T.N.)
|
|
|
|
| 2016年1月24日(日) |
|
|
2016年前半シーズンが始まりました。1ヶ月半のオフというのは、近年には珍しく長かったかもしれません。今日は初合わせと年に1度の総会、そして新年会が予定されていました。
初合わせは、アンサンブル・リーダーの指揮にて、まずはハイドン、そしてメンデルスゾーン。難しい楽章は「ゆっくりめに、おねがい。」という声がかかるものの、気が付くと速くなってしまうのは何故? 余裕が無い焦る心の現れかもしれません。「このぐらいの速さなら、弾けるんだけど。」「でも、きっとこの倍の速さになるんだよね。」「倍かぁ・・・」という会話がなされた楽章がありましたが、さて、どこでしょう?
総会は、活動報告、決算報告、活動計画、予算案、という議題で進みました。武蔵野は小さな組織ですが、一応、形を整えてあります。役員選出は、団長以下、運営委員や会計監査など、留任の方もいますが、新しい顔ぶれの方も加わりました。団員名簿には休団の方のお名前もあります。転勤や引越、職場や職種が変わったことで練習に参加できない、などの方は、いずれまた、戻って来られることを期待して、退団ではなく“休団”の形をとる方も多いのです。最近では、子育て休団も幾組かいらっしゃいます。「私たちが子育てしているときは、ダンナは自由にオケをやっていて、奥さんだけが子育てでオケ休業だったのに、最近では夫婦でオケ休業するのね。世代が違うのね。」と元子育て組のつぶやきも聞こえてきますが。
そうそう、今回、団員間の連絡に、メーリングリストを使うことになりました。今ごろ?と思われる方も多いでしょう。準備をしてくださったビオラのJさん、ありがとうございました。これをお読みになっている団員・元団員の方で、メーリングリストのお知らせが欲しいのに来ていない、という方はいらっしゃいますか? また、元団員の方で、当面復帰できないので、煩わしいからメーリングリストは不要、という方はいらっしゃいますか? 早めにお知らせいただければ助かります。どうぞよろしくお願いします。
※メーリングリストについてお問い合わせ必要な方は、ホームページ経由(団長宛てメール)でどうぞ。(Cb:なおちゃん)
|
|
|
|
| 2015年12月6日(日) |
| ご来場ありがとうございました。本番終了、反省その他・・・ |
ホームページ担当(な)です。本番が近くなると練習が多くなるわりには、いつも練習日ごとのホームページ更新が追いつかず…すみません。ピアニストの鷲宮さんにフィーチャーして、彼女を私たちの団につなぐきっかけとなったシンガポーリアン作曲家TanChanBoon氏にメッセージをいただいて、それを掲載しようと思っていましたが、連絡がつかないままに本番になってしまいました。聴きにきてくださった方、ありがとうございました。一緒に舞台にのってくださったかた、お疲れさまでした。
今回のプログラムは、演奏時間の長さの割に、中身がギュッと凝縮されているというか、集中力を要求されるというか、そういう曲でした。特にシューベルト。前日練習が終わったところですでに、「3回目ぐらいの合奏の時の方が、まだ“弾けたかな”というか“何とか形になるかな”って感じがしたのに、練習すればするほど弾けなくなっていく」とか、「噛めば噛むほど味が出るスルメみたいに、どんどん難しさが染み出してくる」とか、いろんな噂話がありました。指揮者からは「何でもない譜面なのに、きっちりと合わせるのが難しい。それが古典(=シューベルト)の難しさ」というコメントもいただきました。力いっぱ弾けば・吹けば、熱演になって何とか伝わるかも?という曲ではないのは百も承知、でも、技術のレベルアップは亀の歩み、あとは集中力と本番の奇跡に賭けるのか?
そんな中、本番当日の今日、ふたつの“仕掛け”がありました。ひとつは、シューベルト1楽章のリピート。前半の提示部についている繰り返し記号を、楽譜通りやるのかどうか、という話題です。リピートをするかどうかの是非は、しばらく前から聞こえていましたが、何となくなし崩し的にリピートをしない練習が行われていました。今日はリピートしない→いつもリピートしない、になっていき、本番前日の合奏で「頭(冒頭)に戻って(リピートして)」と言われても、全員が反応できなかった私たち・・・。そう、繰り返し練習したことを本番でも披露する、というアタマとカラダの使い方をしているのです、私たち。本番だけ特別なことをする、というのは相当に難しいのだ、と実感しました。
もうひとつの“仕掛け”は、4楽章のテンポ。速い2拍子だけれど、拍子感が停滞気味に聞こえるので、同じ速さでも1つ振りでやってみます、という提案がされたのが今朝。one
in a bar(=1小節に1つ)の感じ方の方が、確かに音楽的と感じたリハーサルでした。が、本番の1つ振りは、(@o@)と驚くスピード感。え?こんなに速い?と思う間もなく、必死で喰らいつかないと振り落とされそう。実際のところは、それほどのスピードアップでなかったのかもしれませんが、呂律が回る限界の速さがもたらす緊張感は、音楽的には有効だったのでしょう。今朝の提案、というところに、指揮者の頭脳戦を感じました。
河野パパさん撮影の今日の写真、以下のURLにあります。どうぞ各自でダウンロードしてご活用ください。合言葉はアルファベット5文字。鷲宮さんの楽器名です。
http://30d.jp/zzalpha/89
また、来季の練習日程について、伝助の準備が出来ていますので、合わせてご活用ください。
http://densuke.biz/list?cd=QvBqHxuT7mRHmhsa
ではでは、みなさま、良いお年をお迎えください。(Cb:な) |
|
|
|
| 2015年11月15日(日) |
|
|
今日は、今回ベートーヴェンのピアノ協奏曲第4番でソロをお願いしている鷲宮美幸さんとの初合わせ練習であった。鷲宮さんとは2006年にモーツァルトの21案の協奏曲で共演して以来、今回が2度目の共演となる。前回のモーツァルトも武蔵野の歴史に残る鳴円であったが、その本番の後に、次はベートーヴェンの4番をぜひやりましょう、と約束してからすでに10年近く経ってやっと実現したのが今回の演奏会である。
今日の練習所は、あいにくグランドピアノがなく、アップライトピアノでの演奏となってしまったが、そんなことには関係なく、すぐに鷲宮さんの美しい音楽に弾きこまれてしまった。軽やかなタッチ、ppのきれいな音色、ffの力強さ、オケとの絶妙なアンサンブルのうまさ、とにかく「素晴らしい」の一言。そして控えめなお人柄とは対照的に、はっきりと音楽に主張が感じられる演奏なのだ。
この4番の協奏曲は、数あるベートーヴェンの作品の中でも、その独自性、ピアノとオケの絶妙な絡み合いなど、彼の最高傑作と言っても過言ではないと思う。特に第2楽章のオケとピアノのドラマティックな対話とそれに切れ目なくつながる幸福感あふれるフィナーレは、まさにベートーヴェンならではの世界である。この傑作を、わしみやさんと共演できる幸せをつくづく感じる練習であった。オケはまだまだ出来ていない部分もあるので、本番まであと2回の練習で、さらに磨きをかけて、聴きに来ていただいたお客さんにもこの素晴らしい協奏曲を堪能していただきたいと思う。(T.N.Vn)
|
|
|
|
| 2015年11月8日(日) |
| 選曲会議 |
練習の後に行われた“選曲会議”に参加したので、その報告をします。とはいっても、決定事項の公式発表は別の場でされるので、今日の練習日記では様子の報告です。
誰でも自由に参加できるこの“選曲会議”。練習所の小学校から、話し合いの場所の玉川会館へ移動して、集まったのは13人ほど。お煎餅とお団子、お茶で一息ついている間に、小さいスピーカーとラジカセがセットされました。スマホをyoutubeにつなぎ、それをbluetoothでスピーカーに流せば、CDなしでもいろいろな曲を聴き比べられるというわけです。対するアナログ派のために、分厚い名曲解説全集が6冊。曲ごとの編成(管楽器がそれぞれ何人ずつ必要か、など)、おおまかな演奏時間や譜例などが載っています。
次の演奏会は6月。会場は秋川。指揮者も決まっていますが、協奏曲の予定はありません。原案がわりの“やりたい曲”の第1案として、ハイドンがあがりました。早速youtubeで音源を流します。「いい曲だなぁ。」それに続く後半の曲には、シューマンが。でもメンデルスゾーンもいいよね。それぞれ、音源が流れるたびに「いい曲だなぁ。」「こっちの方がいい曲だなぁ。」・・・と言っているとなかなか決まりません。組み合わせとしては、前半がハイドンで後半がシューマンかメンデルスゾーン、で良いのかな? 演奏時間がやや短いから、もう1曲なにか・・・という話も出ましたが、しっくりくる曲が見つかりません。2曲でもよいかな?
第1案に対抗して「ほんとは、この曲が好きなんだよね・・・」「これ、いつか演りたいんだけどなぁ・・・」という、個人的にイチオシの曲をつぶやく声が、あちらこちらから聞こえてきました。シベリウス、ブラームス、ベートーヴェン、そしてドヴォルザーク・・・そのたびに、「うちの団では、まだちょっと早いよ?」とか「いい曲だけど、うちの団でやるには難しすぎなんじゃない?」という声も聞こえてきます。youtubeで音を聴いたり、編成を調べてみたり。まぁ、ねぇ。難しくても、やりたい曲をやるのがアマチュアなのですが。あとは、見解の統一が見られるかどうか、かな。l
意見がある程度出尽くしたところで、シューマンとメンデルスゾーンで多数決になりました。「えぇっ、どっちも好きな曲なのに、どうしよう?」というつぶやきも聞こえましたが、眼をつぶって挙手!! まるで中学生みたいです(苦笑)。さて、どっちに決まったでしょうか? 次の選曲会議には、あなたの“やりたい曲”を押してみませんか?(Cb:なおちゃん) |
|
|
|
| 2015年11月1日(日) |
| 合宿、無事終了しました!! |
|
今、NHKの「クラシック音楽館」でベートーヴェンの協奏曲4番を聴き終えたところ。さっきまで合奏していた曲を、絶妙なタイミングで映像つきで復習ができた。やっぱりこの曲、いい曲だわ。今日は、そのピアノ協奏曲とピアニストの話。
10年ぶり(?)ぐらいのオケの合宿で、残念ながら肝心のピアニストは都合が合わずに来られないとのこと。ソロ合わせは別の機会にやるとしても、せっかくピアノがあるなら、誰か弾く人いない?という話題になったのが1か月前の打ち合わせのとき。ふと思いつきで、友達のNさんにメールしてみた。「ソリストが来られないのだけど、オケの練習に付き合ってくれそうな、奇特なピアニストを探してます。オケの私たちがソロとの絡みがわかればよいので、カデンツァは弾かなくてもOKです。どうかしら?」すぐに返事が来て、「ベートーヴェン、5番は弾いたけど4番は弾いたことない。けど、ちょっと面白そう!! でも、私の腕で1か月で何とかなると思う?」・・・あはは、何とかなるかどうかなんて、私にはわからないわ。ともあれ、ボランティアのピアニストを確保できたわけだ。しかも、協奏曲以外の時間に自分でも練習がしたいから、と電子ピアノ持参。1泊2日の全日程での参加。もう有難いやら申し訳ないやら・・・。
そして合宿当日。「せせらぎの宿ごかばし」の音楽ホールにあったのは、ヤマハのフルコンサート用の大きなピアノ。このピアノにNさんが大喜びしたのは言うまでもない。これを使っての協奏曲の合奏となった。オケの私たちにとっては、いつもは無い音(=ピアノ)が聴こえてくる合奏である。ついついピアノを聴いてしまうとズレたりオチたり。微妙なテンポの変り目で、先に行っちゃったり出遅れてしまったり。「ここはほんのちょっと待って」と指示されたので、これまでは何となく指揮を見ながら待ってたけれど、実はピアノの揺らぎを聴いてその揺れに合わせるところだとわかったり。ピアノを聴いてしまうと後打ちが遅れてしまい「ここはピアノに合わせるのでなくて指揮に合わせて」と指示されたり。この曲は、そういうアンサンブルのツボがたくさんあるのだ。その箇所ごとに、誰を聴けば良いのか、誰に合わせればよいのか、それぞれヒントがある。この2日間、私たちがそれを掴むのに、Nさんのピアノはおおいに役立ってくれた。ありがとうございました。
美しいピアノソロにばかり耳がいっていて、この曲はオケと合わせるのが難しいということを忘れていた。ロンドン交響楽団とマレー・ペライアのピアノを聴いて、合宿の復習ができた。それにしても、やっぱりこの曲はいい曲だわ。うっとり聴いていてオチないようにしなくちゃ。
(Cb:なおちゃん)
|
|
|
|
| 2015年10月25日(日) |
|
|
練習日記をを書くのは初めてになります、4月に入団したビオラのR.U.です。 この日も加門さんに来ていただいて、エグモントと交響曲、アンコール(初)の合奏をしました。
エグモントは曲決めで私が提案したら採用された曲なので、弾くことができて嬉しいです。 シューベルトは相変わらず難しいです。個人的に1楽章が一番好きで、4楽章が一番苦手なので、段々自分の中のテンションが下がっていくのがつらいです。
今回の本番には私の高校の同期がバイオリンで乗ることになり、かつて同じ曲を作った仲間と、今お世話になっているところで弾くというのは不思議な感じだなと思っています。毎回越境して練習に来てくれる彼女に感謝です。
次回は合宿なので、気を引き締めて頑張りたいと思います。
|
|
|
|
| 2015年10月11日(日) |
|
先日、「音楽の友」WEBコンサートガイドを見ていたら、新日本フィル定期のプログラムに、シューベルト交響曲第4番「悲劇的」があったので、サントリーホールに行ってきました。指揮はコントラルト歌手で指揮者のナタリー・シュトゥッツマン。
最前列の席を購入して、第2ヴァイオリン1プルトのボウイング・弾き方をじっと見ていたら、トップサイドの女性奏者と眼が合ってしまった(ような気がして)、それ以後はやや斜め目線にしました。プロオケは、武蔵野がもたつくような箇所も事も無げに弾き進めていきますが、4楽章が終わった時に、トップ奏者がサイド奏者に「疲れたねー」みたいなことを言いながら右手首を振っているのを見て、何か妙に嬉しくなり、4楽章を少し頑張ろうという気持になりました。でも、4ページほぼキザミっぱなし(音は細かく動く)、速い、逆弓ありなどなど、大変です。(Vn:S.O.) |
|
|
|
| 2015年9月27日(日) |
|
|
27日(日)より、加門先生に来ていただいての練習となりました。 曲は『エグモント序曲』と『シューベルトの交響曲第4番』を練習しました。 全体を通してテンポの確認をしながら、弦楽器の「アップ・ダウン」の確認をメインに行いました。
私はTpである為、後の席からその様子を見ていましたが、改めて弦楽器の難しさを知った気がします。 また、加門先生の指示に即座に対応する団員に「凄いなぁ~」と感心してしまいました。
私のパートは弦楽器と違い、楽譜上たまにしか出番はありませんが、その分ミスの無いようにしなければと気を引き締めました。
来月末には合宿を行い、演奏会に向けて団員も盛り上がっていきます。この『練習日記』をお読みの皆様、是非とも私達の演奏会へ足を運んでくださいませ!皆様に感動をお届けいたします♪
Tp:T.I
|
|
|
|
| 2015年9月13日(日) |
|
|
今回は、府中の森芸術劇場「ウィーンホール」利用抽選会のお話をします。 ウィーンホールは、音響性能を最重要視したシューボックススタイルで、残響時間まで調整できるホールです。クラッシックファンとしては魅力あふれる最高の演奏会ホールなのです。定員は522名で、武蔵野室内アンサンブルとしてはピッタリです。しかし、人気があるため利用希望団体が多く、利用月の15ヶ月前の月始めの1日に抽選会が行われることになっています。その抽選会に私が代表で参加することになったのです。抽選は、該当日を希望した団体代表がジャンケンし、勝った順番でトランプカードを引くやり方です。エースがでたら当選です。
私はくじ運が悪く、60年間宝くじを始め、くじに当たったことがありません。それで他の方にお願いしたかったのですが、今回の抽選日の9月1日は火曜日で私しか参加できる人がいなかったのです。ところがなんと当選してしまったのです。なんで?人生の運を使い切った?そのカラクリを説明します。
当日の朝、私は、団長(私の妻です)の運の強さにあやかろうと決めたのです。団長が言うには、「ジャンケンはチョキが勝ちそう。カードが3枚だったら左が当たりそう。」念のため私はカード5枚の時も確認しました。「カードが5枚だったら、左から2枚目が当たりそう」、これで、なんとも心安らかになりました。
いよいよ抽選です。希望日は最も希望の少ない日曜日にするのが最初のテクニックです。結局12月18日に決めました。最終的には7団体での抽選になりました。最初は7団体代表のジャンケンが始まりました。「最初はグージャンケンポン」。「しまった! ジャンケンは一回では決まらないじゃないか。最初のチョキしか考えてないぞ。もう全部チョキにしちゃえ」と、かなりいい加減な気持ちで続けました。「じゃんけんじゃんけん・・・・」なっ、なっ、なんと、勝ち残って1番になってしまったのです。「これはまずい!」1番ということは、カード7枚から選ばなければならないのです。私は5枚までしか想定していなかったじゃないですか。でも、5枚で左から2枚目なのですから、7枚なら左から3枚目を引くしかありません。ママヨ。またびっくり、引いたカードはエースだったのです。「ヤッター」いきなり大声を上げてしまいました。
ということで、全面的に団長の運と感に頼ってしまったという、情けない話でしたが、みなさんも今度抽選会に参加してみませんか?どなたでもOKです。また、みなさんの近くにいい音響のホールがありましたら、そこで試してみましょう。是非やってみたいと思われた方は、最寄りの運営委員まで声をかけてください。 (BassY.K.)
|
|
|
|
| 2015年8月30日(日) |
|
|
8月30日。昭島公民館で、1カ月ぶりの練習が行われました。指揮者がお休みのため、Mシェフが菜箸の代わりに指揮棒を持ち、コンダクターを務めました。
まずはエグモント。アレグロから細かく練習をしました。
「3拍子の曲で3泊目から入るのは、日本人は苦手なんですよ。失敗してもいいので、失敗しながら、入るタイミングを見つけて行きましょう。」という言葉に、温かさを感じるとともに、料理も同様であることを思い出し、さすがシェフ!と、心の中で拍手喝采でした。
続いてシューベルトは、4楽章から、3、2、1楽章へと進みました。各楽章では、音程やリズムを合わせるため、スピードを落とした練習です。
シェフは、打楽器奏者であることから、一拍目を合わせたり、管楽器と弦楽器のリズムの違いにこだわったりする練習が中心です。でも、時折見せるエア・バイオリンを弾く姿は、バイオリニストのように手首がしなやかに曲がり、なかなか様になっています。また途中で「ささみのようなパサパサした音はダメ、ジュワッとジューシーな音を出しましょう。」と言うなど、さすがシェフだと思われる言葉で、みんなを笑わせ、納得させてくれました。
エグモントもシューベルトも、心躍る音楽です。12月には、ぜひ大勢の方にいらして欲しいと思っています。(Cl : N.Y)
|
|
|
|
| 2015年7月26日(日) |
|
こんにちは、Vnのゆーじんです。 夏!年々暑さへの耐性が弱くなっています。地球が熱くなっているのか、自分が衰えているのかはわかりませんが。我が家では母氏による節電の厳命のもと、深夜までエアコンを使わずに生活しているため、バイオリンの練習を10分もしようものなら、サウナから出てきたような汗をかいております。よい子は決してマネをしないでね。
今なら業務用の冷蔵庫の中でも練習できる気がします。よい子は決してマネをしないでね。
さて、冗談はさておき、今回の演奏会より、正式に武蔵野室内アンサンブルのメンバーとして参加させていただくこととなりました。 以前、大学時代のオケでお世話になった某先輩にお誘いいただき、トラでご一緒させていただきました。
その先輩は、私に(オケの醍醐味と)お酒の美味しさを教えてくれた方でした。軽い気持ちでお誘いを受けましたが、あれよあれよという間に入団してしまいました。その先輩とは、いつの間にか家族ぐるみの付き合いになり、両家ご挨拶が来る日も近いことやら・・・
武蔵野での練習は、大学時代に参加していたオケとは全く違う環境で毎回がとても楽しく、年代も様々な方がいらっしゃるので非常に多くの刺激を受けます。私が入団する決めてとなったのも、他ならぬ皆さまの人柄に惹かれたからです。仲間というより家族に近いような、そんな温かさを放つオケで是非とも弾きたい、そんなことを思ったのでしょう。
前置きが長くなってしまいましたが、7/26(日)の練習について少しばかり。 赤いメガネが素敵なマエストロに振っていただきながらの練習となりました。初めてシューベルトの合わせに参加しましたが、まだまだ譜面にある音符との追っかけっこ。顔面からは、曲にふさわしく悲愴感を漂わせていたのですが。弦楽器の方が多かったため、ほとんど弦練でしたが、細かい音に気を配ること・弦内でのアンサンブルを大切にすることも改めて感じました。そして、ビブラートに頼らずに表現する。これが本当に難しい。まだまだ成長の余地があるはず・・練習次第・・・
そんな毎回の練習が楽しいです。みなさま、今後ともよろしくお願いいたします。
そういえば、オケが違っても変わらないことは、練習後のビールがうまいということ!・・・ってあれれ、みんな帰っちゃうんですか?次回は飲みにいきましょうね!それまでにはしっかり練習してきますので。
(Vn:ゆーじん) |
|
|
|
2015年7月12日(日)
|
|
7/12(日)は次回の演奏会へ向けての2回目の練習でした。 バイオリンパートは技術的なレベルが高い方々ばかりなので、その人たちを当てにして全く練習をせずに挑みました。次回の練習までに必ず個人練習をすることを、アンサンブルリーダー始め関係者の皆様に誓います。 前述の通り、個人的には反省点ばかりでしたが、他のみなさんの演奏が素晴らしく、すっかりベートーベンやシューベルトの魅力に取りつかれてしまいました。
武蔵野に入団させていただいて半年が過ぎました。今まではあまり交流のなかった管楽器始め、他の楽器の皆さんとも距離が近く感じ、また個人個人のレベルが非常に高いので勉強させていただくばかりです。打ち上げ・飲み会でも、アンサンブルリーダー始め、皆さんの音楽に対する熱い気持ちを目の当りにする度に、入団させていただいて本当によかったと思っています。
これからもよろしくお願いいたします。(MK) |
|
|
|
| 2015年6月28日(日) |
|
こんにちは。VnのT.N.です。先日の演奏会より、正式に武蔵野の仲間に入れていただくことになりました。武蔵野には、実は中学二年生の頃からかお世話になっていたのですが、学生だったこともあり、トラという身分を利用して甘い蜜だけ吸わせていただいておりました。そんな形の参加に少々後ろめたさを感じ始めていた先日、練習後の飲み会にてすっかり酔っ払った私は、翌日、気付くと団員になっていたのであります。時には流れに身を任せる事も大切であります。
しかし、特筆すべきは、先日の演奏会を通じて、なんと五名もの仲間が新メンバーとして活動することとなったこと。こんなことは武蔵野史上始めてであり、武蔵野が着々と楽しいオケになっている証拠ではないでしょうか。
さてさて、前置きが長くなりましたが、日記とのことなので、本番の日の話を少々。
6月14日、皆様の温かいご支援のもと、武蔵野は第33回目の定期演奏会を迎えることができました。今回はその時のお話。ご来場頂いている方はご存知の通り、武蔵野の男性の本番衣装は、「上下黒」。下はまだしも、この「上の方」が意外と曲者で、限られた場所(すなわちUNIQL◎)でしか殆どお見かけしないのです。
もちろん、武蔵野は初めてではないので、黒シャツは持っている筈だったのですが、なぜか家の中で行方不明。しかし、私は知っていたのです。秋川にUNIQL◎があることを。そこで私は本番当日、リハーサルの後、ホール横の東急ストアに赴き、足取り軽くそのまま真っ直ぐUNIQL◎……
が、ない。有ったはずのUNIQL◎が、ない。そこにあるのはなんと、シマMラ。何度読んでも、シマMラ。逆から読もうと、シマMラ。あぁ、シマMラ…シマMラ…。
脳内に響き渡るシマMラの響きに若干の殺意を覚えつつ、まぁしかし、シマMラも洋服屋なので、黒シャツくらいあるかと思い直したのですが、前述の通り、黒シャツは意外と出会えないレアキャラのため、あえなく撃沈。店員さんによると、UNIQL◎は昨年移転し、ここから歩いて30分とのこと。電車に乗って近場まで買いに行くかと企みましたが、ここは秋川、電車の本数の少なさには定評があります。開演まで、あと一時間強。団員としての初舞台、このままでは全身を黒塗りにするしかないのか。高校時代の自分なら上裸でもばれなかったかも…(水泳部でした)。そんな恐怖がふつふつと湧いてきた時、私は未曾有のアイデアを思いついたのです。
……そのアイデアについては、残念ながらここで意気揚々と語るつもりは毛頭ございません。ただ、折角ですので、ここまでお読み頂いた方々に、本事件で私が心に刻みこんだ教訓をひとつ。 「息子は一生、母親には逆らえない」
マザーケイコ託送サービス(株)の世界最高のサービスにより、私は無事に初舞台を踏むことができたのであります。謝々。 とまぁ、こんな感じで無事に本番を迎えた私ですが、何のお陰か本番も思いのほか上手くいき(自己満ですが)、大変美味しいお酒を頂く事ができました。本当に楽しい演奏会でした。
オケの醍醐味は、何と言ってもいい演奏の後の宴会。今後も美味しいお酒を目指して日々精進して参りますので、皆様今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。(Vn:
T.N.) |
|
|
|
| 2015年6月7日(日) |
| 今年の上半期(?) |
年に2回の定期演奏会を持つ私たち。半年をスパンに色々なことを回していくことを積み重ねて、もう30回超え!!なのですが、今年の上半期(?)は、小さな変化がいくつもありました。
まず、新しいメンバーが複数入団されたこと。少人数の楽団の私たちは、決まった顔ぶれでアンサンブルを練っていくのが常ですが、演奏会を聴いて「入団したい」と門を叩いてくれた方がいらっしゃるのはとても嬉しいことです。さらに、それぞれの事情で団を離れていたのが戻ってきてくださった方も。高校生から80代まで幅広いメンバーがいますので、親の介護や孫の誕生、メンバーご自身の結婚や出産や育児、転勤や転居などいろいろな事情で団を離れる方もいらっしゃいます。でも、状況が変わった時に、またいつでも戻ってきてくださると嬉しいです。
また、団の運営や選曲などを係の方々以外にもオープンにして、興味のある方、時間の許す方が参加してもらいやすい形をとりました。大所帯の楽団なら「パートリーダーがメンバーの意見を取りまとめてください」となるところを、「係以外の人もご自由にどうぞ」としたところ、気楽に参加してくださる方が増えました。その結果決まったのが、次回12月のの演奏会の曲目です。いろいろな人の意見が反映されつつ、ひとつのまとまりを保って続けていける団になってきたのかなぁと思います。また、演奏会のチラシを会場近くの飲食店に置かせていただく広報活動は、平日昼間が比較的自由に使えるメンバーで続けていますが、こちらの助っ人も増えていくと良いなぁと思います。
そして、来期の演奏会の楽譜を、今期の演奏会前に配っておく、という画期的な(?)取り組みを始めました。半年スパンで練習をしていく開始時期に、効果的なスタートダッシュとしたいですね。
そんなこんなで、来週は33回目の定期演奏会。土曜日にはソリストとのソロ合わせもあります。本番1週間前で、ビゼーの4楽章の演奏可能な最速スピードは♪=??という話題も出ました。焦らず慌てず、楽しみつつの本番になりますように。(Cb:なおちゃん)
|
|
|
|
| 2015年5月24日(日) |
| ソロcello初合わせとエンドピン |
|
本日はご待望のソロcello初合わせでした。 毎回ソリストをお迎えする時は、それまで入念に下準備をした体制でお見合いの日に臨むふたり(?)の様な感じでしょうか(*^^*) 我々オーケストラの前奏から、ソロcelloの出だしまでのあの間! 緊張の一瞬です。 気持ちよく入って頂けたかな? 大丈夫かな? 顔色を確認しながら第1Themaへ…
今回のソリスト、渡邉さんは某Sメソード出身で私にとっても大先輩のOBです。 今回は某団体の各お教室にも沢山チラシを置かせてもらっています。
実にテクニシャンと定評のあるチェリストでいらっしゃいます。
とにかく、Themaごとの切れ目やフレーズをうまく繋ぐのがとてもとても大変なこの曲。 しかも、渡邉さんは毎回違うかもしれませんが〜と。 それで当然!
とにかくソリストを見ないとどうにもこうにもいきません。
それには、とにかくこちらも暗譜の覚悟でつけていかないと。 練習練習!
私事ですが、今日はやたらとエンドピンが滑って大変でした 先をよく削ってなかったり、床材によってはどんなエンドピンストッパーを使っても滑りはしますが。
私のcelloの先生は、「一生懸命弾いてる時にズルっ!ってウケるよね〜」とよくおっしゃいますが^^; 結構恥ずかしいです…。
celloやコントラバスのエンドピンは、床を伝って音を響かせる役割があります。材質は鉄、カーボン、チタン、真鍮系などありますが、それぞれ音色が違うので、こだわる方はすごくこだわります。
さて、今回のロココで私が最も好きな部分の1つが第6Thema冒頭です。フルートの主題ソロにソロcelloがtrillでついてゆきます。 その軽快なtrillが可愛らしくて、子どもの頃にこのツボにハマってしまいました。
聴きどころです(*^^*)
今回のオリジナル版は同じくらい有名なフィッツェンハーゲン版から世にお目見えするまで多くの技術(X線で筆跡判定)と歳月を経たそうで、今ではこの原典版はチャイココンクールチェロ部門の課題曲となっています。
とにかくチェリストを迎えての定演ということが本当に嬉しいです! ズルっとしないよう、残りの練習〜本番まで楽しみたいと思います!(Vc.U子)
|
|
|
|
| 2015年5月17日(日) |
| 他己紹介? |
ホームページ担当(な)です。最近、嬉しいことに、新しく入団される方や久々に団に戻って来られる方が増えています。このところ、そんな方々に、自己紹介(と“練習日記”の宣伝&ご協力依頼)を兼ねて、当欄を書いていただいています。今日はチェロのT子さん・・・の代理・代筆です。「えぇ~??これ以上私のストレスを増やさないで~。私の代わりに、あなた何でもいいから書いて~」とT子さんの弁。
T子さんは、武蔵野の合奏で初めてご一緒したのは、彼女がシンガポールから戻られた約10年前。その後、タイのバンコク、インドネシアのジャカルタ、とご主人の転勤に伴って海外暮らしが続いていました。が、時折、一時帰国をされると楽器持参で練習場へ遊びに来ていたので、あまり久しぶりの感じがしません。あれ、本番も乗るのよね?と訊くと「いやいや、来月にはもうジャカルタに戻るから~」なんてこともしばしばだったのですが、駐在地へ戻るのを延期して、本番に乗ったこともありましたね。今回はメデタク(?)本帰国となり、正しく団に復活されました。
大人になってからチェロを始めたT子さんは、練習をたくさん積まれた努力家。チャームポイントは、弾いているときの思い切りのよい背中と、たまに拍子をとっている右足先(^^)。今後とも頼りにしてます。(Cb:なおちゃん) |

(練習日記、久々の写真つき。
原稿を書いてくださる方々、
写真やラクガキもOKですので
気楽に頼まれてくださいね。) |
|
|
| 2015年5月10日(日) |
|
入団してから早くも5ヶ月経っていました。皆さん、お世話になります。
「こんなオーケストラに入れるといいな」と思ってから3年と5ヶ月。「願いって実現するのね~♪」といつもありがたく思っています。
今回の練習はモーツァルトとビゼー全楽章。加門さんのマッハスピードにもすっかり驚かなくなりました。ビゼーの交響曲は素直な和音が並んでいる印象で、総じて明るく澄んでいる。その分単調になってしまう可能性のある難しい曲だなと思います。ふわっと湧き上がるような、とてもとても綺麗な曲なので、演奏者として充分に楽しみたいですし、聞いてくださる方にも心地好く楽しんでもらいたいです。
大概2ndオーボエというのは決して目立たず1stオーボエに付き従う陰の立役者といったイメージなのですが、ビゼーは2ndオーボエも表に出したいみたいでチョコチョコと目立たせてくれます。それは楽しいのですが、2楽章はちょっと意地悪じゃない?と思ってしまいます。2本のオーボエを交互につないで1本に聞こえるようにって、音色も技術も違うのに何だってそんな難しいことをさせるんだろう…
と文句を言っても始まらないので、これもステップアップのチャンスだと考えてがんばります!
気がついたら演奏会まであと1ヶ月。大事に過ごさないと! (OB:M.N) |
|
|
|
| 2015年4月26日(日) |
|
今日の練習は指揮者、ソリスト共に、団員による代振り、代奏でしたが、 特に「ロココ」は改めて難しい曲だと痛感しました。 ソロと伴奏というのではなく、各パートがソリストと対話をしなければならないのですから・・・。
ソリストの渡邉先生は、普段は物静かな方ですが、いざチェロとなると、素晴らしい表現力とテクニックを持ち合わせている方なので、「ロココ」はとても楽しみです。
そんな先生とアンサンブル(対話)が出来るように、本番まで練習頑張ります! (Vc:Y.U) |
|
|
|
| 2015年4月12日(日) |
|
|
トラとしては過去3回ご一緒させていただきましたが、2月からは団員として参加させていただいております。よろしくお願いいたします。
前回の練習は仕事で出られませんでしたので、私にとっては、加門先生の指揮による初めての練習となりました。どんな感じで練習が進んでいくのか楽しみにしていましたが、結果、とても充実した3時間でした。
練習した2曲全体にわたって、望むテンポ感や個々の部分の音の処理法、バランス、強弱などをわかりやすく示していただけたので、今後の練習の見通しがずいぶんと立ち易くなったと思います。
今日の練習で指摘を受けた点を直していければ、室内オケらしい楷書体のクリアな演奏は実現できそうです。でもどうせやるなら、もっと深い音色や自由なアゴーギクが表現できたら素敵ですので、そのためにも、これからの練習を通じてもっと曲を自分に引き寄せていけたらいいなと思います。
あと、Fg吹きとしては、今日の練習で試したのですが、ビゼー2楽章の、下のAのppやpppの伸ばしで、ロック+Hキーを押さえて音程を低めにしてみました。今日のリードではとてもうまくいったのですが、他のリードでも順に試していこうと思います。
(Fg: T.K.)
|
|
|
|
| 2015年3月22日(日) |
|
|
入団して初めて練習日記を書かせていただきます!!
今日の練習は、指揮なしでビゼー、モーツアルト、チャイコフスキーの順に通しました。通してみてずれそうになったところや強弱を、コンマスNさんの指導のもとに確認しました。
細かく強弱を見てみると、ffとfは両方強ければよいわけではなく、意識して違いをつけなければいけないなと思いました。
今日は弦が少なかったので、木管の動きがよくわかってよかったです。ビゼーの1st Vnは高い音や細かい動きが多いので、ちゃんと弾けるように頑張ります。。。(Vn:E.K)
|
|
|
|
| 2015年3月8日(日) |
|
今日の練習は分奏である。いつもの練習は全部の楽器が一緒に練習するのだが、分奏はパートごとに分かれて練習する。今日は弦楽器、管楽器に分かれてそれぞれ別の会場で練習した。いつもの練習以上に、より細かい部分を確認しながら練習することが出来るので、時々この様な練習をすることは必要だと思う。
私は弦楽器の練習を担当。弦楽器特有の問題として、ボウイングをそろえるという作業がある。つまり下げ弓(ダウン)と上げ弓(アップ)を決めることで、これが結構手間のかかる作業なのである。各パートごとに上げ下げの都合が合わないことも多い。理想は音楽的でしかも弾きやすいことなのだが、これがなかなか決まらず、結局は試行錯誤の繰り返しになる。これで本番の指揮者の練習が始まると、指揮者の解釈によってもボウイングは変わることになるのだ。とにかく今日はビゼーとチャイコフスキーのボウイングを一応決めることが出来た。また、弦楽器のアンサンブルを作ることも分奏の大きな目的だ。今日は各パート同士よく聴きあってみんなが音楽の構造や仕掛けを理解できるように心がけながら練習した。ちょっと気を付けることでアンサンブルはとてもよくなるものだ。これで次回の全体合奏がちょっと楽しみになった。ただ、今日1日ではまだ十分ではないので、あと何回か、分奏練習を入れていきたいと思う。(Vn:T.N.) |
|
|
|
| 2015年2月22日(日) |
| アンサンブル大会 |
|
毎年恒例のアンサンブル大会、昨年赴任先の中国から帰国したT.N.さんも本格参加(赴任中も一時帰国して参加していましたが(笑))、チェロのK.N.さんも久々の登場で充実したひと時になりました。そして、昨年末から1月にかけて新しく団員になられた3名も、それぞれFg Duo、木管四重奏、弦楽四重奏などで大活躍でした。以下、簡単ですが曲目とプチコメントです。
1)ドップラー「セヴィリヤの理髪師メドレー」Fl Duo・・・さすが、団発足以来の磐石コンビ、難しいフレーズも息ぴったりの名演奏でした。
2)ロッシーニ「弦楽のためのソナタ4番」・・・Vn/Vc/Cbという珍しい編成ですが、Vaに気を使っていただいて、2nd VnパートのVa版譜面が・・ これが相当難しくて、一緒に弾いた2ndのM.K.さん(Vnの新団員!)に溺れそうになるところを助けていただきましたm(_
_)m アンサンブルとしては、T.N.さん指導の練習の成果(?)がそこそこ出ていたかな(!?)
3)モーツァルト 「ファゴットとチェロのためのソナタ」Fg Duo・・・チェロパートをファゴットで演奏するのは(息が)きついらしく、楽章毎にパートを交代しながらのチームプレー!?
見事に3楽章を奏破した後のアンコール、「子守唄東西対決(五木の子守唄&ブラームスの子守唄)」に結構癒されました(笑)
4)ラロ 「スペイン交響曲」 ・・・中学生の頃から武蔵野で活躍しているE.K.ちゃん(もう高校生)、お母さんのピアノ伴奏も素晴らしく、堂々のソロでした。 「うーん、成長したねー」、という大人達をすっかり追い越しているかも・・・。
5)クーラウ 「6つの易しいスコティッシュダンス」・・・Obの新団員Nさんを交えての木管四重奏 数日前のエントリーで簡単に準備してしまう方々、これで木管パートは安泰だ〜、と嬉しくなります。
6)ハイドン 「弦楽四重奏 ”ひばり”」・・・ 意外にやらないハイドンのカルテット、シンプルなんだけど深い・・やり残した2・4楽章もいつかやりましょう!
やはりカルテットは楽しいです。
7)「ボロディン・中央アジアの草原にて」 再び登場のE.K.ちゃん、お母様伴奏でお友達の音大生(Vn)との共演 冒頭のフラジオ、オクターブ下の旋律等、実力派の演奏を披露頂いたお友達の音大生、
お家が近所のようで、美しい若手Vn団員が増えるかも!?と、団員一同(特におじさん達が!?)、打ち上げですっかり浮き足立ってました(笑)
8)最後は全員参加のモーツァルト交響曲12番 後半、気持ちは打ち上げのビールに(?)、終わった瞬間の皆の笑顔は完全にそうでした(笑)。今回は、都合がつかなくて出られない人もあり、こじんまりとしたコンサートでしたが、新団員の方々との懇親も深まり楽しく過ごせました。
色々と調整頂いた幹事さんたち、ご自宅レッスン室を使わせていただいたK先生、打ち上げにご自宅を提供いただいたKさんに感謝感謝です。 また次回も楽しみですね!
(Va:K.U)
|
|
|
|
| 2015年2月8日(日) |
| 総会の報告 |
|
年に1度の総会が行われましたので、この場を借りてご報告します。
まず、2014年度の活動報告と会計報告、そして2015年度の活動計画と予算案、という段取りで進みました。活動内容については、年2回の定期演奏会のほか、2月のアンサンブル大会、5月のBBQ大会、新年会・忘年会や納涼会(?)などが適宜行われています。演奏会はホールをほぼ1年前には予約しておく必要があるため、2015年12月の演奏会までは日取りと場所が決まっています。指揮者も、1年先の仕事(本番)の予定が入ることから、1年前までには依頼をした方が良いよね、という話題も出ました。
会計については、団員数の少ない(=お財布の小さな)楽団ではありますが、団費や演奏会ごとのチケット代による収入と、コンサートホールや練習場の使用料、指揮者やソリストへの謝礼、足りないパートをお手伝いいただくエキストラさんへの謝礼、雑費としてホームページ使用料やチラシ・プログラムの用紙代・印刷代、案内状や通信費、楽譜のコピー代などがかかります。曲目によっては楽譜購入費用や著作権料を払わなければならないことも。年に1度、会計報告をまとめて監査を行う係のみなさん、総会への準備ごくろうさまでした。
役員選出は、前年度とほぼ同じ顔ぶれにお願いすることになりました。○○委員・○○係とついていますが、何しろ30名足らずの楽団なので、団長を中心に家族的な雰囲気で回していくことになります。総会資料についている団員名簿では、結婚・出産や家庭の事情ででお休みされている方、そこから復帰予定の方などの情報交換もありました。また、管楽器に新しいメンバーを迎え、ほぼ欠員が無くなったという嬉しいニュースも。あとは弦楽器、とくにヴァイオリンを充実させなくては!! (Cb:なおちゃん)
追記:2月22日のアンサンブル大会、今年は小規模で行われるため、当初の武蔵野会館ではなく、メンバーのご自宅をお借りして開催することになりました。本番は北原家、打ち上げは金成家です。観客として聴きに来ていただける方、3時前を目安に金成家に来ていただくか、団長までご連絡をお願いします。
|
|
|
|
| 2015年1月25日(日) |
| ようこそ!武蔵野へ |
|
久しぶりの練習日記です。楽しみにしてくださっている方々、長らくお待たせしてしまってすみませんでした。
さて、先日の演奏会の後、武蔵野は、オーボエとファゴットに新入団員を迎えました。パチパチパチ~~♪ (他のパートにも、もう少しで入ってくれそうな方がいるとかいないとかの噂はあるのですが、プレッシャーになってもイケナイので、今日のところは触れません^^;)武蔵野の演奏会にお客さんとして聴きにいらしてくださったり、お手伝いとして一緒に舞台に載ってくださったりした方々です。ありがとうございます。練習をご一緒しながら、仲良くなっていけることが楽しみです。
一説によると、中央線沿線は各市ごとにオーケストラがあるとか、各駅ごとにあるとか、ともあれ、それだけのアマチュアオーケストラがあるわけで、あまたあるうちのどこで/誰と一緒にやるのか、というのはとても悩ましいです。家から近いところ、練習日が都合が良いところ(土日のことが多いですが、平日夜に練習している楽団もあります)、友達がいるところ、楽団のカラーが自分と合うところ・・・etc。50人規模の交響曲をレパートリーとするアマチュアオーケストラが多いなかで、武蔵野は、30人規模の小さな編成を生かした曲を演奏しているのが特色なのかも。それを知って入団してくださっているのがとても嬉しいです。さらに、管楽器のほとんどは定員2名、降り番なし。きっと相性もあるのだろうな、と弦楽器の私は想像しています。今後とも、どうぞよろしくお願いします。
さて、今日の練習。モーツァルトの第32番交響曲の楽譜が届きました。さらっと初見で合奏。こういうシンプルな曲は、すぐ出来そうと甘く見ていると、キチンと仕上げるのに神経を使うもの。油断大敵です。ビゼーの交響曲とチャイコフスキーの協奏曲も、アンサンブルリーダーの指揮のもとに練習しました。技術的に難しいところはあるけれど、曲の流れや仕組みを理解して、丁寧に譜面を読んでいく段階です。そうそう、弦楽器はボーイングも考えなくちゃ。(Cb:なおちゃん)
|
|
|
|
| 2014年11月30日(日) |
| ホルンホルンホルンホルン♪ |
|
本日は、ホルンコンチェルトの合わせを行いました。毎回、コンチェルトのソリストが登場すると練習にも緊張感が漂います。今回のソリストは、満を持してのご登場、前コンミスYさんのご主人ホルン奏者。
以前ちょっとしたコンサート出演のため、練習でYさん宅にお邪魔した際に、遠くの廊下からホルンの音色が聴こえてきました。まろやかで透き通ったような音階にうっとりしたのを覚えています。
私は、ホルンという楽器のことはよく知りませんが、管の長さがとても長く、また楽器自体の歴史も管楽器の中ではとても古い、といったイメージです。
ソロ曲のあと、ホルンの重奏がありました。この管の長さを全部つなげたら、このオケ伴奏隊列をぐるりと何周かできるくらいなのかな??などとくだらないことを考えながら、素敵なホルンの音色に包まれながら伴奏しました(*^^*)。本番が楽しみですね。
ボーイング。
弦楽器はこれが大変ですね。試行錯誤、紆余曲折の末、ようやくシューマンのメインパターンのボーイングが決まりました。慣れるまではどんなボーイングでもしばらく譜面にかじりつきですが、身体がそのパターンを覚えてゆくと、自然と右手が歌うように動きます。
本番まであと少し!! 少しでも身体に覚えさせないと。
最後に、Yさん宅で初めて食べた「納豆キムチお好み焼き」は意外とビックリ!!美味しかったです(*^^*)。(Vc.U子)
|
|
|
|
| 2014年11月23日(日) |
| 遠いところから・・・ |
|
今日は、大阪から、元メンバーのObのTさんが練習にいらっしゃいました。いいえ、正しく言うと、この日の夜にちょっとした練習を東京ですることになっているTさんに、「ついでに、武蔵野の練習に来ちゃえば?」と誘ったのは私です。本番1か月前を切っていて、正規の団員も、お手伝い出来てくださる方も決まっていて、なのに「来ちゃえば?」なんて言って良かったかしら・・・とあとから気が付き、ObのE子さんに尋ねたところ、「ぜひ一緒に吹きましょー。」との温かいメッセージが。木管親分のIさんからも「楽しくやっちゃってください!」とのこと。武蔵野の方々って、本当に心が広い方ばかりで嬉しいです。練習に少し遅れます、と言っていたE子さんが来るまで、と楽しんで吹いていたTさん、結局練習の最後まで吹いていらっしゃいました。山梨から毎回高速道路で練習にいらっしゃるE子さん、ドアの外でTさんの音を聴いていらしたそうです。遠くから来ているのに、外で待たせてしまってごめんなさい。「いえいえ、山梨から来るより、大阪から来る方が遠いじゃないですか!!」・・・・確かにそうですが。
前回の練習では、同じく元メンバーのVcのT子さんが久しぶりに練習に参加。T子さんはジャカルタ駐在中です。時々一時帰国すると顔を出してくれますが、今回は年末まで日本に滞在するために、12月の演奏会の舞台にも乗れるそうです。演奏会に乗る、と決まったので、ちゃんと予習もして練習に来たとのこと、さすが。
HrのKさんは、デリー駐在中。アンサンブル・リーダーのVnのNさんも、今年の2月まで中国駐在でした。そういう私も、3年前までマレーシア駐在でした。
武蔵野は、アマチュア楽団にしては小さな団体ですが、だからこそ、人間関係のつながりが家族的なのでしょう。。どこか他所で暮らすことになっても、東京に来る機会があれば練習に遊びに来るとか、海外駐在が終わって戻ってきたら、元の楽団に戻ってくるとか。帰省したら実家に顔を出す、みたいな感じなのかなぁ。それにしても、小さな団体なのに、自分を含めて海外駐在組が多いのは何故?(^^); (Cb
なおちゃん)
|
|
|
|
| 2014年11月9日(日) |
|
|
今日は、立川「たましんRISURUホール」という、初めて使う練習場でした。展示場に使う部屋とのことで、床も壁も天井も白く、まるでスターウォーズか何かの映画に出てきそうな所でしたね。懐かしいトランペットOKペア(O本さん&K藤さん)も加わってくださり、いよいよ本番1か月前という雰囲気になってきました。
大昔のわたくし事ですが、20代前半の頃、ケルンの大聖堂を外から見ました。ウィーンに行くのに、なぜか飛行機はイギリス着。そしてロンドン中央駅から列車に乗り、当時は国境を超えるたびにパスポートチェックを受けながら、長かったぁ。で、その時、ライン川に沿って移動していたのです。シューマンの交響曲第3番は、ローレライ辺りから始まり、コブレンツ、ボン、ケルン、デュッセルドルフ、と曲は移っていきますが、私が移動したのは逆コースということになります。そう!今日の練習は、5楽章→4楽章→3楽章だったので、まさにその順に! その時、近くを通って眺めたケルン大聖堂は、2本の高い塔がそびえていて威厳を放っていました。4楽章は、あの中で荘厳・厳粛な儀式が行われている感じなのかと思うと、青春の思い出とともに情景が浮かんできます。せっかく近くまで行ったのに、中に入らなかったのは悔やまれますが。
「オイリュアンテ」も話のあらすじを見てみると面白いですね。ヴァイオリンがいくつにも分かれて弾くLargoの所。オイリュアンテの旦那の妹(姉?)が自害したようなんですが、亡霊になって出てきて「このままじゃあ昇天できない」と悲し恨めし語っているところらしいです。そう聞くと、途中から加わるヴィオラのザザザザっていう刻みも鳥肌が立ちますね。
本番が近づいてきましたが、曲のイメージや話を知った上で個人練習やアンサンブルをした方が曲の仕上がりに効果的かなと思い、つらつら書きました。(Fg Y.I.)
|
|
|
|
| 2014年10月26日(日) |
| チューニングのこと |
|
チューニングは、オーケストラが演奏する前に全員が自分の楽器の音程を合わせて、全体の音程を統一化することです。具体的には、オーボエ奏者が基準となるA(ラ)の音を出して、まず管楽器奏者がそのAに自分の楽器の音程を合わせます。管楽器はこれで完了。
次に弦楽器の番ですが、これが問題です。同様に、基準となるAの音程に各自が合わせますが、弦楽器はAの弦以外にあと3本の弦があり、これらをすべて合わせなければなりません。これを、弦楽器全員が同時に行うのですから、いわば騒音の中で各自が自分の楽器の音程を調整することになります。そうなると、自分の音程を聴くために自分で出す音が大きくなり、全体の騒音がますます大きくなる、という悪循環に陥るのです。したがって、チューニングが不完全なまま演奏に入ることもしばしば起こります。これでは、オーケストラのハーモニーは濁ってしまいます。
武蔵野室内アンサンブルは、以前から透明感のある美しいハーモニーを目指しています。そのためには、正確なチューニングが不可欠なのです。特に、ハーモニーの土台である弦楽器のチューニングには十分な時間をかける必要があります。最近の武蔵野の弦楽器のチューニングは、通常のチューニングの後に、全員が解放弦を1本ずつ合わせています。そうすることによって、騒音の中で行った不完全なチューニングを補正することが可能になり、純粋で美しい開放弦の響きを作ることができるのです。
最近は、本番のステージでもこのチューニングを行っており、一部のお客様からは「何かおかしい」との声も聞いておりますが、これが武蔵野の美しいハーモニーの源であることをご理解いただければ幸いです。(T.N.)
|
|
|
|
| 2014年9月28日(日) |
|
|
本日の練習は、エキストラの方々にお越しいただき、初めてホルンが4本そろってのシューマン・ラインとホルン・コンチェルトの練習でした。前回までは、2名のホルン団員が交互に練習に参加したため、互いに1名でこの大曲の練習をしていたので、大変頼もしい限りでした。前回6月の定期演奏会は、別のオーケストラの本番と重なっていたため、私は参加できず、相方とは1年近くお会いできていません(泣)。
シューマンは、ホルンを「オーケストラの魂」と言い残しているそうですが、ラインは4つある交響曲の中でも、ホルンの演奏が特に難しいです。具体的には、ずっと吹き続けてきて一番つらいところでハイトーンや難しいハーモニーが出てきます。リズムがうまくはまらないと曲全体の響きが重くなります。たくさんの楽器が重層的に旋律を奏でているので、旋律を浮かび上がらせるのが大変です。パート内のアンサンブルもままならず、他のパートを十分に留意して演奏することができず、課題が浮かび上がりました。まだ2ヶ月ありますので、皆さんで頑張りたいと思います。(るんほW.T)
追伸:ホルン・コンチェルトの練習の時、2楽章はTacetのファゴットに2番オーボエを吹いてもらいましたが、誰にも気づいてもらえなかったです。(涙)(oboeiko)
|
|
|
|
| 2014年9月14日(日) |
|
|
今日は、次の演奏会に初めてお招きする指揮者加門さんとの初練習である。今まで、一応自分たちでそれなりの準備をしてきたつもりだったが、やはり本番の指揮者に振ってもらうと全く違う世界が見えてくるから不思議だ。
まず、シューマンの第3楽章。これは歌の楽章である。楽譜通りに正確に弾くことも大事だが、ときには少し崩すことによってシューマンらしい歌の雰囲気が出てくることを教えていただく。旋律のアウフタクトの16分音符はちょっと酔っぱらって歩く感じで、と呑兵衛には実にわかりやすいアドバイス。続く第4楽章は、かなり遅めのテンポで荘重な雰囲気を求められる。そしてフィナーレは、生き生きとした躍動感がポイント。しばしばシューマンの曲に出てくる「ターンタタッタ」というリズムがその雰囲気をよくあらわしているという説明に納得。
練習後半は、ウェーバーの歌劇「オイリュアンテ」序曲。はつらつとした速めのテンポでスタート、中間部は幽霊が出るような不気味さ、その後のフーガは精緻なアンサンブルがポイントだ。細かい楽譜のミスも修正していただき、この日の練習だけで全体に大きく前進できたと思う。次回以降の練習が楽しみだ。(Vn.T.N)
|
|
|
|
| 2014年8月31日(日) |
|
|
8月31日。小学生なら夏休み最後の日です。夏休みしてはやけに涼しく、音楽には最適の日ですが、明日から9月だと思うと、それだけで胸が締め付けられるように悲しくなります。小学生でもないのに、なぜでしょう?
今日はメンバーだけで最後の練習日。料理の鉄人・ムッシュMが、菜箸に代わってタクトを持ち、コンダクターというよりはマエストロの風格・・・で、練習が始まりました。
ウェーバーの歌劇「オイリュアンテ」序曲の後、シューマンの交響曲第3番「ライン」の練習に入りました。
団員から「お~」と声が上がったのは、5楽章の78小節目。弦だけでなく、フルート、クラリネット、ファゴットもですが、ファーストとセカンドが半拍ずつずれて演奏することになります。CDで聞くと、この小節になると、皮膚がざわっとする、何とも落ち着かない感じです。
だからこそ、ちょっと気を許すと、合ってしまう音・・・。合わせなくてはならないときには合わず、合わせてはならないときには合ってしまう・・・不思議ですね。
5楽章は、ここだけでなく、様々なところに、落とし穴のように難しい箇所が隠れています。小学生なら夏休み最後の日。はちまきをして最後の宿題をやっているような気分になったひと時でした。(Cl:N.Y)
|
|
|
|
| 2014年7月27日(日) |
|
|
今日は、朝から30度を超える猛暑で、一日中クーラーの下で「ぼぉーぅ」としていたいところでしたが、朝から武蔵野室内アンサンブルの重要なイベントである「弓合わせ」があるため、意を決して炎天下に出かけました。
武蔵野室内アンサンブルでは、最近、「本番直前に弓が変わるのは困る」「早く弓を決めないと練習できない」等の「弓合わせ」に対する不満が出ていました。そんな意見を払拭すべく、私は、自分のパートについて、弓のパターンを想定した上で基本的な弓を付け、準備万端で臨みました。
今日ははシューマンのシンフォニ―第3番の「弓合わせ」を行いました。曲を聴いたことがある方は想像できると思うのですが、非常に弾き難いリズムなのです。楽器同士も複雑に絡み合って、「弓合わせ」は困難で、予想以上の時間がかかりました。しかしアンサンブルリーダの提案を取り入れ、よりメリハリのあるものに仕上がったと思います。
多少前後はしていますが、概ね、以下の手順で「弓合わせ」を行いました。まず、アンサンブルリーダの提案を元に、主題となるメロディーや良く出てくる音形の弾き方を合わせました。次に、クレッシェンドをアップ、ディクレッシェンドをダウン、スフォルツァンドやアクセントをダウンにする等とアーティキュレーションに合わせ、且つ各パート毎に楽器の特性に合わせて弾き易い弓としました。そして、その過程の中で、音の弾き始めを合わせて行きました。時には、スラーやタイを途中で切ったり、弓をアップアップやダウンダウンと連続させたりするところもあります。今後若干の調整は出ると思いますが、良くできているのではないかと思います。
最難関のシューマンの弓が決まれば一安心です。弓が同じになると他の楽器と息が合い、はるかに弾き易くなります。アンサンブル効果も見違えるように良くなりました。
9月からは新しい指揮者での練習が始まります。指揮者の意向で弓が変わってしまうこともありますが、今回は団員の不満が出ないようにしっかりやっていきたいと思っています。乞うご期待。
補足)弦楽器は、弓を引いたり押したりして、弦を震わせて音を出すのですが、弓を引くのを「ダウン」、弓を押し上げるのを「アップ」といい、弦楽器全体でこのダウン・アップを合わせることを「弓合わせ」と言います。決めた弓は楽譜に記号で記載します。指揮者やコンサートマスターが弓のアップ、ダウンを決めてしまうオーケストラもありますが、武蔵野室内アンサンブルは、アンサンブルリーダが中心となって、弦楽器の各パートのトップが集まって決めるのが恒例になっています。何故「弓合わせ」が必要かというと、演奏会での見た目もありますが、弓が違うと音楽表現が異なり、違ったニュアンスの音楽になってしまうのです。また、弓の動かし方次第で弾きやすかったり、難しかったりもします。 (Bass Y.K.)
|
|
|
|
| 2014年7月13日(日) |
| シューマン |
|
2014年度後半戦に向けて、そろそろ何かアップしないと…と思いつつ、2回の練習を何となく過ごしてしまった。そろそろ始動しないと・・・!!と焦るホームページ係である。とりあえず書く。
今回のメイン曲は、シューマンの交響曲第3番「ライン」。シューマンは、学校の音楽室にも肖像画(髪型がボブカット風の油彩画)がかけられているぐらい知名度の高い作曲家。が、私のウン十年のオーケストラ経験が偏っているのか、シューマンの曲をオーケストラで弾いたことが・・・実は無い。無いのだ。ベテラン・チェロのUさんも、「ぼく、シューマンやったこと無いんだよね。難しい?」と言っていた。ヴァイオリンのNさんが答えて曰く、「シューマン、良い曲だよ!! 僕はシューマンが大好きなんだ。」・・・・それって、難しいかどうかの答えになってない(苦笑)。簡単じゃないってこと? Nさんは、初めてオーケストラで弾いた曲がシューマンならば、初めて1st
Vnのトップ(つまりコンサートマスター)を務めた曲もシューマンなのだそうだ。思い入れの深さが伺える。
ロベルト・シューマン、1810年ドイツのツヴィッカウに生まれ、1856年ドイツのエンデニッヒで死去。ロマン派の作曲家で音楽評論家でもある。ピアノ曲で有名なものが多い。そう、「トロイメライ」なら私も弾いた。「流浪の民」も歌ったことがある。妻は有名なピアニストでもあった妻のクララ・シューマン。年の近い親友はフェリックス・メンデルスゾーン。親しい後輩(?)にはヨハネス・ブラームス。晩年、精神を病んだシューマンなのだが、それを支えるクララへのブラームスの思慕というか叶わぬ恋というか、そのテの話題が楽曲分析とともに話題になったことを思い出した。
そんな切れ切れの記憶をつなぎたくて、図書館で子ども向けのシューマンの伝記を読んだ。もともとピアニストを志していたが、指の障害で作曲家になったのだそうだ。クララとは相思相愛で結婚したが、彼の師匠でもあるクララの父の反対にあい、裁判に勝ってやっと結婚できたそうだ。ロベルトさん、プライベートだけでなく仕事に対しても、一途で情熱的でエキセントリックな方だったのだろう。万事に一生懸命であるがために、突き詰めてやり遂げるタイプのために、「ま、いいか」「何とかなるさ」ができないために、バランスを失い、ロベルトの内面は壊れていく。この曲のタイトルでもあるライン川に、飛び込み自殺未遂もしたそうだ。その壊れる寸前の精神が、緻密な構成で言いたいことがぎゅぎゅっと詰まったフレーズが、完熟トマトの状態で手もとの楽譜にちりばめられているようである。さて、ロベルトさんとお近づきになって、彼の歌や考えや感じ方を自分のものにしなくては。(Cb:なおちゃん)
|
|
|
|
| 2014年6月14日(土) |
| 答え合わせ |
|
6月8日(日)定期演奏会に来ていただいた方々、本当にありがとうございました。一緒に舞台に立ったみなさん、お疲れさまでした。
今日は、珍しく、演奏会後の報告を、練習日記がわりに記します。プロのオーケストラ(T交響楽団)によるシューベルトの“グレイト”を聴きにいったのです。CDでは何度も聴いているこの曲ですが、プロの生の演奏を聴くのは初めて。T交響楽団には私の師匠が所属しており、2~3か月に1度ほど受けているレッスンでも“グレイト”をみてもらっていたのでした。そういう意味で、今夜の演奏会は、“グレイト”の答え合わせをする気分でした。
レッスンでは、指使い(フィンガリングやシフティング)や弓の使い方など、個人の技術的なことをたくさん教えていただいています。譜面をみただけだと頑張れば弾けそうな感じなのに、そこだけさらうと弾けるのに、どうして最初から通すと弾けないんだ??みたいなところも、練習の仕方を教えていただいたりしています。自分が悪戦苦闘しているフレーズを、目の前で弾いてもらって「そーやって弾くんだ!!」とわかることも多いです。一方で、オケ全体でのバランス感やフレーズ感といったもの、4つの楽章全体を通しての配分のようなものは、個人レッスンだけではなかなかわかりません。
今夜は、あらためて客観的に曲を聴き、また師匠が弾く様子をそれこそガン見しての“グレイト”でした。先週は目の前にある音を弾くだけで精一杯だったけれど、今夜やっと、全体としてとらえられたたかも、と思いました。この曲は、そんなに力いっぱい濃密にエネルギーを注ぐ音で弾く曲ではなかったようです。fであってもpであっても、もっとコントロールされた、爽やかな音、余裕のある音で弾く曲だったのです。繰り返しが多くて疲れちゃう、ではなく、繰り返してもっと弾きたい、と思うような音楽だったのですね。何しろシューベルトなのですから。
例えば2小節でppからffまでクレッシェンドするようなフレーズは、楽譜に印刷されているボーイングどおりにやらない方がより効果的であるとか、長いフレーズのどこでボーイングを切るのがオケの響きとして効果的なのかとか、いろいろ試してみればよかったな、と反省する部分もありました。その時の指揮者のテンポによって、またオケ全体の技量にもよって、どう弾くのが効果的なのかは違うので、印刷どおりが正しいわけじゃない、とはわかっていました。が、いろいろ試してみる、という余裕が無いまま、通り過ぎていってしまったところが何か所もあり、勉強不足を感じました。ffやsfzと書いてある音が続いている箇所でも、特に力強く弾かなければならないのはどの音なのか、師匠の弾く様子を見ながら、金管やティンパニの重なり具合を聴きながら、あらためて納得した次第です。
・・・もう一度、“グレイト”を弾く機会があったら、今夜の反省の分ぐらいは前回より上手く弾きたいなぁと思っています。もう一度・・・なんて、あるかなぁ?(Cb:なおちゃん)
|
|
|
|
| 2014年6月1日(日) |
|
|
とっても暑い日でした。6月に入ったばかりなのに、クーラー無しでは練習できません。(昔、某吹奏楽団はクーラー無し、音楽室閉め切った状態で地獄の練習でした。)本番1週間前で、エキストラの方もそろい、まず、リーダーの通したことが無いというご指摘でグレイトの通しが始まりました。全楽章通すとかなり長いので(?)、今までの練習で通したことはありませんでした。でも、力の配分とか楽章の切り替えとか(頭の中での)考えることがたくさんあるので、やっぱり通し練習って必要ではないでしょうか~!? 4楽章では集中力が切れて数えられずに落ちまくり・・・・本番1週間前でそれはないでしょう、すみません・・・・
休憩後、少し細かいところをやって、アンコールの練習に入りました。アンコールの曲は低音ばかりで吹きにくい!! でもとっても有名な曲なので、笛が落ちたら話にならないし・・・・意外と緊張する曲なんです。
それから協奏曲に入りました。この曲、大学入試の曲で、1楽章だけは本当に2年間みっちりイヤっていうほど吹いたのですが、2・3楽章はほとんど吹いたことがなく・・・・今回が初舞台です。しかし、2年間レッスン代を払って、いろんな講習会まで受けて、これほどお金のかかった曲はありません(思わず計算してみてビックリ)。でも、演奏会は入試と違うので、楽しんで演奏したいと思ってます。急に決まってタナボタな感じですが、精いっぱい吹かせていただきます。本当に、コンチェルトを吹かせてもらえるところなんてそうそう無いので感謝です!! そして、できたら、10年後ぐらいにイベールのコンチェルトもお願いしま~す!!
それにしても、今回の演奏会に向けて、ホルンやトロンボーンのエキストラの方々が早くから何回も練習に参加してくださって、とても助かっています。本当にいるといないでは違います。本番直前に新しい音が入ってくると、急に変わってドキッとすることもあるので、何とか正団員を増やしたいですね~。(Fl.Y.K)
|
|
|
|
| 2014年5月25日(日) |
|
|
本番までいよいよあと一カ月を切り、そろそろ細かい練習から卒業しなければ・・・なのですが、グレイトは手強いです。全然鳴り方が違う楽器に同じリズムを演奏させたり、掛け合いのバランスや受け渡しが結構大変だったり。パーツが出来上がったら、今度は全体の流れを作り上げるのが一苦労。
武蔵野は、小編成を目指している割に、足りていないパートが結構あるので、エキストラさんのヘルプが不可欠なのですが、今回はトロンボーンも入る大きな編成。嬉しいのは、エキストラさんでも、気がついた点があったらどんどん意見を出してくださる点で(それに甘えてしまって、たまに申し訳ないときもあるのですが(笑))、アンサンブルのしやすさのために、管楽器の配置も試行錯誤しました。みんなで意見を出し合って、どこかに良い妥協点(?)を見つけていけるといいですね。
そして、今回のもう一つの楽しみは、中国から帰国されたアンサンブルリーダーNさんとの久しぶりの共演。Nさん留守中に、リーダーを務めていただいたYさんが2nd Vnトップで、なんとも豪華な顔ぶれ。本番に少しでも余裕を持って楽しめるよう、残された時間の練習を頑張りましょう。(Va. K.J)
|
|
|
|
| 2014年5月11日(日) |
| パートリーダー勉強会とシューベルトとびっくり箱 |
|
本日は母の日でした。あちこちのお店で、母の日フラワーが並んでいるのを発見したのと、「サザエさん」でやっていたから!という理由でうちの末娘(小1)が母の日のプレゼントをくれました。お手製の「びっくり箱」です。
武蔵野の練習は午後からなのですが、本日は午前中に「弦パートリーダー勉強会」をやりました。本番までそうたくさん時間は残されていない時期にさしかかり、ここまでの練習の中でわかってきた各弦パートのそれぞれの都合を擦り合わせるにちょうど良い時期、ということで。オブザーバーとしてFgのIさんにも参加して戴きました。Iさんありがとうございます。
コンマスのNさんを中心に、シューベルト全楽章をさらいました。全体の速さも具体的な数値(♪=n)の提示があり、びっくりしながら始まりました。まずはその速さで弾けるまでになっておくのは当然なのですが、私事・・・速いぱっセージが追いつきません!特に最終楽章!! これはゆっくりテンポで正確に音取りを練習して、確実に運指もボウイングもできていないと。それ以前の状態でただ速弾きすると・・・きっとぐちゃぐちゃの塊になるのでしょう。シューベルトの「びっくり箱」です。
そしてダイナミックスの確認。楽譜に所狭しと並ぶ強弱記号の表現を確認しました。こっれを揃えるだけで、だいぶ曲の完成度が上がります。
休憩無しでしたが、あっという間に時間が過ぎて午後の全体練習へ・・・・
ここのところ、管楽器の皆さまの人数が増えて、後ろでがっちり構えてくださっているので、前衛の我々弦パートとしては全体の厚みを感じております。いつもの武蔵野の少人数アンサンブルとまた違って良いですね~(*^^*) 今日は3楽章→4楽章を重点的に。掛け合いになっている所の主旋律はどっち? 合いの手になっている所との違い。
本番まであと少し。パートリーダーとは名ばかりの私としましては、とにかくしっかり練習して、本番はウキウキ楽しみながら演奏したいと思います。
母の日の「びっくり箱」は、全て画用紙で出来た、開けるとびよ~ん!!と交差に折られた蛇腹みたいのが飛び出てくるやつでした。しかし何故か蛇腹の先が箱の蓋にセロテープで留めてあるのでブラブラしません。本人いわく、先がブラブラしなくてこの方が良いのだと。確かに、行き先がブレずに一方向に定まっているのでした。なるほど・・・・・。(Vc:Y子)
|
|
|
|
| 2014年3月30日(日) |
| 2014年4月13日(日) |
|
ホームページ担当(な)です。3月末から4月にかけて、ホームページ更新が滞っておりました。ご迷惑をおかけしました。練習日記も、原稿を戴きながらもアップが遅れ、失礼しました。以下、ざっくりと復習します。
3月30日は、指揮者の加門さんに練習を見ていただきました。初めて私たちの音を聴いていただいたのですが、シューベルトの1楽章でまず指摘されたのが「音の長さをそろえること」。お互いの音を聴きあっていく中で、どんなフレーズなのか、どのぐらいの音の長さなのかを共有していく、探していくということでした。アクセントだから、スタッカートだから、と自分と楽譜だけの関係で音を出していることがあるので、ちょっとドキッとする指摘でした。練習の後半は、演奏会のあと1曲を決めるために、いくつかの曲を持ち寄って音を出してみて決める、という選曲大会でした。候補に挙がった曲はいくつかあったものの、考えていたよりも難しかったり、すでに決まっている他の曲との関係でパッとしなかったり・・・・。選曲大会のあとに短時間の話し合いを持ち、有力な候補となったのがシュターミッツのフルート協奏曲。ソロは、もちろん河野洋子さんで。河野さん、リーダーのNさん、指揮者の野崎さんに打診をして決定する、ということでこの日は終了となりました。
4月13日、さっそくシュターミッツのフルート協奏曲の楽譜が配布されました。野崎さんの指揮でシューベルトのⅢ、Ⅳ楽章を練習してから、シュターミッツの初合わせ。短いながらも、明るくすっきりした印象の曲です。曲の概要がまだ掴みきれていないのですが、軽快なフルートをしっかり支え、引き立てられるようなオケの音を出していきたいです。また、前半に練習したシューベルトは、管楽器にお手伝いの方々も増えて音に厚みが出てきました。Ⅲ楽章のTrio、欧州の田舎の歌のような素朴さがあって個人的に好きなのですが、管楽器にメロディが次々にリレーされていく様子が聴こえ、弾いていて楽しかったです。聴き惚れすぎて、自分の音が雑にならないようにしなければ。(Cb:な)
|
|
|
|
| 2014年3月23日(日) |
|
|
こんにちは。武蔵野では、いよいよ指揮者の野崎さんを迎え、本格的に演奏会に向けた練習が始まっています。今日の練習は、モーツアルトとシューベルトをともにまんべんなく取り上げました。シューベルトは、譜面に記された記号の解釈が難しい作曲家で、練習の初期段階は、最新の校訂版などを参考に、演奏箇所ごとにどのように演奏すればよいかを擦り合わせる作業となります。今日もいくつかの箇所で、そのような擦り合わせをしながら曲作りをしていきました。だんだんと見通しは立ってきていますが、この長大な曲が開いてです。根気よく練習していかなければと感じました。
ところで、個人的な楽器生活では大きな変化がありました。新しい楽器(とマウスピース)を購入したのです! 増税前の駆け込み需要!というわけではなく、前々からそろそろ新しい楽器が欲しいと思っていたところで、大学時代の後輩が、最近同モデルの楽器を購入しており、触発されて購入した次第です。憧れのベルリン・フィル、ホルンセクションの使用楽器と同モデル!これさえあればなんでも吹ける(笑)!なんてこともなく、以前の楽器との吹奏感やイントネーションの違いに戸惑っています。それでも、それぞれのダイナミクスでの音のまとまりや音色は格段によく、今日が新しい楽器での初のオケ練習でしたが、手応えはまずまず。これからまた楽器生活が楽しみです!(Hr:K.S)
|
|
|
|
| 2014年3月9日(日) |
| アンサンブル大会と、野崎さん初練習 |
|
3年8カ月の中国単身赴任を終えて、1月末に帰国しました。
2月23日は団内のアンサンブル大会ということで、久しぶりになつかしい武蔵野の仲間たちとアンサンブルを楽しむことができました。場所は、昭島駅前のフローラル・カルチャークラブという小さなスタジオでしたが、いつも通りの和やかな雰囲気の中で各グループが練習の成果を披露しました。私は、ミヒャエル・ハイドンの「ヴィオラ・チェロ・コントラバスのためのディヴェルティメント」にヴィオラで出演、ハ音記号の楽譜に悪戦苦闘しながらも楽しく弾かせてもらいました。ヴィオラにはヴァイオリンにはない面白さがあって大好きです。最後の全員合奏では、ハイドンの交響曲第38番の第2楽章と、フルートのKさんの弟さんがオーケストラ用にアレンジした「蛍の光」を演奏。久しぶりに武蔵野サウンドを思い出しながら、ヴァイオリンを弾かせてもらいました。終了後の打ち上げも、大いに盛り上がりました。
3月9日は、6月のコンサートの本番指揮者、野崎さんの初練習でした。曲は、モーツァルトの「魔笛」序曲と、シューベルトの交響曲「グレイト」。どちらもヴァイオリンにとってはかなりの難曲です。何とか通すことはできましたが、これから細かくさらわなければ、という実感をみんなが持ったことと思います。まだ時間は十分あるので、頑張りましょう。
というわけで、武蔵野室内アンサンブルでの音楽活動を再開しましたが、この室内オーケストラがさらに成長できるように、一生懸命やっていきたいと思います。不在中にリーダーを務めていただいたYさんには、ただただ感謝です。ありがとうございました!(Vn:N.T)
|
|
|
|
| 2014年2月23日(日) |
| 第6回 団内アンサンブル大会!!! |
|
大雪の影響で、練習が1回休み。その結果、久しぶりに集まったのがアンサンブル大会の当日となりました。ですが、第6回を数えたアンサンブル大会、係のY子さん中心に準備が進み、グループごとの打ち合わせや練習も着々と行われていたようです。
今回は9グループのエントリーがありました。プログラムの最後が弦楽合奏1曲+全体合奏1曲というところまで決まっていて、前半9曲の曲順は、なんと当日のくじ引きで決めることに。最初だとドキドキする人あり、さっさと終わらせて飲みたい人あり、の順番決めです。内輪のアンサンブルで、お互いに出演者と観客を交互にこなすので、お茶菓子&飲み物つき。もちろんワインもあります。
出演するのは、常連のFl三重奏や木管五重奏に加え、Vaの代わりにCbの入った弦楽四重奏などちょっと変わった編成で選曲したグループがありました。また、いぶし銀のおじさま達のアラ還トリオや、武蔵野の切り札(?)Eちゃんによる親子共演のVnコンチェルト、ドリアン好きがきっかけでグループを組んだマリンバ四重奏、PfのFさんを加えたK音大トリオなど、ユニークなも組み合わせがありました。
海外駐在で団を留守にしていたVnのNさんが、このアンサンブル大会から復活されました。Nさんは、第1回アンサンブル大会の仕掛け人でもあります。また、武蔵野がピンチの時には、利根川の向こうから通ってきて一緒に演奏をしてくれるFlのYさんとも一緒にアンサンブルを楽しむことができました。さらに、飲み屋で団長にスカウトされたというPfのFさんは、このアンサンブルを機に、私たちと楽しい仲間づきあいができそうです.。
旧知の仲間との再会も、新しい仲間との出会いも、どちらも今後の武蔵野の大事な財産です。そんな思いを深くしたアンサンブル大会でした。(な)
|
|
|
|
| 2014年1月26日(日) |
| 車座になって、合わせる |
|
今日は、練習のやり方を詳しく報告します。1stVn=1、2ndVn=2、Vc=1、Cb=2、Fl=1、Cl=1、Fg=1、Tp=1。人数も少ないし、「まだまだ弾けてない(吹けてない)ところもたくさんあるから、今日はお互いの顔が見えるように丸く座って練習しましょう」と、VnのYさんからの提案で、車座になって合わせ練習を始めた。
 まずは「魔笛」序曲。Allegroでヴァイオリンから出てくるテーマは、4拍目のタラララをダウンボウпで弾き、次の小節の頭はアップ・アップV・V、が弾きやすい。今のところ、それで統一して練習しましょう。また、後半に出てくる、四分音符のコード進行の部分、低弦のパート譜にはダウンボウпが印刷されているけれど、中高弦にはボウイングの指示がない。「じゃあ、一応ダウンボウпで揃えるけれど、力いっぱい弾くというよりは、長めに丁寧に弾く、って感じで」。 まずは「魔笛」序曲。Allegroでヴァイオリンから出てくるテーマは、4拍目のタラララをダウンボウпで弾き、次の小節の頭はアップ・アップV・V、が弾きやすい。今のところ、それで統一して練習しましょう。また、後半に出てくる、四分音符のコード進行の部分、低弦のパート譜にはダウンボウпが印刷されているけれど、中高弦にはボウイングの指示がない。「じゃあ、一応ダウンボウпで揃えるけれど、力いっぱい弾くというよりは、長めに丁寧に弾く、って感じで」。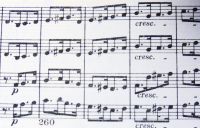
次は「グレイト」。4楽章から。譜例の部分、ゆっくりだったらппV Vで弾くけれど、かなり速いと、音が滑ってしまってリズムが出てこない。VпVпという逆弓ではどうだろう?低弦には見慣れないボウイングだが、いろいろやってみた結果は悪くない。では、ппV VとVпVп、どっちに決まってもよいように練習しておく、ということで。
弦楽器は、このようなボウイング合わせが初期の練習になる。楽譜の指示、自分たちの都合(力量?)、指揮者の解釈やテンポ設定によって決まってくるのだ。管楽器は、「スコアを手元に置きましょう」とのアドバイスがあった。基本的に弾きっぱなしの弦楽器に比べ、休みの小節を数えることが多い管楽器は、自分が誰と“絡む”のかが重要となる。どのフレーズの後に自分が吹くのか、どのフレーズと掛け合いになるのか、伴奏なのか目立って良いのか、etc。家でCDを何となく聴くときも、スコアを見ながら聴くと“絡み”がわかる。構造を理解して吹くことができる、というわけだ。ちなみに、今回の2曲のスコア、国内版が出ており比較的入手しやすい。
少人数でも充実した練習、このあとはやよい会館に場所を移し、新年会となる。私は所要で参加できなかったが、きっと皆さん、美味しいお酒を沢山召しあがったのでは??(なおちゃん)
|
|
|
|
| 2014年1月12日(日) |
| 2014年初練習 |
|
新年明けましておめでとうございます。今年も、武蔵野室内アンサンブルをどうぞご贔屓に、よろしくお願いします。
今日は、練習の前に“総会”を開きました。12月で前年を区切り、1月から新しく新年スタートです。Vnまさひこさん議長のもと、団長に整えていただいたレジュメをもとに、議事が進められていきます。2013年の活動報告、会計報告があり、会則について確認をしました。2014年の活動計画は、2月23日のアンサンブル大会、5月の秋川でのBBQ大会、第31回定期演奏会(6月8日:秋川キララホールにて)、第32回定期演奏会(12月14日:府中の森芸術劇場ウィーンホールにて)、というところまで決まっています。2014年の予算案も拍手で承認されました。
役員選出。そうはいっても総勢25名そこそこの小さな団体ですので、できる方ができる事をやっていくことで運営を回している現状があり、ほぼ留任で決まりました。団長きぬこさん、アンサンブルリーダーは空席です。弦代表はまさひこさんとゆきおさん。管打代表はよしくにさんとたけおさん。会計はまりさん、庶務はゆうこさん、ライブラリアンはようこさん、広報はなおこ。空席のアンサンブルリーダーについては、今月末で海外駐在を終えて復団される予定のとしあきさんを待つことに。
そのほか、第32回の指揮者について、出欠を把握するためのソフト導入について、来月のアンサンブル大会出演者募集について、などの話題がでました。メンバーが顔を合わせて、意見交換ができる貴重な機会となりました。
総会のあと、Mozartの序曲「魔笛」の譜読み・初合わせ。軽快な楽しい序曲、とっつきやすいのですが、クリアな冷静さも必要とされる曲です。残った時間でSchubertの「グレイト」もゆっくり目のテンポで譜読みを。「グレイト」はとにかく長大で長いので、体力や集中力のペース配分に工夫が必要なようです。再現部のメロディや、ダ・カーポして戻った最初のメロディを、いかに新鮮に生き生きと表現できるか。いや、表現だけが上手にできる私たちではないので、いかに新鮮に自分たちが感じ取れるか、なのでしょうl。新鮮な気持ちで、目の前のフレーズに向かい合うことを心がけていきたいです。(広報係なおこ)
|
|
|
|
| 2013年12月8日(日) |
| 久しぶりの練習日記です。 |
|
今日は定演後の休み明け、次回の定演シューベルトのグレイト初練習でした。指揮者は我らが団員ヒゲじいことFgのstone riverさん。
初見の方が多かったにもかかわらず、超有名な曲なので、という理由かわかりませんが、いつもの「とにかく1回目だから全体をつかむためにゆっくりねー」はありませんでした。しかし、それなりに良いテンポのおかげでダラダラせず、心地よい初合わせになったのではないかと思います。さすがstone riverさん。(^-^)/
シューベルトらしいメロディラインや付点のキレやダイナミックス・・・・。少し重点的にもさらいました。普段あまり意識できていない基礎的な部分や、チューニングの基本、それからアインザッツのこと・・・・。
当団には、素晴らしい指揮者の先生がいらっしゃるのですが、本日のように先生がお休みの時には、団員の中で練習を引率できるメンバーがいるのは大変ありがたいことです。コンミスのYさん(プロ奏者)はじめ、指導者でもあるVcのUさん、FlのKさん、TimpのMさん(別名外国語講師!!)、そして本日のstone riverさん・・・・。他にもプロアマ級のメンバーがそこかしこにいて、少人数ではありますが、なんと質の高いアマオケだこと!!(自画自賛(^^)) 有難くその恩恵を受け、自分を棚に上げて、気持ちよーく混じっている私です(*^^*)。
音楽に限らず、いつもの引率者に加えて別の引率者がいるということは、また違った目線や刺激が生まれて、とても良いことだと思います。新しい意識を持つことで、それまでピンとこなかったことが再認識できたり、もします。
次の練習は来年です。
皆様、良いお年をお迎えください!! Vc U子
|
|
|
|
| 2013年10月13日(日) |
|
|
昨日までの夏日最遅記録更新も一段落して、気候も秋らしく爽やかに。今日はエキストラの方々も加わって、気候・演奏ともに「あと1カ月で本番、がんばろー」的な気分でした。
今日の練習、特にヘンデルは、音のニュアンス(長さ、切り具合、弾ませ具合、強弱、硬軟軽重etc.)をパートごとに違わないように揃えていくものでした。音符ひとつの発音も、その音符の役割や流れの中で、できるだけ多種類の発音の仕方ができる、それも指揮者の指示やアンサンブルの中で直に変えられるように磨いておくことが必要だなあと思いました。(自戒中心)
あと、ホルスト「ふたつの無言歌」の楽譜が揃った(なんと武蔵野蔵書として!!)ので、音出しをしました。同じホルストのもう1曲「セント・ポール組曲」と通じるところもあるし、新しいホルストの一面もあって、もう少し慣れたら楽しく演奏できそうですね。
練習中笑いあり:
その1)KB/Kさん「この場所は、みなさんも“p”なんですか?」
影の声「はい、“p”です。っつーか、音デカイってことかよー?」
その2)楽譜を見つめて顔が固まっているVc/Iさんに、
先生「なんか難しい顔してるけど大丈夫? わからない事あったら聞いてね。」
小学校の時、算数の先生が首を傾けている生徒に優しく語りかけているようでした~
(追伸)今回の練習日記に、最近小生の楽器で起こった「Fgのお尻」事件について書くようにとのオーダーがあったのですが、写真入りの長文になりそうだったので勝手に省略しました。興味ある奇特な方はFacebookを覗いてみてください。以上/Fg-Y..I.
|
|
|
|
| 2013年9月29日(日) |
|
|
ホルンのKです。入団して初めて練習日記を書かせていただきます。
今日の練習では、今回の演奏会のホルンパート4人が初めて揃い、ヘンデル「水上の音楽」を集中して練習しました。今回ホルンパートは、私と、今回から新たに入団されたTさん、それからエキストラの学生さんお二人で臨みます。お互いにほぼ初めましてという感じで挨拶もそこそこに合奏が始まります。久々にバリバリの学生さんと一緒というのもあり、とても新鮮で楽しかったです。(私が不安定でごめんなさい。。。)
ところで、今回の演奏会で取り上げる「水上の音楽は、アイルランドの指揮者・作曲家のハミルトン・ハーティによる編曲版で、少し変わっています。ヘンデルのオリジナルと比べると、現代オーケストラ向けに楽器の編成が増えていたり、いろいろと音が追加されたりしていて、かなりゴージャスな響きになるように書かれており、まるで古典的なヘンデルの音楽のモチーフを借りて映画音楽にでも仕立て直したような感じです。今でこそオリジナルに忠実な演奏が主流ですが、以前には近代的なオーケストラの機能性に合わせてこういった改変が普通になされる時代もあったようで、マーラーのベートーヴェンの改編などは際立ったところです。
今のところ、武蔵野の曲作りは、オーケストラが小さいこともあり、あくまで中庸です。私たちのイメージも、基調はヘンデルの雅でキラキラした感じ(でしょうかね?)でありつつ、時折現れる重厚な響きにはっとしたりして、これからどんなふうに私たちのイメージが固まっていって曲が仕上がっていくのか楽しみです。ちなみにこの曲、ホルンがかなり重要な役割を担っています。頑張ります。。。。.(cornokenken)
|
|
|
|
| 2013年9月22日(日) |
|
|
22日の練習は、コンミスの初参加により、演奏会へ向かうという気持ちが高まった練習だったような気がします。弦楽器にはボーイングを決めるという大事な作業があり、この日もコンミスのYさんは、表現したい音に近づくためによりよいボーイングを試行錯誤。加えて、弾き方、技術的なことまで指導してくれるのですから有難い。聞いていると実際に出てくる音が変わってくるからさすが! また、指揮者のNさんも弦楽器奏者なので、特に若い弦のメンバーには、期待を込めてか時に熱くご指導くださる。それが功を奏して、若い子たちが上達していくのが目に見える。若者には道の能力があるらしくうらやましい。武蔵野の将来を担う若手がどんどん育ってほしいと願っているので、とても嬉しい。
この日の練習前半は、弦中心の練習となりましたが、指揮者が弦に要求していることは、そのまま管にも通じることなので、ぼーっとしていられません。「管の人もわかりましたか?」(Fl.KK)
|
|
|
|
| 2013年9月8日(日) |
| 2020年オリンピック |
|
「今朝、オリンピック決まった時のニュース見た? ”TOKYO”って言ったとたん、言ってすぐ、”うわぁぁ~っ!!!”って歓声があがったでしょ。」休み時間の話ではありません。合奏中の話です。「あの時みたいに、”TOKYO”って聞いてすぐ後に、”うわぁぁ~っ!!!”って言った人たちは、すぐにでも立ち上がれるように、すぐに叫びだせるように、どっかり座ってなんかいないで、今か今かと跳びあがって叫ぶ準備をして座っていないといけないんだよ。そんな感じ。そんな感じで、この部分を弾いてください。」・・・・ヘンデルの「水上の音楽」の一場面でした。
王侯貴族の野外での宴のBGM。私のイメージはそんなものでした。「仮面の男」「三銃士」「ベルばら」あたりの(ヘンデルのそれとは数十年の誤差がありますが^^;)近世欧州が舞台の映画のきらびやかな一場面をイメージしていたものの、それは映像イメージでしかなく、感覚や感情のイメージではありません。感覚や感情を思い出し、そのイメージを音にする・・・・音楽を通して表現するって、そういうことだったんですね。改めて気付かされました。近世欧州と2020年の東京オリンピックとは、300年の隔たりがあるけれど、湧き立つ感情という点では同じなのでしょう。
こういうアドバイスを受けて、反応が速いのはやっぱり若手。技術の多少はあるけれど、持てる力を組み合わせたり工夫したりして新しい音が出てくるところが素晴らしい。人生ベテラン組は、知恵と経験は豊かにあるけれど、すでに使い古されたもので何とかしようとしてしまう。知恵と経験に安心して甘んじないで、新しい音がどうやったら出るか、試行錯誤する度胸や冒険も必要だな、と自戒を込めて感じた日でした。(なおちゃん)
|
|
|
|
| 2013年8月25日(日) |
| 武蔵野の老若男女 |
|
前回から、さらに1か月空いての練習でしたが、今回は指揮者の野崎さんによる合奏。この曲はこんなイメージで、とメンバーと指揮者がお互いに擦り合わせをする最初の回です。今回は、演奏会までの練習回数がいつもより少ないので、効率よくペース配分をしながら練習を進めないといけません。細かいところはさておいて、とりあえず全貌をつかみ、大丈夫そうなところとヤバそうなところが明らかになったかしら。誰かが言っていましたが、アマチュアはプロセス(過程)が大事。プロは結果が良ければ過程がどうであってもよいのだそうですが、アマチュアは、たとえ本番に100%の結果が出なかったとしても、そこに至るまでの練習が十分実りあるものであれば、“成功”なのだそうです。良い練習を今後も重ねていきたいと思います。
ところで、武蔵野室内アンサンブルは、老若男女、いろいろなメンバーがいます。いちばん幅広い顔ぶれなのがヴァイオリンパート。若者代表(?)の現役高校生のEちゃん、現役大学生のSくんは、ふたりとも中学生の頃からアンサンブルに参加していました。最初のうちは、合奏で隣の人と2人でひとつの譜面を見るのもドキドキ・・・といった様子でしたが、ふたりとも今ではすっかり頼りになる若者に成長しました。今日は、EちゃんがコンミスYさんの代わりに1stヴァイオリンのトップ。指揮者からの細かい指示も受け止めて弾く様子に、後ろからおじさんおばさん方の熱い視線が注がれていましたよ。Eちゃん、頑張ったね。そしてすごく立派になったね。
一方で、人生の大先輩であるSさんは、淡々と2ndヴァイオリンで弾いていらっしゃいます。年をとっても、ずっと楽器を弾き続け、仲間と音楽を楽しみ続けている姿は、私たちの励みです。休憩時間にトイレに行ったきり戻って来なかったので、みんなで心配して確認に行ったことがありましたっけ。Sさんがそこで弾いている、ということが、私たちの安心と心の支えになっています。今後ともどうぞよろしく。
そんな当団のヴァイオリンですが、慢性人手不足につきメンバー募集中です。今日は、入団希望で見学にいらした方がありました。私たちと一緒に、ぜひ、良い練習を、楽しいアンサンブルを重ねていきましょう。(なおちゃん)
|
|
|
|
| 2013年7月28日(日) |
| 初合わせ |
|
1か月以上空いての練習日記更新となりました。1か月+αぶり練習だったわけです。みなさま、たいそうご無沙汰しました。
次回にむけての初合わせ。“初見大会”と言ってしまうと「初見だもん、弾けなくても(吹けなくても)しょうがないじゃん~」という笑ってごまかすニュアンスも含んでしまうので、あえて“初合わせ”と言いたい。初見でだってちゃんと弾けたり(吹けたり)しないと、ホントはいけない。かくいう私も、ハイドンはCDを何度か聴いてきたつもり。耳から全貌を掴んでおくだけで、だいぶ違う(はず)、と自分では思っている。ヘンデルは、合奏で音を鳴らしながら、十代の頃にこの曲を弾いたことを思い出した。こんなフレーズだったっけ、と改めて楽譜を読むと、当時気付かなかったことを今気付いたりする。ホルストも、若い頃やったことがある、と思い出しつつ、記憶は結構いい加減なので、小節数はちゃんと数えなくては。そうそう、各楽譜には小節番号が無いので、これを読んでいるメンバーのみなさん、楽譜をもらったらそれぞれで小節番号を書いておきましょう!!
自分のパートに限った話で恐縮だが、今日やった3曲は「どーやって誤魔化すべ・・・」という曲ではない。むしろ、とっつき易く弾き易く、すぐに出来た“気分”になってしまうような印象。それだけに、他のパートとの絡みや曲全体の構成をわかったうえで合奏すると、もっと面白い音楽になるのかも。一回一回の合奏を大事に、曲を作っていかなくては。
早めに練習を終えたあと、今回のプログラムの残るもう1曲のこと、今後の練習のことなどを、その場で車座になって話し合った。きちんとした○○会議、という形ではなかったからこその、ぶっちゃけた意見や本音が交わせた。お茶もお酒も抜きの方が、中身が充実した話し合いになると思う。
アマチュアでオーケストラをやってる友達が、先日こんなことを言っていた。プロは、結果が大事。でも、アマチュアは過程(プロセス)がもっと大事。プロは、本番の演奏の出来が良いか悪いかが全てで、結果さえ良ければOK、他人に評価されれば次の仕事につながる。でもアマチュアは、そこに至るまでの日々の練習やら人間関係やら、どうしてこの曲をやることになったかとか、気に喰わない奴がいるとか、指揮者にこう言われたとか、そんなひとつひとつを消化していくプロセスが重要なのだ。誤解を恐れずに言えば、他人の評価よりも自己肯定感や自己達成感の方が大事ということだ。今日のような腹を割った話し合いも、次の演奏会に向けての自分たちの達成感につながるんだよなぁ。(Cb なおちゃん)
|
|
|
|
| 2013年6月9日(日) |
|
|
本番1週間前となりました。
練習は、フォーレの「マスクとベルガマスク」からスタート。この曲、今までは短めの時間でポイントのみを修正する練習が中心でしたが、今日はたっぷり2時間かけて細かいニュアンスやフレーズ、テンポ感などを確認しました。確認したことを体にしみ込ませておいて、フォーレにしては(失礼!)うきうきした明るい音楽を、楽しみながら演奏しましょうね。
次の練習は、クラリネット・コンチェルト。これは全曲を通して、流れや合わせどころなどを曲感の中で確認しました。橋爪先生との合わせも3回目となり、しっくりしてきていると感じました。あとはソロに聴き惚れて落ちないようにですね。(<自分へ)。
最後はシューベルトのシンフォニー。今日は練習時間が長かったので、疲れが出てきたせいか、正直テンポの感じ方など多少ずれが出てしまいましたね。1週間美味しいものを食べて体力をつけ、週末は集中力を持って明るく臨みましょう。
今回の3曲は、しいて共通点を挙げるとすると「うた」だと思います。個性は違っても、いずれもメロディラインが美しい曲なので、思い切って歌えば道は開けるかも、と思っております。
最後に、今回も何人かのエキストラの方にご協力いただいていますが、TimpaniのIさんはマリンバ・コンチェルト以来久しぶり。イイ男になってきましたね(あ、前もですが、もっとの意味です)。(Fg Y..I.)
|
|
|
|
| 2013年6月2日(日) |
| いよいよ追い込み |
|
ここ数回の練習で、弦楽器のエキストラの方が加わり、いよいよ本番が迫ってきているのを実感。
やはり弦が揃うと嬉しい。一方で、人数が増えると当然ながら音程や音の出し方を合わせるのがより難しく、細かい部分の再確認を重ねる。この段階になると各自が弾けてくるので、掛け合いや、ハーモニーなどが良く聞こえてきて、なかなか楽しい。前回のソロ合わせ練習後に、ソリストに指摘された“コントラバスに、チェロ・ビオラが巧くのっかれていない(特に音程!)部分有”、というのを意識したり、2ndヴァイオリンと一緒に刻んでいるところをS君とアイコンタクトで合わせる努力(報われているかは??)、弾けてくるとそれに応じてボウイングも変わり、「あーなるほど」と妙に納得したり。毎回のことながら、もっと早くこれができていれば・・・と反省しつつ、“エキストラさん、武蔵野でのアンサンブルの楽しさを感じて、良かったら是非、入団してくださいね!”と願いながら、あと数回で心をひとつに出来るよう、いよいよ追い込みです。
本番後に、また美味しいビールが飲めますように。。。 武蔵野の打ち上げは、本当に楽しいですよ!(Va/K.J)
|
|
|
|
| 2013年5月26日(日) |
| クラリネット・コンチェルト |
|
いよいよ演奏会本番が近付いてまいりました。今日の練習にはエキストラの方々がたくさんご参加くださり、そして、ソリスト橋爪先生にもお越しいただき、初ソロ合わせとなりました。
ここで改めて我が師匠の橋爪恵一先生をご紹介させていただきます。東京藝術大学を卒業され、現在はカメレオン・オーケストラの要として独自のコンサートを開催されています。日本政府の派遣によりアフリカ・ザンビアの大学で音楽指導を行ったり、オペラシアターこんにゃく座オペラ公演カフカ「変身」にてヨーロッパ4カ国ツアーに行かれたり、パントマイム・ヨネヤマママコさんとのコラボレーションを行うなど、幅広く音楽活動をされています。また地元立川では、開発のために切られそうになった3本のプラタナスを救うため、「スズカケ3兄妹救出作戦」というタイトルで木管三重奏のコンサートを開いて保存運動を行い、東北復興のため楽器支援を進めるなど社会派の一面もお持ちです。
今日の初ソロ合わせは、私、本当に楽しませていただきました。まず、みんなの前に立たれた先生のお姿。どっしりと大きく、安定感があり、頼れそうという雰囲気。演奏が始まると、アーティキュレーションが本当に自由。素人はテンポに遅れないようにスラーで吹いてしまいがちですが、先生のクラリネットらしい美しいスタカート、素敵です。ソロの楽譜には、アーティキュレーションの指定がない箇所も多く、ソリストに任されるので、どんな風に演奏されるか聴きどころと言えるでしょう。また、カデンツァがストルツマン風にアレンジされていて、なんだか嬉しくなりました。リチャード・ストルツマンというアメリカ人の有名なクラリネット奏者がいます。モーツァルトやブラームスなど、クラシックの定番だけでなく、ジャズやクロスオーバー音楽へも積極的に取り組んでいる演奏者です。二楽章後半の再現部にもストルツマン風アレンジが入っていて、聴いていてはっとしました。後で先生に今日のオリジナルな演奏の楽譜をいただいてしまって、更に舞い上がりました。
あと数回で本番を迎えますね。何度も代奏させていただきありがとうございました。とても勉強になりました。皆さん、先生との演奏をぜひ楽しんでくださいね。野崎先生、橋爪先生、よろしくお願いします。(Cl.M.N.)
|
|
|
|
| 2013年5月19日(日) |
| 指揮者の野崎さんがお休みということで |
|
指揮者の野崎さんがお休みということで、代わりに諸遊さんが初めて来てくださいました。
代振りの方が来てくださるたびに、その空間の雰囲気が大きく変わることに驚きます。戸惑いあり、発見ありですが、「音楽は、そこに集う人によって創られる」のだと実感する時間でもあります。
諸遊さんは、ひと言でいうなら、「言葉によって巧みに音楽を創り上げる」先生です。たとえば、途切れ途切れになってしまう管楽器の演奏に対して、「これじゃあ、だるまさんがころんだ、ですね。」という言葉。「だるまさんが、ころんだ!」と振り返った瞬間、みんなが一斉に止まる場面を思い浮かべ、笑いが起こりました。また、装飾音符がついている所では、「装飾音符は、ある人がお洒落をして、羽飾りをつけているようなものです。でも、今の演奏では、飾りそのものが南国の鳥になって跳んでいるみたいです。」という比喩。また、あるときは、「ここはA dur(=イ長調)ですから、イカヅチを落とすのではなく、天国感があってもいいんじゃないかな。」という説明。
人に伝える仕事をしている私にとって、自分の思いをいかに伝えうrかということを、深く考えさせられる瞬間でした。
「そんなこと考える暇があったら、もっと練習に身を入れなさい!!!」と自分に言い聞かせているうちに、練習、終わっちゃいました・・・・。(Cl.N.Y)
|
|
|
|
| 2013年5月19日(日) |
| だるまさんが転んだ |
|
本日の練習はシューベルト中心で、残りフォーレをやりました。代振りで諸遊先生にいらしていただきました。とても躍動的で楽しい先生でした。例えの表現がひとつひとつ面白く、笑いのつぼにはまらないように必死でこらえていた団員も少なくなかったかと思います。
言われてみれば確かにその通り、と気づかされることばかりで、とっても勉強になりました。そういえば、子どもの頃、先生に似たようなことを言われたのを思い出しました。曲の始まりから終わりまで自分なりのストーリーを作る、というものです。テンポの変わり目や転調のタイミングで場面転換をしながらそれを演じてゆくのです。そして自分が思って演じた分のせいぜい7~8割が表に出ていれば良いほうで、大概は思ったほど表現できていないのです。だからちょっと大げさなくらいで調度良い。これが個人単位の作業だとすると、アンサンブルって・・・・・。指揮者というストーリーテラーのもと、みんなでひとつのイメージを持って、周りとのバランスを見ながらそれぞれ自分の役を演じる。難しいけど、とっても楽しい!!
こんなことを、趣味としてやらせていただける環境とメンバーにつくづく幸せと感謝を感じています。
因みに、「だるまさんが転んだ」はやっちゃダメです。(Vc.U子)
|
|
|
|
| 2013年5月12日(日) |
| 武蔵野の母 |
|
本日は、分奏で弦楽器の練習をしました。クラリネットコンチェルトのみ。
1楽章、曲の冒頭を華やかに飾る序奏部は、弦楽器部隊にとってはすごく緊張する部分です。この部分によってソロ奏者の吹き始めの気分を左右すると言ってもよいぐらい大事なところ。気持ちよくソロ奏者を導引し、支え、決して出過ぎず、でも主張するところはし、繋ぎ目を繕う、コンチェルトならではの難しくも楽しい練習を、本日はみっちり行いました。
コンミスのYさんご指導のもと、厳しい中にも愛情あふれる特訓をしました。こうした弦分奏は、きっともっと多くの機会があるといいなぁ、なんて感じました。
しかし、このコンミス、今や武蔵野にはなくてはならない存在で、弦楽器部隊の「母」のような存在です。(おこられちゃう!!?)弦奏法はもちろん熟知されているので、運弓やアーティキュレーションの指導は分かりやすい。それに応えられているかは別として。チェロ・コンバスは基本的に移弦の方向が肩に楽器を構えるバイオリン属とは逆になるし、ポジショニングもかなり違うので(コンバスは4度調弦なのでなおさら!)、多少の楽器個体差はあるにせよ、意図していることが伝わると、不思議と同じ方向が見えてくるのです。まるで、母と子のよう。
何度か同じフレーズを弾いてひとつになったとき、「おぉ!! 今アンサンブル!!って感じになったねぇ~!!」と皆感動。自画自賛。うちのパートはこれだと弾きにくいな、とか個々の悩みも聞いてくれて、温かく適切にアドバイスしてくれます。いくら嘆願してもダメなことはダメ。時には厳しく軌道修正もしてくれます。
もうお気付きかと思います。本日は「母の日」です。日頃の感謝をこめて、「Yさん、いつもありがとうございます!!」(Vc.U子)
|
|
|
|
| 2013年4月28日(日) |
|
|
今回は、昨年7月に入団した I が担当させていただきます。私から見た武蔵野の魅力をご紹介したいと思います。ひとことで表現しますと、ズバリ『アットホーム!!』。新しく入団した方、いわゆるトラでいらした方、長く団で活動されている方、仕事などの環境の変化により今現在休団されていて、久しぶりに戻って来られた方、皆が集まって音楽(合奏)をする時にソレを一番感じます(練習後の宴会でも(笑))。音楽造りは、もちろん指揮者の先生を中心に行われますが、指揮者の提案に対し、合奏の中で皆で検証し、カタチを作っていく。私は、長年、絶対的な指導者の下で吹奏楽をやってきましたので、それは凄く新鮮でした。奏者ひとり一人の人生経験も音楽作りに反映しているようで、私は武蔵野の音が大好きです。その中に居られる自分が幸せだと感じることができます。現在、正規団員が少ないパートがあります。もし入団を迷っていて、この日記を読んでくれた方がいましたら、『いつ始めるか』、『今でしょ!!!』。団員全員であなたの入団をお待ちしております。(Trp T.I)
|
|
|
|
| 2013年4月14日(日) |
|
|
今回の練習は、指揮者の野崎さんがお休みされるということもあり、代振りとして藤本さんという方に来ていただきました。この方は、武蔵野室内アンサンブルの過去の演奏会に何度か足を運んでくださっていたのですが、団員の多くにとっては初対面ということもあり、はじめはお互いに手探りの練習になりました.時間が経つにつれてお互いに慣れてきて、有意義な練習ができたと思います。普段の練習と少し異なる環境ということで、普段の練習以上に緊張感があったり、いつもとは少し違う視点からの発見があったりして、とても新鮮な練習となりました。
普段、僕は比較的大規模のオーケストラで演奏をしていますが、そのような環境で弾くのと、武蔵野のような小規模な編成で弾くのでは、同じ合奏でも大きな違いを感じています。演奏者が少なくて、その分全体の音量も小さいアンサンブルでは、音の出し方も曲の作り方なども、いつも以上に気をつけて演奏しなければなりません。大編成での合奏でも、少人数のアンサンブルを拡大したものとして演奏をしていきたいのですが、大人数での環境に慣れてしまうと、お互いの音を聴いてハーモニーを作るという基本的なことを疎かにしてしまいそうになります。アンサンブルの基本を忘れないためにも、少人数での合奏はとても大事なことだと常々感じています。
いろいろな環境で弾くことは大事だと、改めて思う一日でした。(Vn.S)
|
|
|
|
| 2013年3月31日(日) |
|
|
主人の仕事の都合で、昨年末までタイのバンコクに、そしてこの5月からは次の転勤先インドネシアのジャカルタに向かう予定の元団員です。数か月の日本滞在という宙ぶらりんな状況の中でも、「暇なら弾きにおいで!」とみんなが声をかけてくれる。そんな懐の大きい武蔵野室内アンサンブルのメンバーに感謝しています。
バンコクでは、室内楽規模とのものと80人からなるアマチュアオーケストラの二つの団体に参加していました。どちらもベートーヴェン、ドヴォルザーク、チャイコフスキーなどをガンガン弾く十台後半から二十台前半の若い子ばかりで、“質より量”という感じで沢山の曲を楽しく弾かせてもらっていましたが、武蔵野の練習では「フレーズを考えて」「テンポ感が合ってない」との指揮者の声に、久しぶりの緊張感と丁寧に音楽を作っていく楽しさを思い出しました。2月のアンサンブル大会では、チェロ4本のパッサカリアに、弦楽四重奏でモーツァルト&ビートルズ。これはまたいつもの練習と違い、お酒も入り、自由で楽しいミュージックパーティとなりました。
6月の本番に出られないのは残念ですが、もうしばらくみなさんと一緒に練習を楽しませていただきたいと思いますので、よろしくお願いします!!(Vc T.K.)
|
|
|
|
| 2013年3月24日(日) |
|
|
久しぶりに武蔵野室内アンサンブルの練習に参加させていただき、シューベルトの6番、フォーレの「マスクとベルガマスク」を楽しく演奏させていただきました。本当に感謝、感謝です。
大阪に転勤し、ここ1年間は中規模のアマチュアオーケストラで、シンフォニーだけでなく、オペラやオラトリオを楽しんできました。武蔵野室内アンサンブルでは、弦楽器・管楽器ともに各パート1~2名程度の、小ぢんまりした編成で、ひとりひとりの音が音楽を形成するため、いつもより集中して演奏しないといけません。野崎さんの練習は、ひとつひとつのフレーズと和音の展開を大事に丁寧に組み立てていきますので、演奏にはいつもより気を遣いました。
大人数のオケで演奏していると、ついつい力任せに吹いてしまう癖がついていましたが、今日の練習で、音をあわせる、アンサンブルの楽しみを再度思い出しました。練習終了後、久しぶりの緊張感と心地よい疲労感が残りました。やっぱり武蔵野室内アンサンブルは楽しい。
6月の本番には参加できませんが、演奏会が成功裏に終わりますこと、大阪の地から応援しております。(ObのOBのT)
|
|
|
|
| 2013年3月10日(日) |
| 金管楽器側からみる音楽 |
|
今回の日記担当が金管奏者ですので、勝手ながら金管楽器からみたアンサンブルの難しさや課題を記してみます。
金管楽器の出番は、古典の音楽では特に少なく、40小節、長くて120小節のお休みを経て、管が冷え切った状態で決まった音を出さなくてはならなく、それはそれは緊張の伴うことなのです。楽譜上は、単純に同じ音の四分音符が3つだけ並んでいるだけだったりし、ではその音をどう表現するのか、単に同じ音量で正確な長さで音を吹けばよいということではなく、作曲家がなぜそこに音を入れたのか、常に考えながら演奏しないと、生きている音楽ではなくなってしまいます。でも、今の私にはそれが非常に難しく、果てしない道のりであります。でも、周りの音に対して自分の音をどう関わらせるのか考える作業はおもしろく、まだまだできてはいないですが、それがアンサンブルの醍醐味でもあるのかなぁと思っております。
今回の練習で指揮者にご指摘を受けたこと、「弦楽器のスピードに合わせて」。これも頭ではわかっているのですが、実践は難しく、行きのスピードを速くさせると鋭い音になってしまい、古典の音楽に合わなくなってしまいますし、逆にスピードを遅くすると穏やかな音は出るのですが、弦楽器と合わなくなってしまい、難しいのです。(少なくとも、私にとっては、ですが)でも、少しでも近づけられるよう、日々練習していきます!! 必要のある音が出せるよう努力していきます。(Tp. A.I.)
|
|
|
|
| 2013年2月24日(日) |
| シューベルト雑感 |
|
個人的な事情で練習を急遽欠席したのだが、練習日記の割り振りをお願いしそびれてしまった。ドタキャンの申し訳なさ&ホームページ担当者の責任(?)で、「練習に出ていない人の練習日記」を書く。悪しからずご了承ください。お題はシューベルト。
丸眼鏡にもしゃもしゃ頭の肖像画で有名なこの方。最も有名な曲は何だろう?「野バラ」「ます」「菩提樹」あたりがポピュラーだが、個人的には「魔王」も捨てがたい。中学1年の教科書に出ていた「魔王」、何と言っても強烈なインパクトがあった。何しろ、曲中で登場人物が死んでしまうのだ。こんな話を歌にするのか?と驚いたの何のって。でも、のちに、「美しき水車小屋の乙女」とか「冬の旅」とか、もうすぐこの世に別れを告げます、と歌っている名曲たちにも出会うのだけど。
“歌曲の王”であるシューベルトだが、室内楽も捨てがたい。前出の「ます」五重奏は、私の大好きな曲(この秋、演奏する機会に恵まれました!!)。「死と乙女」などの弦楽四重奏にも美しい曲がいくつもある。彼は、父や兄たちと家庭内弦楽四重奏をちょくちょく楽しんでいたという。ああ、武蔵野の団内にもそういう雰囲気はあるなぁ。美しい曲を書いてくれるオカカエ作曲家はいないけれど。
では、もっと大きな編成の器楽曲・・・・・・オーケストラの曲は?というと、やはり有名なのは交響曲ロ短調、通称「未完成」。実らなかった恋ゆえにこの曲も完成させなかった、というのは映画の中だけのお話らしいが、ロマンティックな筋立てにこの曲のメロディがぴったりで、だから映画も名作となった。
今回、私たちの選曲は、シューベルトの交響曲第6番である。「未完成」の後に作られた、通称「グレイト」と呼ばれるハ長調の交響曲に比べ、同じハ長調でも短い方、ということで「小交響曲」と呼ばれることもあるらしいが、いやいや、そんなに小さく短いわけではない。重厚な大論文ではないけれど、長編エッセイのような、ふむふむ、そうか、そうだよね、という曲。“もっとも詩情豊かな音楽家”と言われたシューベルトの美しいメロディが、それぞれの楽章ごとに色合いや雰囲気を変えて生き生きと描かれている。さて、この曲を、あと4ヶ月間で、私たちは自分のものとして弾き、吹き、叩き、表現するわけだ。その出来栄えを、天国のシューベルト氏はどのようにご覧になってくださるだろうか?(Cb:なおちゃん)
|
|
|
|
| 2013年2月10日(日) |
| アンサンブル大会 |
|
今日はやよい会館で団内アンサンブルコンサートが開催された。武蔵野の仲間とも離れ、中国での単身赴任生活を開始してはや2年8カ月が経過したが、ありがたいことに、今年も私の一時帰国日程に合わせて団内コンサートを企画していただいた。
今回も、デュオから室内オーケストラの合奏まで盛りだくさんのプログラムが組まれ、弾く方も聴く方も大いに楽しむことができた。私が弾かせてもらった曲は、ボッケリーニのフルート五重奏曲Op.17-4、メンデルスゾーンの弦楽のためのシンフォニー第1番、そして全員合奏によるモーツァルト交響曲第9番の3曲。短い滞在期間のため、合わせ練習は前日と当日の2回だけという、いつも通りの無謀な企画ではあったが、やはり長年付き合ってきた仲間とのアンサンブルは、みんなすぐになじんで楽しい演奏になった。モーツァルトでは、指揮者の野崎さんが仕事の合間に本番に駆け付けてくれて指揮をしていただいたのは嬉しかった。
終演後に中神駅近くの居酒屋で行われた打ち上げでは、新たに仲間入りされた若い人たちとも楽しくお話をさせていただいた。また、飛び入りで打ち上げにきていただいたヴァイオリンのYOKOさんは、つい先日まで香港のアマチュア・アンサンブルで一緒に弾いていためちゃめちゃ楽しい友達で、最近日本に帰国されたばかり。さっそくみんなとも親しくなり、近々武蔵野に仲間入りする予定。ということで、これからがますます楽しみな武蔵野である。私も今年はなんとか帰任出来ると思うので、それまでにさらに素敵な仲間が増えていることを期待したい。(アンサンブルリーダーT.N:在中国広東省)
|
|
|
|
| 2013年1月27日(日) |
| 1月13日・27日の練習にて |
|
武蔵野室内アンサンブルでは、「定期演奏会では取り上げられることが少ない小編成の曲を演奏して楽しみましょう」ということで、毎年アンサンブル大会を実施しています。二重奏、三重奏、四重奏等々、メンバー自身が自由に選曲して演奏するとっても楽しい演奏会です。その中に1曲、私が推薦したモーツァルトのシンフォニー第9番が決まったのですが、実は大変な問題が起こってしまいました。
ネット上でフリーの楽譜をダウンロードしてメンバーに配ったのですが、その楽譜が間違いだらけだったのです。音がないところに音符があったり、臨時記号の間違いで音の高さが違ったりで、練習中の奥の時間が、楽譜修正確認にとられてしまったのです。とっても優しい指揮者は、「楽譜の間違い探しで勉強になった。面白かった。こういうのをまたやりたい???」と言ってくださいましたが、こちらは冷汗ものでした。
ところで、この曲(交響曲第9番)は、モーツァルトが、初めてイタリヤ巡業に出かける直前の1769年12月(13歳)に作曲されたもので、幼年期終盤の作品と言われています。モーツァルトの幼さを感じる明るく素直な曲で、1~4楽章の全体で10分程度と短いので聴き易い曲です。アンサンブル大会が楽しみです。
(追伸)武蔵野室内アンサンブルメンバーのみなさん、間違いだらけの楽譜を調達したのは私です。ごめんなさい。(CB K.Y.)
|
|
|
|
| 2013年1月13日(日) |
| クラリネット・コンチェルト!! |
|
みなさま、13日の練習お疲れ様でした。2013年の武蔵野初練習はモーツァルトのクラリネット・コンチェルトで始まりましたね。僭越ながら橋爪先生の代奏をさせていただきました。お聴き苦しくてすみません。でも、なんだか今年はたくさんいいことがありそう!?と思えてしまうのは私だけでしょうか。
モーツァルトのクラリネット・コンチェルトは有名ですが改めてご紹介させていただきます。時は1780年代のウィーン。マリア・テレジア女帝の死後、ヨーゼフ2世の時代。マリー・アントワネットのお兄さんですね。フランス革命前夜の華やかなウィーンでは以前から存在していたフルート・オーボエ・ファゴットに加え新しい木管楽器としてクラリネットが登場しました。現在はB管とA管に落ち着いていますが当時はD管、C管、G管など様々な調のクラリネットが混在し、演奏者と製作者の間でも試行錯誤が続いていたようです。そんな時代、通常のクラリネットの最低音Eよりもさらに5度低い音域を持つバセットホルンという楽器をクラリネットの名手アントン・シュタッドラーが好んで演奏していました。モーツァルトは彼の演奏に魅せられて1791年この協奏曲を完成しました。が、実際の演奏は後にシュタッドラー自身が依頼して改良させたバセットホルンと同じ音域をもつバセットクラリネットで演奏されたようです。この楽器は1991年に復元されユーチューブで演奏を聴くこともできます。モーツァルトはこの3オクターブ半の幅広い音域を存分に活かし最低音近くの重厚な低音部と高音部の対比をみごとに描いています。また、協奏曲では独奏楽器が常に旋律をとりオーケストラは伴奏に徹する作品もありますがこのモーツァルトの協奏曲ではソロ・クラリネットと同等にオーケストラが活躍し旋律を担う構成です。だからきっと皆さんにも楽しんでいただけるのではないでしょうか。
第1楽章冒頭部の第1主題は定形どおりオーケストラで始まります。弦楽器のこの旋律が聞こえてくるとなんて素敵なメロディー!と胸がいっぱいになります。第2楽章はアダージョ。個人的にはこの楽章が1番好き。ゆったりしたメロディーで広い草原に静かに雨が降っているイメージ。低音部では雨がやむのを待ちながら動物たちが蠢いているような・・3楽章は軽快で可愛らしい曲ですね。8分の6がオケとぴったり合うと本当に気持ちいい。途中の短調の旋律は吹いていて快感です・・・
ああ、やっぱりモーツァルトって素晴らしい。シンガポールでレッスンについていた頃、ピアノ伴奏でこの曲を演奏したことがありました。が、「オーケストラでこの曲を演奏する機会はめったにないのでソナタや5重奏を中心に練習しましょう」と当時の先生に言われた記憶があります。それなのに代奏で何度も吹かせていただける私って!なんて幸せなのでしょう。めったにないこの機会を満喫させていただきますね。でも、なぜに師匠橋爪先生から全調のスケールと分散和音を毎週鬼のように吹かされたのかわかりました。先生がいらっしゃるまで皆さまにも楽しんでいただけますよう精進してまいりますのでどうかよろしくお付き合いくださいませ。(Cl.M.N)
|
|
|
| 2012年12月22日(土) |
| 譜読み(初見大会) |
|
第28回の定期演奏会が終わり、お休みの日曜日を1回挟んで、また練習日がやってきた。本番があってもなくても、先を見越して日程も練習曲目もきちんと組んでおくような団体もあるけれど、ウチの団は、ひとつが終わらないと次の計画になかなか着手できない。そんなわけで、先日の演奏会が終わってから、次の定期演奏会に向けての選曲会議があり、楽譜を手配して、今日の練習となった。楽譜を配り、せーの!で合わせる譜読みである。曲目は、シューベルトの交響曲第6番と、モーツァルトのクラリネット協奏曲。これらの曲になった経緯を、備忘録がてらここに書いておく。
ここ何年間か、ベートーヴェンの交響曲を継続して取り組んでいた武蔵野室内アンサンブルだが、次に取り組むのは何がよいだろうか。半年前の選曲会議で話題になったのは、メンデルスゾーンとハイドンだった。じっくり取り組むならメンデルスゾーンなのだが、今の武蔵野の弱点は、ヴァイオリンが少ないことである。本番には何とか助っ人を集めているものの、普段の練習に参加するメンバーの絶対数が少ない。弦五部でかっちり動くメンデルスゾーンだと、ちょっと厳しいかも。Vnが少なくても大丈夫という曲は無いけれども、という前置きがついて、浮上したのがシューベルトとシューマン。特にシューベルトを、ということで、何回かシリーズで取り上げることにした。
ソリストを招いての協奏曲は、演奏する私たちにも刺激になるし、聴きに来てくださるお客様へもアピール度が高い。これまでも、フルートやチューバ、ギター、マリンバなどの協奏曲を取り上げてきた。ただし、小編成の団ゆえに、お財布も小さい。地元貢献という名の下にボランティアで演奏して頂ける方や、これから売り出す音大生などにソリストをお願いしているのが現状である。今回は、クラリネットのMさんの師匠である橋爪氏に、地元オケとのコラボを引き受けいただけることになった。万歳! 今後は、器楽の協奏曲だけでなく、歌曲やアリアなど歌い手との共演できる曲目も探していきたい。
モーツァルトのクラリネット協奏曲が決まり、それとのバランスでシューベルトは交響曲6番がしっくりくるだろう、と決定。民音から楽譜を借りて、今日の練習となった。
譜読みは、若手Sくんがコンサートマスター、I爺チーフの指揮のもとに、次の定期の2曲を通し、さらに2月のアンサンブル大会で全体合奏をするモーツァルトの交響曲9番を通した。その後、駅前の居酒屋で長時間の大忘年会。新人のIくんは楽しい人だということがわかり、親世代のTさん・Kさん・Iさんが「ウチの娘を貰ってほしい」と婿さん話題で盛り上がったとのこと、これはKさんからの報告である。みなさん、年末年始の飲み過ぎにはご注意を。次回の練習は1月13日。アンサンブル大会のエントリー〆切もこの日。そして1月27日の総会に欠席する方は、委任状のご準備を。それではみなさん、よいお年をお迎えください。(なおちゃん)
|
|
|
| 2012年11月25日(日) |
| 本番1週間前 |
|
少し広い練習所を確保して、いつもより少し長い時間をかけて仕上げの練習。長丁場なのでMozart→Holst→Beethovenとおおまかな時間割が決めてあった。このように曲順が決まっていると、降り番のメンバーがそれにあわせて練習に来られるのでありがたい。
協奏曲の練習は、毎回毎回ソリストと合わせて合奏を練習している。これはとても有り難いことというだけでなく、とても珍しく貴重なことだと言わなければならない。普通、ソリストを依頼するときは、練習○回と本番●回で¥おいくら万円、となるので、オケが仕上がりつつある本番直前に1,2回合わせ、あとは当日、というパターンが多い。ところが、武蔵野の場合、ソリストのKさんは武蔵野のメンバーなので、ふだんの練習にも参加されている。Beethoven
ではTutti(合奏)の席に座っているが、Mozartのときは前に出てソロを吹くわけだ。もちろん、何回練習をご一緒いただいても、¥おいくら万円もお支払いしていない。(^^) 武蔵野って、何て贅沢なんだろう。ソロを聴きながら、その息づかいや歌い方に添えるように合奏を積み重ねていけるのだ。
さて、今回の武蔵野室内アンサンブルは、前回までとは少し顔ぶれを変えて、来週の演奏会に臨むこととなった。まず、Trpパートは新入団員2名を迎えた。Obパートも旧メンバーの転勤によって一新。少人数の室内アンサンブルにとっては、管楽器が変わるとサウンドも新しい色を見せる。さらに、Vnが、旧知のメンバーの出入りがあり、故障者もあって、初めてご一緒する方々を何人かお迎えした。これまで、私たちの団は、お互いをよく知り合った上で培ってきた呼吸や音色を自分たちのサウンドとし、それは少人数のアンサンブルならではの良さであった。今回はそこに新しい風が入ることになる。新しい方々を、武蔵野のサウンドにうまく巻き込んで、フレッシュ武蔵野の音楽を紡ぎだしていければ・・・・と思う。本番のステージに、武蔵野らしい風が吹くことを祈って。(なおちゃん)
|
|
|
| 2012年11月11日(日) |
|
|
今日はいろいろビックリがありました。
1)ピッカピカのTimpani登場
M氏が半年前にオーダーしていたWienのハンドメイドTimpaniがやっと到着し、本日練習でお披露目されました。このシリーズは日本初上陸だそうで、N響はじめプロの方々も注目の一品を武蔵野で初めて音だしとなりました。みためからして 正にウィーン風、輝いて品格のある顔立ち、深いけれど軽やかな羊皮特有の響きは、M家の家宝とともに武蔵野の宝ですね!
2)ワールドワイドなオケ
今日、タイからK山さん、インドからK田さんが練習のためだけに!来てくださいました。そして練習後の飲み会でも盛り上がりました。これからも一時帰国の際は必ず顔を出してくださいねー。
3)ちょっとびっくり
Sさんが練習中にトイレに行きましたが、暗くてスイッチを間違えて、緊急呼び出しボタンを押して、管理人のおじさんが来てしまいました。でも、さすが武蔵野のみなさんは微塵も動じず落ち着いて対応。ホッ。
<肝心の練習内容>
練習の始めに指揮者から「あと練習は今日を含めて3回です。今日は細かい約束事を今一度確認しましょう」と話があり、強弱、拍感、フレーズ、曲の変わり目、パート感の受け渡し、etc.を確認しながら練習を進めました。
私見ですが、特にベートーヴェンは、強弱、sub Pなどなど、楽譜に書いてあることを、その通りにきちんと演奏するだけで曲になるように書かれているように思います。なので、まずは楽譜に書いてあることは全て意識して音を造り、その上で他のパートの動き、全体の流れを意識したら、気持ちよいアンサンブルが体感できるのではないでしょうか。
技術的に難しくてできないのは、我々ある程度仕方がないと思いますが、言われたら出来るのに、何回も同じ箇所で同じ注意を受けるなんてことは恥ずかしいかな。ちょっと意識しただけですぐに直せるはずなので、がんばって良い本番を迎えましょう。(I爺)
|
|
|
| 2012年10月28日(日) |
| みんな雨のせい |
|
練習場所まで自転車で移動している私は、出かける前に必ず空を見上げる。「大丈夫そう・・・。」なんて言い聞かせてペダルを踏み込んで5分後、「うっそ・・・」雨がポツポツ降り始めた。会館に着き、あわただしく雨用ポンチョを脱いで練習場所に行くと、何だかいつもと違う。みんな楽器を出すどころか、いろんな話が飛び交っている。「傘の事は気にしていたのに、楽器を電車の中に忘れてしまった!!」「直前まで練習していた楽譜を自宅に忘れて取りに帰った」「雨で近くの駐車場が空いてな~い」など、いつになくザワザワ。でも数分後、楽器はちゃんとあったし、楽譜を取りに行ったメンバーも、みんな練習場に着いた。森山さんが「ここ(武蔵野会館)は、この前も雨でした・・・。」そう、みんな雨のせいなんです。気圧が低いと感覚がちょっと変わってしまうし。
さて練習♪ ベートーヴェン→クサビ(点でなく楔型のスタッカート)の確認や、今までの再確認。フルートコンチェルト→ポイントは、コンミスの助言どおり「ソリストに寄り添う」コンチェルトは一体感を感じたとき、これが一番の醍醐味だから。合ったとき、とても楽しい。ホルスト→森山さんの“こう作り上げたい”という気持ちに応えたいのだが、3楽章はたまにマジックにかかり見失いそうになる。でも、確実に面白くなってきた。これで練習終了♪
帰りも雨。私は、この後9:30まで仕事だった。帰るとき空を見上げると、雨は止んでいた。やっぱり私は晴れ女(^^)v 練習も残すところ少なくなりました。次回は青少年等交流センターです。晴れることを願って、よろしくお願いしま~す! (Vla tommy)
|
|
|
| 2012年10月14日(日) |
|
|
個人的には、前日の大学OBオケ合宿・演奏会に引き続いての練習に、ちょっとバテ気味で参加。若い頃は、前日練習で程よく唇の筋肉がほぐれたのに、年齢をとると結構キツイ。管楽器は年齢との闘いが、遅かれ早かれ出てくることを、今回も体感。
・・・なんて後ろ向きの話は止めて、今日は12月2日(日)の本番に向けた練習日記を書きます。そして、今回は自分のパートの話ではなく、今日の練習で感動(感じた)ことを書きます。
指揮者の森山さんが、「ここはもっとpppで・・・・・」と弦楽器に指示。弦のみなさんは、pppppを出そうと、自分の身体も前屈みになってpppp・・・・になっていく状態。後ろから見てると、よく見える。
すると、コンミス(コンサートミストレス)のYさんが一言。「このpppは、こうして弾けばpppになる。逆に身体を起こして、こう弾く!」ーーーー
指揮者から指示されたイメージ通り、あるいはそれに近い音を出すのが、私たち演奏者の役割。それを、奏者として技術的にどうすれば、要求された音や表現したいメロディになるのか・・・・・・? なかなK難しい。
Yさんの具体的かつ的確な指導は凄い! さすが、コンミス!と感動。思わず、管楽器のメンバーで顔を見合わせてしまった。そういう音になったのだから。
自分の楽器で、どういう奏法をしたら、指揮者が求めている音や作曲者が求めている(想像)音楽になっていくのかを追求していくことが大事なことだと思う。それには、練習しかない。
本番まで1ヶ月半。悔いのない本番を迎えるためにも、求められる音が出るための奏法や音色にこだわって、練習を続けていこう!と感じた14日(日)の練習でした。(Hrn N.I.)
|
|
|
| 2012年9月23日(日) |
| ジェットコースター |
|
雨の一日でした。雨の日はホントに憂鬱です。移動ももちろんのこと、湿気を帯びた楽器も嫌そ~な音を出してきます(→これは奏者のせいでした。)楽器も私も、何とか雨の日の練習が楽しくなるようなことを考えてみようと思います。お揃いのレインカバーをまとってみるとか・・・・。
最初はベートーヴェン。sf - (sub)p - ff - p - f。全体のテンポがあがってくるに従って、目まぐるしくうねる強弱記号の連続は、まるでジェットコースターです。私は絶叫系は大の苦手ですが、それでもたまに乗ることがあります。スタートして最初の山を登り切るまでの静寂。ppでしょうか。いったんrit.したかと思いきや、そこから一気にffーーー!!! ppが前にあるからこそ、次のffが効く。一定のスピード(ff)ばかりが続くと、乗客が慣れてしまって、絶叫が途切れるからでしょうか、たまにガクッとsub pになります。そして再び、sf、sf、sf、<<<ffーー!!! ゴール!!! です。
こんな息の切れる演奏はいかがかと思いますが、乗客(観客)を惹きつけて離さない、最後の音が鳴りやんだ時にジェットコースターが最後に止まったときのようなため息が出たら最高なんじゃないかと思います。(=^^=)
ちょうど1年前、ヨーヨー・マ with Tonhalle Orchesterの来日公演に行ってきました。ドボコン(ドヴォルザークのチェロコンチェルト)とブラームス2番でした。印象的だったのは、このオーケストラの方たち、とっても自然体だったんです。まず、オケメンが入ってくるときに、楽器の他にバッグを提げてる方がちらほら。予備の弦だとか演奏に必要な小道具が入っているようなバッグじゃなくて、完全私物です。椅子の背もたれにひょいっと掛けて、さて始めるか♪って感じです。そして私語・・・・。左右のみならず、前後で、しかも楽しそうに微笑みあったり・・・。演奏中のこんな風景、たま~に見るけどココまではあんまり見られないです。ブラームスでは降り番のはずのヨーヨー・マがチェロパートに加わりました。しかも2プルト裏に。するとさらに楽しそうにパート内をかき乱す(?)ヨーヨー。曲の流れに合わせて、大袈裟に隣のメンバーの運弓を真似してみたり、ものすごく躍動的に弾いて笑わせたり・・・もちろん全て演奏に支障のない程度の(気づいてない人もいたと思う)モノでしたが、聴いているこちら側が目が離せないぐらいのブラームスでした。
オーケストラのもつ雰囲気って、やはり伝わりますね~。(Vc.U子)
|
|
|
| 2012年9月9日(日) |
|
|
Tシャツに首から下げたタオルが今日もお似合いの森山先生です。ぽっこり出ているお腹も何ともチャーミングです。でも、時折、り、気品漂う空気がそこからピンと発せられています。
そんな森山先生が参考にするようにとおっしゃっていたベートーヴェン、ジンマンの録音をさっそく予習して臨んだ本日の練習でした・・・。テンポに関しては、フレージングのイメージをもっともっと先取りして掴まないと思い通りのテンポに収まらない。ポーイングやスラーを工夫したりして、わずかコンマ数秒のタイミングを合わせます。パート内での息を合わせるのももちろん、似たような作業をしている他パートさんとのニュアンスも揃えなくてはいけません。まだまだやるコトいっぱいあるな~。・・・と、その前に自分がもっとちゃんと弾けてなきゃ(>_<)
目標のテンポがあって、今はまだそれに向かって走っている状態。そうではなく、目標としている曲調やイメージがあって、そうして演奏したらこのテンポになりました、って時に、チューリッヒのトーンハレの路上演奏のようになるのかなぁ、と思います。目標テンポに、最終的にそんな風にたどり着けたらいいな、と。
練習の翌日、同じパートのYさんのグループ絵画展に行ってきました。とっても素敵な雰囲気の作品でした。音楽と絵画は違うけれど、何かを表現するという意味ではどちらも同じです。いろいろなジャンルで感性を高めているメンバーと一緒に合奏できるのって楽しいな~、幸せだなぁ~って改めて感じました。(Vc,U子)
|
|
|
| 2012年8月26日(日) |
| 夏休み明け!! |
|
毎日お暑うございます。1ヶ月ぶりに練習再開となった武蔵野。今日は、本番の指揮者の森山さんとの初合わせ。私たちオケも、指揮者も、「さて、相手がどう出るか? どう来るか??」とドキドキワクワクの緊張感を持っての合奏となった。
べートーヴェンについては、音を出す前に森山さんから“こんなイメージで”という話があったが、その具体的な例としてあがったのが、David Zinman指揮、Zurich Tonhalle の演奏。ひとつの例として、一度は聴いておいてください、とのことだった。一楽章のごく一部が聴けるYouTubeがこちら。路上演奏なので全部の楽器は入っていないが、かしこまったところの全くない、血湧き肉躍るベートーヴェンが伝わってくる。(アドレスをクリックしてもジャンプしない場合は、コピー・ペーストして別ウィンドウで開いてください。何曲も入っているので、37曲目を選択。交響曲2番のストリート演奏が聴けます。)
http://youtube.digru.com/?v=Beethoven%3A+David+Zinman%3A+Tonhalle+Orchestra
最初の合奏は、速さにのまれてしまわないように必死だった。けれど、そのスピード感や躍動感に浸り、味わい、乗っかり、コントロールできるようになると、一段上の音楽が出てくるのかも。pとppの違い、fとffの違いなども指示がある。丁寧に細かく読んでいくと浮き上がってくる音のうねりが見える。p<cresc<p、=ピアノかクレシェンドして少し大きくなってすぐにピアノに音量を落とす、という表現もあちらこちらにある。合奏の合間に、「やっぱり、こっちのボーイング(弓使い)にした方がいいね。」という指示や相談が弦楽器の間で交わされる。7月に、だいぶやったと思っていたけれど、さすがはベートーヴェン、まだまだ奥が深い。
練習後は暑気払い&新入団員歓迎会。トランペットとヴァイオリンに新しいメンバーが加わった。飲んで食べて、たくさんおしゃべりをする。ひとりひとりの素顔を知ることが、合奏の時の良いコミュニケーションにつながるはず。特に、私たちのようなアマチュアは、技術向上も大事だけど、みんなでひとつの音楽を作り上げよう、という気持ちの結びつきも、演奏の出来不出来に大きく影響があると思うから。(なおちゃん)
|
|
|
| 2012年7月29日(日) |
| 練習報告とは別に・・・・少し先のことを相談しました |
|
29日は、先週に引き続きKさんの指揮の下にみんなで聴きあっての合奏練習。しつこくしつこくベートーヴェンをやっているうちに、何となく形になってきたような気がする。昨今の武蔵野はVnが人数不足が悩みなのだが、今日は2ndが少ないわ、と気づくと1stから自主的に応援に駆けつける姿がある。場を見て、自分たちで助け合える関係、というのも素敵だ。
さて、今日の練習に先立って、先日、団長を中心に委員会が開かれた。これからの武蔵野がどんな方向に進んでいけばよいか、どんな練習をしていけばよいか、という真面目な話し合いなのだが、“飲みながら”の会のため、建設的な話が脱線しがちになるのが玉にキズ。それでも、おおむね以下のような話になったので、この場を借りてご報告。
前回の演奏会でブラームスに挑戦したことから、”歌える”曲へレパートリーを広げていけるとよい、という話題。これまで、年に1回ベートーヴェンの交響曲を取り上げてきたが、メンデルスゾーンやシューマンにも挑戦してみるとよいのでは、という提案があった。演奏会で取り上げるにはやり甲斐のある選曲だ。
また、“団として、アンサンブルが上手になりたい”という話題。これに応えるには、ハイドンの交響曲を片っ端から練習していくとよいのかもしれない。ただし、ハイドンの場合は、半年じっくり練り上げるのではなく、空いた時間をみつけてちょこちょこと練習し、録音し、それを聴く、という勉強会形式はどうか、という提案があった。
来年の春の演奏会は、立川の教会ではなく、秋川のキララホールになりそうだ、ということ。来年の秋は、今まで使っていないホール探して開拓していこうということ。年に2回の定期演奏会だけでなく、学校での音楽教室なども機会があれば取り組んでいけると楽しみながらも力量アップをめざせるのではないか、ということ。などなど。・・・以上、盛りだくさんの内容だが、時期を見て改めてみなさんにご報告・協議となると思う。ご意見、ご質問があれば、団長または委員会まで遠慮無くどうぞ。(なおちゃん)
|
|
|
| 2012年7月22日(日) |
| お互いに聴きあってアンサンブルをする |
|
本番の指揮者が来ないときは、メンバーの誰かが前に立って仕切ることが多い。今日は、こういう時にいつも指揮をするM氏が不在、コンサートミストレスのYさんもお休み。ということで、木管のKさんにお願いしたところ、指揮棒持参で練習所に来てくれた。パチパチパチ!! 「ちゃんと指揮できるほどにはこの曲を知らないのよ。」と謙遜するKさん、細かい指摘はなしにして、きっちりしたテンポで通し練習をした。1回通したところで、「うーん、もう一回やってみる?」 ・・・2回目の方が、明らかにさっきよりは合っている。自分で弾いていても、周りを聴いて合わせる余裕があるのがわかる。合間に、めいめいが、他所のパートの譜面をのぞいてボーイングを確認したり、譜割りのあやしいところを、口ずさんで確認したりする。「とにかく今日は、キレイな音で、周りと合わせて。強弱は後回しでいいから。」と、Iさんが設定した目標を意識しながら4楽章までを通す。「じゃあ、休憩してから、もう一回1楽章をやろっか。」・・・3回目になると、sfzやアクセントのニュアンスも、何となくだけど周りと自分が合ってきているのがわかる。そう、まだまだ、通せば通すほど、やればやるほど、右肩上がりでマトモになっていく段階なのだから。もう少し練習を重ねると、「何度やっても、しっくりいかないねえ。」というように上昇カーブが緩やかになっていく。ここまでくると、指揮者やトレーナーなど、客観的な指摘が重要になるのだ。
それにしても、今日は疲れた。よく考えてみると、ひたすら、練習時間中は合奏=弾いていたのだ。そうか、普段は、他のパートが指示を受けている間の1、2分や、指揮者が何か説明や解釈を話している間が、身体にとっては休憩だったのだ。延々と3時間弾き続けた練習。手も指も使ったけれど、耳も頭も使う、有意義なアンサンブルだった。仕切る人がいない練習、というのも、少人数で気心しれた私たちにはプラスに作用するものだ。(なおちゃん)
|
|
|
| 2012年7月8日(日) |
| ボーイング(運弓) |
|
新シーズンは、ベートーヴェンの交響曲2番で練習開始。この曲は、2006年冬の定期演奏会で演奏した曲なので、今日集まったメンバーのうちの半数ぐらいは、当時の舞台に乗っていた顔ぶれだ。何となく覚えている曲だから、とりあえず一曲まるまるを通してみる。いわゆる、「初見大会」である。
ライブラリアンのKさんが持ってきてくれた楽譜には、前回の演奏会のボーイング(弦楽器の運弓)が書き込まれている。私の譜面の1楽章のAllegroのテーマは、ダウン・ダウン、アップ・アップと書いてあるものを鉛筆で消して、ダウン・アップ、ダウン・アップ、となっていた。他のパートもまた然り。みんなでその通りに弾いてみて、大きな問題は無さそうだ。とりあえず、このボーイングで練習を始めていこう。指揮者が細かい味付けをしていくなかで、みんなでまた少しずつ変えていけば良いんじゃないかな。
新しい曲の練習を始める時は、いつも弦楽器の各パート間でボーイングを合わせるのが最初のシゴトとなる。曲によっては、何通りかのボーイングが考えられるものもあり、「それって、そう弾くの?」などと相談しているだけで、あっという間に練習時間を喰ってしまうため、合奏とは別に、各パートのトップだけ集まって相談して運弓を決めておくこともある。今回は、自分たちが演奏したボーイングの書き込みのある譜面を使うこと、曲の構造がシンプルなBeethovenであることなどから、「とりあえず、これでいこう」との結論がスムーズだった。
曲の構造がシンプル、と書いたけれど、この曲がシンプルだから簡単、というわけではない。シンプルなものをシンプルに聞こえるように弾くのは難しい。歯が立たないほど難しいわけじゃないけれど、どこまでやっても「これでいいかな」に行きつかないのがBeethovenだと思うのだ。(なおちゃん)
|
|
|
| 2012年6月3日(日) |
| あと1週間 |
|
Brahmsの練習をしていると、こんな曲を演奏するグループって、武蔵野ぐらいだなぁ、武蔵野らしい曲かもなぁ、と思うことがあります。オーケストラなのに、ヴァイオリンなしの編成。ヴァイオリンが降り番でも、ヴィオラに持ち替えられるメンバーがいるからこその、Brahmsのセレナーデです。木管やホルン、弦楽器が絡み合っていく音の厚みを聴いていると、オーボエの音、とか、クラリネットの音、とかの楽器の音ではなく、オーボエのTさんの音、クラリネットのMさんの音、というようにその人独自の声のように聴いている自分がいます。チームで参加している弦楽器も、チェロのKさんやYさんの音、というように聴こえています。小編成の楽団で、同じメンバーと長く音を紡いできたからこそ、その人その人の持ち味や音色がより濃く反映されるのでしょう。
武蔵野には、遠距離から通ってきている方が何人かいます。転勤で500kmの彼方へ転居してしまった方、武蔵野が気に入って隣の県のそのまた向こうの県から通ってくださる方。都心に住んでいるのに、下り電車で1時間以上乗って毎回の練習に来る方。もっともっと通いやすいところに、趣味で参加できる楽団はあるのだろうけれど、そうまでさせる武蔵野の魅力って何だろう?と訊かれました。小編成の楽団で、同じメンバーと長く音を紡いでいくことの魅力、気ごころ知れた仲間と音を練り上げる面白さ、のようなものかなぁ。
さて、ここ半年は、リレー形式で練習日記を書いてきました。ホームページ係からの依頼を、快く引き受けてくれた皆さん、どうもありがとうございました。そして、今後ともよろしくお願いします。おっとその前に、来週の本番もよろしくお願いします。(ホームページ係:なおちゃん) |
|
|
| 2012年5月27日(日) |
|
|
今日は、朝からブラームス、昼からモーツァルト、夕方には疲労困憊でした。皆さん、お疲れ様でした。(私はたった今、飛行機で帰ってきました。へとへとです。)
今日の私の練習目標は、譜面を見ずに周りの演奏者と指揮者を見て演奏すること。そろそろ指回し、曲の流れは覚えてきましたので、皆とどのように音を重ねていくかを楽しみながら練習させていただきました。
武蔵野室内アンサンブルに来て、はや4年経ちます。その間、様々な経験、事情、腕を持っている人たちと音楽をさせてもらいましたが、皆の音に囲まれてとても幸せな気持ちで過ごしました。
世の中にはいっぱいオケがありますが、各々のオケの色(良さ)とは、そこで実際に演奏している人が、主張したり、共感したり、時には妥協しながら音楽を作り上げる中にあると思います。今、目の前のこれだけの色々な人たちが集まって武蔵野のオケの色を作っているのだなー、と考えながら吹いていたら、あら間違えた!(譜面、あまり見てなかったし) 指揮者が困った顔をしています。集中、集中。やっぱり集中力が落ちてきている今日この頃です。
旅行や食事会と同じで、本番よりその直前の方が期待と不安でわくわくします。本番まであと2週間。そんな楽しい気持ちを大事にして練習に励みたいと思います。(OBのT)
|
|
|
| 2012年5月20日(日) |
|
|
チューニングに始まり、いつもとっても頼りにしているObの音色。今日は500kmのはるか彼方で、ブラームスもモーツァルトも心細いことこの上無し・・・・・
ところで、ひとつの音には「始まり」と「途中」と「終わり」の3つがあります。そして、どの音にもこの3つに相応しいそれぞれの「カタチ」があるのだそうです。
「始まりのカタチ」は比較的習得しやすく、丁寧に発音する、明るく発音する、というような、ちょっとした心がけでコツがつかめるようになります。
「終わりのカタチ」は少し難しくなります。なぜかというと、終わる前に次の音のことを考えてしまい、結局終わらないまま移ってしまいがちだからです。
「途中のカタチ」は一番難しくて、実は私もよくわかりません。身のある音を出すということなのだと思います。言うは易く行うは難し。
音と空白(休符)が連続するとフレーズになるわけですが、ここにも「始まり」と「途中」と「終わり」があります。
モーツァルトは、音とフレーズの「終わりのカタチ」を整えると、グッと雰囲気が変わるみたいです。しっくりこない時は「押して駄目なら引いてみろ」精神で取り組むと、意外な発見があるかも。(α)
|
|
|
| 2012年5月13日(日 ) |
| 今回も、ブラームスから始まりました! |
|
ひとりひとりがちゃんとしたイメージを持ってメロディを奏でないと、すぐにテンポが遅くなってしまったり、受け継ぎが乱れてしまいます。うーん、難しい・・・・。よく言われるのが、ブラームスは年齢を重ねれば重ねるほど、曲の深み、重みを理解できる、ということ。僕はあと何年したら、ブラームスを心から理解できるのでしょうか・・・。
曲は変わってモーツァルト、今回の練習からトランペットも加わりました。トランペットが入ると、一気にオーケストラが華やぎますね! ホルンパートとしても、同じ金管楽器が入ると心強いです。しかし、今回も金管楽器は「抑えて!」「小さく!」と何度も指摘を受けました。
曲の時代、雰囲気、編成の大きさなどから求められる音色に、特にホルンパートはさらに工夫が必要だと感じさせられました・・・。
日々精進です。がんばります!(Hrn T.Y.)
|
|
|
| 2012年4月22日(日) |
| 新メンバー歓迎! |
|
今日、チェロパートに昭島在住の I さんが入団されました。本当に嬉しいです。人数の少ない団ですが、 I さん、一緒に楽しみましょう! と言いたい私ですが、ブラームス、なかなかまだ楽しむ境地になれずにいるのがホンネです・・・・・。「前回よりはさらっているかも・・・次回まで待ってみようか・・・」なんて、指揮者の心のつぶやきが聞こえてくるようでした。見逃してくれたかもーとホッとしつつ、そんなこと思ってないで、いいメロディなんだからもっと練習しなくちゃだめでしょ!と叱咤激励しています。
練習後、ふと、あと何回あるんだっけ?と練習日程表を見て「!!」 ゲネプロを入れてあと5回。次回の練習までずいぶん間がありますよ~。危ない危ない、のんびりしているとあっという間に5月13日が来そうです。今よりずっとセレナーデが楽しめるように、GWもありますが、ヴィオラのケースの蓋を開けようと思います。それから、補足しますが、モーツァルトは結構楽しんでいますよ。(tommy)
|
|
|
| 2012年4月8日(日) |
| 管分奏 |
|
今日は弦と管に分かれての分奏練習。今回のBrahmsは管楽器中心の曲ということもあり、Brahmsオンリーの練習となった。これまでの合奏中心の練習から、細かく分解してソロやアンサンブルを確かめ合う練習となって、非常に有意義な約3.5時間となった。それにしても、反省に反省の3.5時間でもあった。
自分自身、練習不足を再確認する分奏練習となった。学生オケをやっていた頃は、暗譜するまで指が自然に動いsていたし、他の楽器のフレーズも頭に入っていた。今は、出番までの休止小節を指を数えることで精いっぱいで、周りのメロディを感じ合う余裕がない・・・とか、自分の出番で技術的に難易度の高いフレーズも、楽譜を見ながら演奏している自分・・・。
「練習はウソをつかない」。これは、元プロ野球監督の野村さんが著書で語っている言葉だが、練習不足のまま分奏・合奏に臨んでいるとウソが露呈する。今週末の休日は、すべての予定をキャンセルして、ひたすら個人練習に充てようと思っている。大好きなBrahmsが楽しく演奏できるまで・・・・・・。(Hrn N.I)
|
|
|
| 2012年4月2日(月) |
| 中神小ランチルームにて |
|
いや~、ブラームス、いい曲ですね~。聞けば聞くほど好きになります。武蔵野にとって初挑戦、モーツァルトやベートーヴェンと違って、長いフレーズ、和音の響きなど勉強することがいっぱいありますね。
今の武蔵野、なかなか大変な状況ですが、野崎さんの練習では、少なくとも音楽造りができるように、個人でよくさらっておかなければいけないと思います。貴重な合奏の時間、もっと効率よく良い練習ができるよう、とにかく一生懸命さらいましょう!! いいアンサンブルしましょう!! 武蔵野を活性化させましょう!! (Vc K子)
|
|
|
| 2012年3月18日(日) |
| 中神小学校 |
|
今日は、今度の本番指揮者である野崎さん指揮による初合わせ。まずはテンポや曲のポイントを確認、ということで、モーツァルトの序曲「劇場支配人」、交響曲第35番「ハフナー」、ブラームスのセレナーデ2番の順番で全曲練習。
序曲は4拍子で書かれていることもあり、「そんなに速くはしません」との言葉をいただき、ちょっとホッ。伸ばしや頭拍、キザミのニュアンスなどを確認しました。次回までに、みなさんパート譜に小節番号を書き込んでおきましょうね。
ハフナーは、1楽章→4楽章→3楽章→2楽章の順で練習。4楽章が速かったですね。アンサンブル・リーダーの一言もあり、焦り感で固くなってしまわないように、少しゆっくりなテンポから練習していって、落ち着いて出来るようになるのを確認しながら、徐々にテンポアップしていきましょう、となりました。
ブラームスは、室内楽的な曲なので、個人個人がフレーズなどを明確に表現するようにとの指示がありました。曲を何回も聞いて、他のパートとのからみなども覚えましょうね。4月8日はブンソウですので、その辺をお互いに確認し合いましょう。本番ではアンサンブルを十分楽しんで、美酒を堪能しましょう。
あと、T君が昨日ヨーロッパ演奏旅行から無事帰国したとのことで、お土産のチョコレートをみんなでいただきました。ごちそうさまでした!(木管後列Y.I.)
|
|
|
| 2012年3月11日(日) |
| 初合奏 |
|
弦分奏・管分奏の各2回を経て、今回のプログラムの初合奏となった今日。とりあえず全体でどんな音が鳴るのか、曲のイメージをつかむ合奏である。前半にモーツアルトの序曲と交響曲、後半にブラームスのセレナーデ。
モーツアルトは、武蔵野では何度も取り上げているはずなのに、ちっとも“手慣れた”音にはならず。よく知ってる曲なのに、弾いているつもりなのに、やっぱり、モーツアルトに聴こえない~。家に帰って、メトロノームつけてさらおう、いや、その前にエチュードさらおう。そう思ったのは、私だけじゃなかったと聞いて、妙な安心感を覚えてしまった。その一方で、ブラームスは・・・武蔵野でブラームスを演るのは初めてなのだ!! ちゃんと弾けてるかどうかは別にしても、ずっしり中身の詰まったブラームスの音にするために、ずっしり重さをかけて弾いてしまえるところが、単純に気持ちがイイ。いやいや、もっと練らないといけないのだけど。
震災から1年のこの日。2:46には練習所で黙祷を捧げた。去年、3月末に練習を再開した日に「武蔵野らしく、やれる人だけでも、練習をやりましょう」と団長が声をかけていたことを思い出した。“武蔵野らしく”。無理をせず、でも、一生懸命に、楽しんで続けていくこと、なのだと思う。
ここ1カ月ほど、ホームページ更新をお休みさせていただいた。ホームページ係の私のパソコンが入院中だったのだ。(“私”が入院中、と勘違いした方もいたようで、ご心配をおかけしました!?)昨夜めでたく退院して、今日から、通常通り練習日更新となります。引き続き、よろしくお願いします。
追伸:モーツアルトの序曲、譜面に練習番号がありません。時間のある時に、小節番号をふっておくとよいですね。(な)
|
|
|
| 2012年2月12日(日) |
| 弦トップ練習 |
|
弦は5パートのトップが集まってのトップ練習でした。各パートの諸々の“都合”を持ち寄ってのボウイング合わせ、5人分の感想や成果を聞いて、この“練習日記”に載せるつもりだったのですが・・・・練習場のアルジの伝達ミスで伝わらず。2ndVnのOさんのみ、コメントを頂戴しましたので、今日はそれをお伝えします。(Oさん、ひとりだけでごめんなさい。)他の弦楽器の方々には、次回の練習日記にてコメントを戴くつもりです。(by練習場のアルジ)
モーツァルトの2ndヴァイオリンは難しいなー。アマチュアにはたぶん無理。今回 のハフナーも気が重いのですが、Yさんに無理のない自然なボウイングを教えても らって、なるほどなーの連続でした。(O) |
|
|
| 2012年1月29日(日) |
| アンサンブル大会 |
|
早いもので、中国単身赴任もすでに1年半が経過、ただいま旧正月休暇を利用して寒い日本に一時帰国中です。その間にアンサンブル大会を設定していただき、1月22日・28日に練習、そして29日に本番というスケジュールで久しぶりに武蔵野の仲間たちと音楽を楽しむことが出来ました。やはり気の合う仲間とのアンサンブルはいいものです。今回は、ロッシーニの弦楽ソナタ、ハイドンの交響曲第6番「朝」、テレマンのターフェル・ムジーク、バッハのブランデンブルグ協奏曲第3番に参加させていただきましたが、たった2回の練習にしてはまずまずの出来だったと思います。
最近はバロック音楽にハマっていて、聴くのも弾くのも大好きなのですが、バロックはスピードと軽さが演奏のポイントではないかと思っています。今回のテレマンやバッハは、そんなイメージが出せればいいと思いましたが、限られた練習時間ではなかなかうまくいかなかったところもあり、また次の機会にいろいろやってみたいと思っています。付き合っていただいた皆さんには、ただただ感謝です。次回6月の本番の快演をお祈りします。(N)
 |
|
|
| 2012年1月22日(日) |
| アンサンブル三昧 |
|
昨日は、この冬初めての積雪でしたが、幸い天気は回復し、予定通り練習場に向かうことができました。
今日はアンサンブル大会の練習に参加させていただきました。午前中に笛3本の合わせ、午後から木管五重奏、テレマンでした。トリオは毎回ご好評を戴いているとのことで気合い十分なのでありますが、今回は少し難易度が高かった?変拍子の部分をうまくとらえることが出来るよう、もうひと頑張りです。普段のオケ練でなかなかお話しする機会がないので、こういうチャンスがあると嬉しい木五の練習は、限られた時間の中でだいぶ形が見えてきました。古楽器風に演奏するテレマンは、旧正月で帰国中のNさんの完成されたイメージについていくのがやっとでした(汗)。それでも、こんな素晴らしいお仲間と一緒にやらせてもらえるのは貴重&感動です。今日も2時間かけて来た甲斐がありました。
来週までに、最大限自分の出来ることをやって、本番を楽しみたいと思います。
(団友.Y)

|
|
|
| 2011年12月4日(日) |
|
|
本番1週間前となりました。
「本番の棒が降りる直前まで、“ここをこうした方がいい”“ここはこう演奏しよう”ということをやっていきますから」と、練習の冒頭で森山さん。今の段階で出来上がっているものを固めるための、慣れるための、流していくような練習はしません、とのことでした。ある意味で、ありがたいような、今の私たち(私だけ?)の現実に合っているような、そんな言葉でした。森山さんの言葉を実証するかのように、今日の練習中にも「ここのボーイング(弦楽器の弓づかい)、どっちにするの?」という相談が。本番1週間前に弓づかいを替えるなんて、もう慣れちゃったのに!!という意見があってもおかしくないのですが、替えた方が演奏効果が上がるのなら替えていこう、というわけです。本番直前まで、良くなる可能性があるということ(?)、言いかえれば、まだまだ発展途上の段階の演奏である、ということです。
最近の練習でよく耳にするのが、「前にも申し上げましたが・・・」「何度かお伝えしていることですが・・・」という指摘。つまり、ここはこう演奏してほしい、という指揮者からの指示を、その時はその通りできていても、次の練習のときには出来なくなっていることが多々ある、ということ。楽譜に書き込みをしても、頭から飛んでしまうのか、それとも、そう演奏している“つもり”になっているだけなのか。指揮者の指示と違う演奏をしたい、と意図的にやっているわけではなさそうなので・・・やはり忘れているのかも。そんな“思い込み”や“つもり”のひとつひとつを、この1週間で確認した方がいいなぁ、と、自戒を込めて。
本番当日には、演奏でお手伝いいただく方々だけでなく、受付など演奏以外の部分でお手伝いいただく方々もいらっしゃいます。楽しい音楽の時間を、気持ちよく、私たちと共有してもらえると嬉しいです。(な)
|
|
|
| 2011年11月28日(月) |
| “歌う”ということ |
|
いつもより2時間長く練習しただけなのに、すっかりくたびれて、昨日は早々に寝てしまいました。というわけで、昨日の練習日記です。
昭島公民館の小ホール。いつもより広いので、本番に近い形でセッティングができました。狭い練習所では気にならなかったことが、広いステージで気になることは多々あります。合奏中に誰の音を聴いて合わせるか、誰の合図を見て合わせるか。広い場所では響きも異なり、聴こえ方も違うのです。特にコンチェルトでは、これまでソリストとオーケストラが向かい合って、顔や動きが見えるところで合わせてきましたが、本番のようにソリストが観客の方を向くと(オーケストラに背を向けると)・・・気配とか空気とか呼吸とか、そういった目に見えないナニカがとても大事になってきます。
序曲・協奏曲・交響曲とも、“武蔵野の演奏”らしく方向づけられてきました。そこそこ危なげなく曲がこなれてきた一方で、ひとつひとつのフレーズを“歌う”ことが忘れられがちになっています。自分なりに思い入れのあるフレーズを、その思い入れを十分に込めて、毎回そのように演奏すること。私たちアマチュアは、技術ではプロにかなわない分、その思い入れをどれだけ音に込められるかでなんぼ、という気がします。「アマチュアは、歌えば伸びる、刻めば走る、だよね。」と昔メンバーだったOさんと笑い合ったことがありました。伸びず、走らず、でも歌う。今日の練習で森山さんが言うところの、「長い音符では縦を合わせてください。短い音符で歌ってください。」に集約される技術なのでしょう。
本番が近くなり、運営面での仕事の打ち合わせも行いました。ビラ配りなどの宣伝活動や、プログラムに載せる原稿、当日の楽器配置、受付や楽屋の管理、支払いなど、いろいろなメンバーで分担しています。さらに、今回の演奏会後のスケジュールや曲目などのことも話題になりました。目先の演奏会に集中しつつ、先のことも視野に入れていかねば。おっとその前に、終演後の打ち上げのこともね。(な)
|
|
|
| 2011年11月20日(日) |
| ♪八分音符で表現する |
|
本番3週間前。弦楽器・管楽器ともに八割方そろっての練習となりました。足りないパートにはお手伝いのプレイヤーも入ってくださっています。遠方から団のために来てくださるみなさんには、本当に頭が下がります。一緒に、“楽しい音楽の時間”を共有してもらえれば嬉しいです。
久しぶりの森山さんの合奏、まずはマリンバ協奏曲から。前回のソロ合わせのあとの特訓(?)の成果か、曲の景色がだいぶ見えるようになりました。リズミカルに縦に刻む箇所、メロディックにやわらかく流れる箇所、それぞれが際立つことで、曲の魅力が見えてきます。こうなると、細かいニュアンスがうまく合わせたくなるのですが・・・キメが決まらなかったりして、なかなか難しい。残り2回のソロ合わせで、呼吸を合わせていきたいです。
打楽器のお手伝いが入ってのモーツァルトの序曲とアンコール。そしてベートーヴェンの交響曲。本番が近くなり、曲が形作られてきたからこそ、細かいニュアンスをはっきりさせたい。「♪八分音符で表現してください」と森山さん。短い♪八分音符でも、その中にcrescやsubito
Pがある、ということです。何となくではなくcrescや何となくPではない、ということ。肌理細かに音楽を紡いでいくことを大事にしなければ。
本番1か月前から、隔週ではなく毎週の練習になります。来週は昭島公民館。広い練習所で時間も長く、実質的なゲネプロです。曲順は、序曲→交響曲→協奏曲の予定です。練習前には委員会も行われますので、委員のみなさんよろしくお願いします。(な)
|
|
|
| 2011年11月13日(日) |
| 大盛況(!?)@弦分奏 |
|
西荻窪のスタジオにて、アンサンブル・リーダーのYさんのもと、弦分奏でした。総勢14名。1st Vn:4名、2nd Vn:4名、Va:2名、Vc:4名。これまでの練習で最多ではないでしょうか。(本番1か月前だしね!!)
クレストンの大特訓。1楽章、3楽章を、まずはゆっくり、音とリズムを再確認。“3拍4連”のところは、タイをきって、みんなで歌ってから弾いてみるとぴったり合ってビックリ!歌えないと弾けない、というか、歌えれば弾ける、が見事に実証されました。いたるところで出てくる苦手なシンコペーションも、まだ完全とは言えませんが、かなり慣れてきました。それぞれが違うことをやっている場所でも、お互いを聴き合うと素直に合うということを、みんな実感したのでは?(これはクレストンに限らず、後半練習した“エロイカ”でも然り。)
こういう練習は良いですね。疑問点を確認しながら進めることで、一緒に音楽を作っている実感も育ちますし。毎回、練習日程の初期と中期に1回ずつ(できるだけ出席率の高い日に)やれば、効果が増すかも。(J)
|
|
|
| 2011年10月30日(日) |
| 練習の仕方はいくらでもある |
|
今日は、団員の指揮による練習でした。前回までの練習での課題を丁寧に洗いだすために、まずはクレストンのマリンバ協奏曲。 「みんな、”難しい難しい”というけれど、そうでもない。練習の仕方はいくらでもあるよ。」とは今日の指揮のM氏。モーツアルトやベートーヴェンと違い、現代作曲家のクレストンは、一見とっつきにくく、調性やリズム・フレーズもわかりにくいので、苦手意識が先に立ってしまうことも多いようです。少しは慣れてきたものの、ひたすら音符を追うだけでなく、フレーズのまとまりごとに区切ったり、同じリズムをやっている楽器だけで音を出したり、アクセントの付け方を工夫したり、と交通整理をしてもらうことでだいぶすっきりしました。
後半はベートーヴェンを楽章ごとに通し練習。部分的にやればできるのに、最初から通すとできなかったり忘れていたり・・・みたいなポイントを確認。「英雄」は長いので、集中力や体力の配分も考えないといけません。
遠方より友来る。休団中のKさんが楽器持参で遊びに来てくれました。Kさんは2年前からバンコク駐在中・・・そう、ニュースで起きている出来事が、こんな身近なことにつながっているんです。バンコクの洪水は一日も早く収束してほしいけれど、Kさんの一時帰国が延びて、本番も一緒に弾けるといいなぁと、つい他人の不便(?)を願ってしまいます。
次回の練習は、弦セクションのみになります。場所は西荻窪のスタジオ。13:00に荻窪駅南口に集合してバスで乗り合わせていきます。みなさんお声を掛け合って、迷子にならず集まってくださいね。詳細は、団員用掲示板にも記しておきます。(な)
|
|
|
| 2011年10月23日(日) |
| 初ソロ合わせがありました |
|
今日の練習のトピックは、マリンバの初ソロ合わせ。ソリストの飯野さんは、当団のエキストラ奏者として大半のメンバーにはお馴染みだったので、「久しぶり!」「元気だった?」などと声がかかります。挨拶も早々に、まずは楽器搬入から。各パーツごとに丁寧に毛布にくるまれたマリンバが、目の前で組み立てられていきました。マリンバって、分解して運ぶって知っていましたか? そして、あらためてマリンバってでかい!!と実感。
さて、ソロ合わせ。前回の宿題の効果か、オケの方もそれっぽいサウンドになってきましたが、細かいところはまだまだです。それでも、ソロのマリンバが入ることで、曲全体の景色がだいぶ鮮明に見えるようになってきました。ここはこんな景色、ここはこんな色合い、匂い、手触り・・・そういうイメージをメンバー全体で共有することで、「この曲、いい曲だなぁ!!」と思いながら演奏することができるのです。これは、とても大事なことです。
後半は、ベートーヴェンの英雄、3楽章→4楽章→1楽章と進みました。個人的な話題ですが、最近この「英雄」の生演奏を聴く機会が2度ありました。1度目は、フル編成の現代楽器のオーケストラで。2度目は、ちょうど私たちと同じぐらいのサイズの室内オーケストラの、古楽器奏法の団体で。もちろん、同じ曲なのに色合いも雰囲気もだいぶ違います。両方の演奏に、「いいなぁ。かっこいいなぁ。」と思うところが多くあり、そしてそれをどうやって自分たちに取り入れていくか、自分たちにも弾けるのか?なんて考えながら、今日の練習を参加しました。ちなみに、ひとつのオーケストラの演奏は、今週末BSで放送されます。ご興味のある方、ぜひどうぞ。29日夜11:30からNHKのBSプレミアムで、「NHK音楽祭 ベルリン放送交響楽団」の後半のプログラムです。(な)
|
|
|
| 2011年10月9日(日) |
| 休符を音楽的に演奏する |
|
|
|
| 2011年9月25日(日) |
| マリンバ協奏曲の譜面が配られました |
|
とても久しぶりになりましたが、練習日記の更新をぼちぼち再開しようと思います。気長に、長い目でお付き合いくださいませ。
今日は、クレストンのマリンバ協奏曲の譜面が配られました。ソリストとの初合わせは1ヶ月後。ということは、練習は今日を入れてもあと2回。本日は初見大会です。パッと見ると、シンプルな3拍子の譜面に見えます。現代の作曲家クレストンだから、5とか7とか11とかの数字が並んだ変拍子かと思ってたけど、なんだ楽勝じゃん・・・なんて思ったら大間違い。シンプルな3拍子で書かれているフレーズは、5拍フレーズだったり3+4拍フレーズだったり、それを3回繰り返していたり・・・ちょっと待ってぇ~~という初見大会でした。次回までには、もうちょっとちゃんと譜面を見ておかなければ。
今回の演奏会の指揮は、森山崇(もりやまたかし)さんにお願いしました。打楽器出身の森山さん、さすがにこの変拍子の曲をスパッと読み解いて、「ここはこんなフレーズになっていますから」と解説をしてくださいました。「それほど複雑でもないでしょう?」確かに、ね。あとは私たちが練習するのみ?!(な)
|
|
|
| 2010年5月9日(日) |
|
|
今日は、トレーナーの佐藤先生の初めての指導を受けました。
佐藤さんは、私が以前演奏(20年前)していた某オーケストラで指揮をして下さっていて、当時大変お世話になっておりました。
なぜか、思い出すのは酒を飲んでいることばかり。早速、お酒をご一緒することで頭が一杯になってしまいました。今夜はご予定があるとかで、残念なことに延期になってしまいました。
お酒の話はまた次の機会としますが、今回は、非常に分かり易い演奏上の指摘をして頂きましたので、忘れないように記録しておくことにしました。
①p,mf,ffだけある譜面で、p,mfの差が出てこない。
②四分音符のスタッカートと八分音符のスタッカートが同じ長さに聞こえる。
③フレーズの最後の音の長さが短くなる傾向がある。音の長さを正しく。
④「タカタン」のリズムと「タンタカ」のリズムの違い。前者は留まり、後者は前進
⑤細かい音符を意識して、長い音符を演奏する。
⑥細かい音符になると急ぐ傾向がある。
⑦低い音と高い音が交互に出てくる音形は、低い音符をベースに高い音符を載せる感じ。
⇒そうは思ってましたが、そうは演奏してませんでした。もう少し頭を使わないとだめかなぁ。
⑧フレーズの切れ目を教えて頂きました。
⇒低弦の楽譜ではフレーズが分かり難いのです。この指摘は助かります。
⑨強弱は装飾音符に移ります。装飾音符をしっかり演奏と意味ないです。
----------------------------------
以下は、上記指摘に対する私なりの反省(言い訳?)です。
①の指摘は、野崎さんにも何度か言われています。もう言われないようにしたいなぁ!
②の指摘は、うっかりしてました。スタッカートはみんな同じように演奏してました。練習し直しです。やってみると大分イメージが違います。これからも気を付けないと。
③は、単純ミスですね。メロディーの思い込みです。まずは、譜面に忠実でないといけませんね。
④は、初めて聞く話です。非常に分かり易い話です。今後の演奏に役立てましょう。
⑤も、野崎さんにも指摘されてますね。佐藤さんの説明は分かり易く印象に残る説明で身体に染みつきそうです。意識するだけでなく音に現れないとだめでした。
⑥は仰る通りで、長い音符では遅れるんです。耳にタコですが、この癖を強く意識すればもう少し良くなるかも知れませんね。
⑦については、そう思ってました。でも、そうは演奏してませんでしたね。もう少し頭を使わないとだめかなぁ。
⑧は、低弦の楽譜ではフレーズが分かり難いのです。この指摘は助かります。
⑨は、意識すればもう大丈夫?
他にもいろいろな指摘がありましたが、説明が違うと頭の違う箇所にマークが付く感じで分かり易いですね。いい癖付けよっと。
------------------
次回の練習までの課題がはっきりしました。練習し易いですね。するしないは別ですけど。
それではみなさん。次回の練習をお楽しみに。
コントラバス Y.K.
|
|
|
| 2010年4月25日(日) |
| 練習日記 |
|
久しぶりに本番指揮者、野崎さんの練習である。
まずは今回のメインプログラム、モーツァルトの交響曲第31番「パリ」から。明るく華やかなこのシンフォニーの魅力をどこまで出せるかが課題だ。
とは言ってもやはりモーツアルトは楽譜に忠実に、正確に演奏することが大切だ。そのために、いままでゆっくり丁寧に音程、リズム、アンサンブル作りを練習してきたのだが、その成果が少しずつでてきたように思う。
いつも辛口の野崎コメントだが、今日は不気味なぐらい褒めてくれたのは、そのせい?
難関はフィナーレの第3楽章だ。第2バイオリンの細かい動きに乗って第1バイオリンがシンコペーションのテーマを奏するのだが、これがなかなか決まらない。正確さと同時にエレガントな美しさが要求される部分である。ここはじっくりさらっていかなくては・・・
残りの時間はエマニュエル・バッハのシンフォニア、今回のプログラムの冒頭に演奏する爽やかな弦楽合奏曲である。
のちのハイドンの交響曲のさきがけであり、古典派の原点といえる素晴らしい曲だが、バイオリンパートはかなり技術的にも難しいと思う。この曲もしっかりさらいましょう。
さて、私事だが、5月から仕事の関係で中国に赴任することになり、しばらくこの武蔵野室内アンサンブルに参加できなくなる。
せっかくメンバーも充実してきたところで本当に残念だが、おそらく3年後にはまた復帰できると思うので、それまでの間、みなさんで楽しく活動を続けていって欲しい。
武蔵野のモットーである「仲良く愉快に」を忘れずに、後任のアンサンブルリーダー、T君を中心に、さらに武蔵野サウンドに磨きをかけて下さい。
海の向こうから応援しています。
T.N
|
|
|
| 2010年4月11日(日) |
| 練習日記 |
|
ホルン新入団員Yです。2月のアンサンブル大会に参加させていただき,勢い余っ
て入団してしまいました。楽しみながら頑張りたいと思います。
さて,この日の練習後はリーダー送別会。
私は,仕事の都合で練習には遅れての 参加となりましたが,この日一番の目的である送別会にはばっちり参加しました。
送別会と言いつつ,新入団員歓迎会なども兼ねていて,普通の懇親会みたい
になっていました。主賓リーダーが自ら仕切ったりする場面もあり,ちょっと面
白かったです。盛り上がりましたね。
このオケの魅力のひとつは,こういう場での温かい雰囲気だなぁと思います。
皆さまこれからどうぞよろしくお願いいたします。
Y.Y
|
|
|
| 2010年3月14日(日) |
| 練習日記 |
|
こんちには!
3月14日、団員として初めての練習に出席致しましたヴィオラのKです。12月の演奏会にエキストラとして参加させて頂きましたが、それはとても素晴らしい出会いと感じ、入団させて頂くことになりました。
今後とも宜しくお願い致します。
さて、その日の練習はモーツァルトの「パリ交響曲」が大半の時間を占めました。ニ長調のとても明るい曲ですが、随所にモーツァルトらしい陰影も見えます。
私の五十年程の人生で、モーツァルトが傍らに無かったことはありません。大好きです。この曲はメヌエットを含む4楽章ではなく、3楽章で出来ていますが、「起承転結」とも思える前者の形式美に対し、後者は「ホップ・ステップ・ジャンプ」といった躍動感を感じます。
比較的上演率の低いシンフォニーですが、素晴らしい曲ですね!当時のパリにはクラリネットがあったので、ここに用いられています。大好きなクラリネットが使えるので、彼はとても嬉しかったのでしょうね。あっ、そうそう。第二楽章に異稿があるそうで、それも演ってみたいです。
バッハの息子さんの曲は→内声部に意外な、えっ?と思うようなフレーズ、音が出てきて、前回演奏したクーラウでも似たような印象を持ちました。モーツァルトやハイドンとは作風が違いますね。
ロドリーゴはパート譜に間違い・落ち(乱調・落丁?)多く、→間違い探しも結構楽しいかも!?典雅な調べの裏で弦楽器は「フラジオレット」「コル・レーニョ」など色々演奏は忙しいので、のんびりとソロを聴いているわけにはいかないようです。
このほかにディーリアスの小品がプログラムに上るそうですが、どの曲も私としては演奏するのは初めて。人との出会いとともに、新しい経験がとても楽しみです。生きててよかったぁ。
弦中声部TK
|
|
|
| 2010年2月14日(日) |
| 日記 |
|
午前中、アンサンブル大会の練習を各グループ順番に行いました。
午後から、少し人数は増えたものの、アンサンブルとそれほど変わらない編成で全体練習が始まりま
した。
アンサンブルリーダーの指導のもと、ゆっくり目のテンポで練習しました。
パリの1楽章をみっちり、2、3楽章をかるくやった後、弦楽器のみで、バッハの1楽章。
最後にアンサンブル大会で弦楽器全員参加のシベリウスを、力の限り熱く弾いて終わりました。
来週はアンサンブル大会本番!楽しみですね!!
Vn.K
|
|
|
| 2010年1月31日(日) |
| シュポア |
|
全体練習の前にアンサンブル大会の練習をしました。
シュポアの9重奏。
あまり有名な曲ではないのですがT君が事前に音源を探してきてくれたおかげで初練習ながらみなさん早くもイメージが掴めていましたね。前に一度演奏したことがあるのですがその時の初合わせよりずっとまとまっていました。
この曲はFlの友人のお気に入りで、シンガポール時代なぜか私が日本で楽譜を買ってくることになってしまって今手元にあるのですが、本当はこのシュポアという作曲家よく知らないのです。そこで参考までに調べてみました。
1784年ドイツ北部の町ブラウンシュバイクで生まれたルイ・シュポア。父は医師でフルート奏者、母はピアノや声楽を嗜むという恵まれた家庭でした。
5歳からバイオリンを習い始めたシュポアは多作な作曲家でバイオリンコンチェルト、交響曲、室内楽曲などさまざまな作品があるそうです。またベートーベンと同時代の作曲家でベト7の初演ではなんとベートーベン本人の指揮の下、演奏に参加していました。
それにしてもドイツ人のシュポアの名前がなぜ「ルードビッヒ」ではなくフランス語読みの「ルイ」なのでしょうか。
英語読みの「ルイス」でもイタリア語読みの「ルドビーコ」でもなくて「ルイ」。本名は当然「ルードビッヒ」なのですがこれはドイツ語圏ではあまりにもありふれた名前で特に「ルードビッヒ・ヴァン・ベートーベン」と同じ名なので使うのを避けていたようです。
またシュポアの最初のバイオリンの先生がフランス人だったので5歳のころ「ルイ君」と呼ばれていたのかもしれません。ちょうどフランス革命の時代ですからフランスからドイツへ逃げてきた貴族も多かったはず。その中には音楽家、音楽愛好家もたくさんいたことでしょう。そんな理由でシュポアはつねにルイ・シュポアとサインするようになったのではないかしらん。
バイオリンが特に難しいのは作曲者がバイオリニストだからでしょう。T君ごめんね。でもよく弾けていましたよ。アンサンブルのリーダーもしてくれてありがとう。N氏が不在でもなんとかなりそうですね。Nリーダー大丈夫です。安心して中国に赴任してください。遠い空から私たちのことを見守っていてくださいね。
木管MN
|
|
|
| 2010年1月24日(日) |
| シーリング(sealing) 建物を充填材などで塞ぐこと。 |
|
今日は練習+総会+新年会と盛り沢山の一日で、お疲れ様でした。
特に、Eリーダーの4月から中国駐在のニュースは衝撃的でしたね。
武蔵野の音楽作りの中心人物なだけに、不在は心細いですが、
皆で知恵出し合って、武蔵野らしく文字通りのアンサンブル力でやっていきましょう。
まあ、世界各国に団員がいるオケは余り無いと思うので、
海外演奏旅行やっちゃいますか。(ヤケ?いやいやプラス思考ってやつですよ)
木管後列Y.I.
|
|
|
| 2010年1月10日(日) |
| 弾き初め(吹き初め) |
|
2010年となりました。
初練習は一見して集まった人数は少ないようだが、実は団員のほとんどが顔を揃えた。
昨年も一昨年に続き海外流出者がいて、オケとしては辛いななんて思いながらの練習。(仕方ない。戻ってくるのを待ちます。)
そんな中、初練習に現われたVn若手二人がなんだか頼もしい。大学生のT君と小学生のEちゃんは武蔵野がどんなオケかを知った上、昨年入団してくれた。
練習も真面目だし、これからの武蔵野の担い手になりそうで、とても期待してしまう。
そんな二人の存在が武蔵野を明るくしてくれるようだ!
この日の練習は、次の演奏会のプログラムのモーツァルトの交響曲31番とドイツ舞曲。ますは、メトロノームを使ってテンポをかっちりとキープできるように指定テンポより遅めの譜読み。
さあ、やってみると、メトロノームが壊れてるんじゃないかと疑うように、あちこち乱れてしまう・・・。
指揮者が来るまで、ある程度自分達の音楽を作っておかなければならないし、やることはたくさんある。
アンサンブルリーダー中心にこれから本番まで楽しい(?)練習が始まります。
2月28日は第3回アンサンブル大会を開催するが、エントリー曲数は既に15曲位。皆さん積極的!!
団内演奏会ではあるが、団外の方も覗いてくれたら大歓迎です。
今年もどうぞよろしくお願いします。
団長 K.K
|
|
|
| 2010年1月8日(金) |
| 告知 |
|
あけましておめでとうございます。
この度web担当となりました、1stVn.の田原です。
HP運営は初めてですのでまずは必要な知識の獲得、そして担当業務の遂行(=更新)となります。
現在基礎から勉強中ですので、正式な業務開始は今しばらくお待ちください。
なお、団員の皆様には無作為にこのページの原稿執筆をお願いいたしますが、その際は快く引き受けていただければなぁ・・・と思います。
最後になりましたが、団員の皆様、今年度もよろしくお願いいたします。
より一層素晴らしい合奏を実現するために、微力を尽くしたいと思います。
|
|
|
| 2009年10月25日(日) |
| 昨日の練習きつかったですね~。 |
|
2週間に2日しか弾けなかった私は今日左腕筋肉痛です、トホホ。
若い人たちも来てくれて人数も増え、ちょっと活気づいてきましたね。
トリプティークはなんとか格好になるかな、という道筋が見えてきた気がします。(でも2楽章、日本人として、もっとゆっくり演奏したい、と思ったのは私だけ?)しかぁし!ベートーベンはさすがベートーベン、全然見えません!どうしよう~。それにしても野崎さんは追い詰めますよね。もうちょっと具体的に、どう弾くかの指示をくれればわかりやすいんだけど。。だから何?つまりどう弾けばいいの?ってますますわからなくなってしまい、後で個人的に聞きに行ったりするのですが。。。(私の能力には高度過ぎるのかなぁ。)
今の私、みんなでアンサンブルをするのが楽しくてしかたありません。本番まであと数回、メンバーも集まらず不安もあるけど、もっともっと息の合った演奏を目指しましょう!もっともっと音楽しましょう!楽しみましょう!
チェロのK子
|
|
|
| 2008年11月23日(日) |
| もうすぐ演奏会、何だか落ち着かない! |
|
あと本番まで今日の練習を含めて3回だというのに集まりが悪い。今回の演奏会はエキストラが多いので仕方ないけど・・。次回の練習はやっと全パート揃う予定なので、どんな音になるか楽しみ。今日は、指揮者無しアンサンブルリーダー中心の練習でしたが、休憩時間を忘れてしまうほどのリーダーの熱い練習。いくらやっても時間が足りないという感じで、やりたいことはたくさんあるようだ。それは、きっとみんなも同じ。まあ、時間で解決できないこともあるけど・・。せめて、自分は少しでも本番が楽しくなるように、出来ることはやろうと思っている。(チューナーで音程チェック、スコアを見る、音を出す、他)
それより、今の時期は裏方の仕事に抜けがないかが心配!我が団は小規模楽団で、演奏者が全ての準備や係を行うので忙しい。これからプログラムを作る人、その原稿を書く人、お金の勘定する人、宴会の準備する人、諸々。当日はトップ奏者にも係りがある。でも、誰もが優しく協力的。つくづくいいオケだと思う! さあ、あとしなきゃいけないことは?
(団長)
|
|
|
| 2008年11月16日(日) |
| メンデルスゾーン |
|
演奏会まであと1か月を切ってしまいました。今回の演奏会はクラリネットとしては「田園」をがんばらなくてはと思い一生懸命さらっておりました。ところがメンコンのクラリネットの難しいこと。苦手なスタカートばかり吹かされ、3楽章のXなんてみんな悠々と対旋律を歌っているのになぜかクラリネットはmolto vivaceでソリストとかけ合いだし。なかなか横山さんの素晴らしい演奏を楽しむ余裕もなく…。これは田園より難しいかもしれません。はあ。メンデルスゾーンてクラリネットが嫌いだったのかしら…。
そんな気持ちで家路につき、夜9時から日曜日恒例のN響アワーを見ておりました。すると今日の特集はメンデルスゾーン。あらまあ、なんてタイムリーなのでしょうと思い、いつもより真剣に見てしまいました。メンコンではなく「スコットランド交響曲」と「フィンガルの洞窟」を取り上げていましたが。20歳でスコットランドへ旅したメンデルスゾーンは2曲の着想をこの旅行から得たとか。当時若者は職業に就く前スコットランドに旅行するのが流行っていたそうです。銀行家の父の後を継ぐか音楽家になるか迷っていたフェリックス・メンデルスゾーン。1809年に祖父は哲学者モーゼス、父は銀行家アブラハムという厳格なユダヤ人家庭に生まれ4歳年上のファニーと大変仲がよく共に作曲の才能があったとか。裕福でありながらユダヤ人であるがゆえの迫害を受け、一家でプロテスタントに改宗するも改宗後の姓バルトルディは使いたがりませんでした。
スコットランド旅行では16世紀に当地を治めていた悲劇の女王メアリ・ステュアートに深く同情し10年以上の歳月をかけてレクイエムとして「スコットランド交響曲」を作ったそうです。ヘンリ8世の姉の孫にあたるメアリ女王は反乱によりスコットランドを追われたあと一時はエリザベス1世に庇護を求めますが自分にも王位継承権があること、エリザベス1世の母アン・ブーリンがヘンリ8世に処刑されていたことを理由にカトリック教徒を集めて王位奪回を企てます。ところが逆にその陰謀が露見し結局18年も幽閉された挙げ句処刑されてしまうのでした…。そういえば全体に暗く重苦しい旋律が続き哀愁漂うメロディーはクラリネットが担当することも多く、おいしい使い方をしてくださっています。一方「フィンガルの洞窟」はヘブリディーズ諸島を見学した時の経験から作曲したとか。これもスコットランドの寒々とした情景が思い浮かびますね。N響首席Cl奏者横川さんの深い音色のソロが素敵…
最後に池辺晋一郎氏曰く、「クラリネットばっかりですね。クラリネットが好きだったのかな」だって。ああ、そうなのです。メンコン、スコットランド、フィンガルと聴いて来て私にもわかりました。メンデルスゾーンはクラリネットが大好きでつい、たくさん使ってくれちゃったのでしょう。これは光栄なこと、幸せなことと思わなければ…。Kご夫妻、パールマンのCDありがとうございます。田園もメンコンも、もちろんコリオランも良い演奏になるようあと1か月がんばります!きっと我らがキララホールが力になってくれるでしょう。
MN
|
|
|
| 2008年11月9日(日) |
|
|
前回に引き続きソリストの横山さんに来ていただき、コンチェルトを細かく練習した。前回はお見合いのようにお互いの様子を探り合う練習だったが、今回は横山さんの表現したい音楽にオケがピッタリついていくための練習ができたと思う。まだまだオケのほうは練習の余地を残しているが、ポイントはつかめたので、次回12月6日のリハーサルまでにさらにいい状態にしていきたい。
後半は田園を全曲通して練習し、今までのおさらいをした。管楽器メンバーも徐々に揃ってきて充実した練習だったが、まだすべての楽器が揃っていないのは残念。すべて団員でまかなえるようにすることが今の武蔵野にとって最大の課題だ。
T.N (Vn)
|
|
|
| 2008年11月3日(月) |
| 初Soloあわせ |
|
12月7日の本番まで約1ヶ月となった今日の練習は、メンデルスゾーンのコンチェルトでソロをお願いしている横山奈加子さんとの初リハーサルである。今までに何度かリサイタルに伺ったりして横山さんの音楽の素晴らしさはよく知っていたつもりだが、いざすぐ目の前で弾いていただくと感激もひとしおであった。とにかく音が美しい!そして抜群のテクニックと心にしみこむ音楽性には、ただただ圧倒された。その素晴らしいソロと一緒にオケパートを弾く喜びはやはりコンチェルトの醍醐味である。何だか自分達もつられてうまくなったような気がするのは錯覚だろうか。本番まであと2回のリハーサルで、ソロとオケがひとつになったようなコンチェルトに仕上げたいと思う。
今回のプログラムはこの超有名なバイオリンコンチェルトをベートーベンの序曲コリオランと田園交響曲でサンドイッチにした、なかなか贅沢なものである。どれも素晴らしい名曲だが、やはりベートーベンはオーケストラの基本がぎっしり詰まった音楽だと思う。あと1ヶ月の間にもっともっとベートーベンらしさを出せるようにしたい。練習にメンバーがなかなか全員揃わないのはいつも悩みの種だが、楽しく、しかも充実感のある練習をすることで人も集まってくるのだと思う。今日はトランペット、コントラバスに若手が初登場、武蔵野も全体的にかなり若返った印象だった。
T.N (Vn)
|
|
|
| 2008年1月13日(日) |
| ♪初練習♪ |
|
1月13日は今年の初練習。次の演奏会に向けての初練習でもあった。
ということで、当然初見大会。初見は苦手ながら、失敗しても注意されないし(スミマセン!)、スリリングさも加わりちょっと面白い。いつも通り楽譜が配られていきなり始まる。
この日、演奏会でやる曲3曲を指揮者なしで最後まで通したが、当然曲本来の良さなど出てこない。だからこそ、アマはこれから本番までに仕上げていく課程が楽しみというものだが・・。
それにしても、みんな初見なのに良く弾き、吹くので感心してしまう。私は懸命に楽譜に集中するのだけど、どこかでこけてしまう。集中力だけの問題ではなく能力の問題もあるといつも自覚するのです。(ちょっと落ち込む。)いつもながら、この武蔵野で続けていくつもりなら「もっと頑張れ!」と自分にはっぱかけます。最近ちょっと嬉しいのは、このところの武蔵野は楽しい。きっとみんな同じ方向を向いているからではないかと私は思っているのですが・・。、次の演奏会はどんな音が出るのか楽しみです。
この日は練習後に総会もおこなわれましたが、問題なくスムーズに終わりほっとしている。良かった!
そして、もうひとつ良いことが。FgとVnに待望の新入団員が加わりました。Fgは数年前からトラで来てくれていた名人、Vnは地元の若手美人ママ。今年は幸先のよいスタート。
最後に苦言を。18回演奏会のCDが出来上がりさっそく聴きいてみましたが,その感想を。歯切れはよくなったけど音が汚い!まずは音程に大きな課題有りと感じました。音作りには全員が欠かせないと思いますが。今年の目標ですね! K.K
|
|
|
| 2007年12月8日(土) |
| 本番前日 |
|
いよいよ明日は本番である。今日は土曜日午後の練習ということで出られない人もあり、じつはこの練習日記もいつものNさんがお休みで私が代わりに書いている。大事な最後の仕上げなのだが、あいにく指揮者の野崎さんも別の本番のため来られず、自主練習ということになった。先週みっちりと練習してだいぶいい感じになってきたので、その状態のまま本番に突入したいのだが、一週間の空白はアマチュアにとっては痛い。せっかく出来たことが元に戻らないように、まずはポイントをピックアップしておさらいし、そのあとは指揮者なしで本番どおりに通すことにした。
なにしろ今回のプログラムは2曲とも半端じゃなく難しいのだ。弦も管も速くて細かいパッセージ次々に現れ、一生懸命さらわないとなかなか弾けないのだ。そしてこの難曲2曲を最後まできちんと弾き通すためにはスタミナの配分も考えなければならないので、その感覚をつかむことも今日の練習大きな目的だ。
明日に備えて早めに練習を終えるつもりだったが、結局いつもの時間になってしまった。でもいい感じには仕上がっている。これにキララホールの素晴らしい音響効果が加われば大丈夫。今回もお客さんに喜んでもらえるような、楽しい演奏会にしたいと思う。
ご期待下さい!(あんりー)
|
|
|
| 2007年12月2日(日) |
| 目と目で通じ合う? |
12月。ベートーヴェンは4番でなく9番のシーズンだ。以前、第九を演奏するたびに不思議に思ったこと、それは合唱団の人たちはどうしてあんな“目”をして歌うんだろう、ということ。歌っているときの目、指揮者を見るときの目の表情が違うのだ。直径が3倍になってビームを発射するような、凝視の目なのである。
では私たちは、練習中に何を見ているのか。まずは楽譜。そしてポイントでは指揮者。特にフレーズの入りや速さが変わるところ、そして曲の終わり。あとは・・・実は、奏者同士お互いを見ているのである。ヴィオラに合わせるところは、ヴィオラを見ることでそのフレーズが聴こえてくる。管楽器と息を合わせる時も、弦楽器と弓を合わせる時も、ソロに伴奏型をつける時も、お互いを見ることで合わせていく。うまくいったり間違えたりしたところも顔に出る。目の表情は、一カ所を凝視するのではなく、四方八方にアンテナを張って獲物を狙う動物のような・・・といったら言い過ぎかな? 私は演奏中のメンバー観察はかなり好きなのだが、みなさんもぜひ観察してみてほしい。
本番1週間前。広い空間に慣れようと養護学校の体育館を借りての練習である。耳が慣れるまで、最初の数分はギクシャクした感じになるが、こういう時は目が頼り。何度もやり直してやっとうまくアンサンブル出来たときのメンバーの表情を目にすると、自分も嬉しくなる。あまり重要でないと思っていたフレーズを“もっともっと”と目で訴えられて、あわててしっかり弾くことも。そんなノン・バーバル・コミュニケーションが音と一緒に飛び交うのだ。(な) |
|
|
|
| 2007年11月25日(日) |
| セカンド・バイオリンのお仕事 |
|
練習が終わって、片づけをすると、だいたい夕方の5時頃となる。車で練習所に来る人も多いので、三々五々解散となるのだが、時々近所のファミレスに集って、しゃべったり食べたり、打ち合わせをしたりすることも多い。ちなみに、今日は2008年春の演奏会の曲目についての話し合い。もっとも、民主的に話し合うというよりは、各々言いたいことを言い合って、何となくまとまる(無理矢理まとめる?)ことが多いようだ。家に帰ってきて、”大河ドラマ”と”N響アワー”を見ると私の週末が終わる。
”セカンド・バイオリンのお仕事”は、今日のN響アワーのタイトルだ。1st
Vnに比べ、地味な存在に思われがちな2nd Vn。だが、リズムを刻み、和音を作り、メロディを演奏し、効果音も担う、という仕事ぶりを、モーツァルトのディベルティメントを例に解説していて、「そうそう!!」とうなずきながら聴いていた。合奏全体のバランスを見ながら、臨機応変に役割を演じていく重要なポジションである。
オーケストラなどの器楽合奏は、音楽の中での役割分担が明確である。車にたとえるなら、ハンドルを切る役割、エンジンに燃料を送り込む役割、外にむかって華やかさをアピールする役割、などがあって、進むべき方向へ走ることができる。役割が明確だから、穴があいたり綻びができたりした時の責任の所在も明確だ。そこが合奏の厳しさでもあり、やりがいでもある。
武蔵野室内アンサンブルは、1st Vnも2nd Vnも6人ずつ。大編成のオーケストラであれば、太い束をになう細い1本として”寄らば大樹の陰”的に弾くこともできるが、6人ではそうはいかない。6人であれこれ弾いてみても、いまひとつ何かが足りなかったのが、指揮者のアドバイスと試行錯誤の結果、1+1+1+1+1+1が6ではなくて10や20にもなって聞こえる一瞬がある。音楽ってすごい、と心の底から思う一瞬でもある。(な)
|
|
|
| 2007年11月18日(日) |
| ベートーヴェンのpp(ピアニシモ) |
午前中はアンサンブル・リーダーのN氏による弦分奏。あちこちに、いつもの練習で気になりながらもゆっくり詰める時間がないまま来てしまった箇所がある。Vnがボーイングを変えたけれど、VcやCbも合わせる? 同じフレーズが高弦と低弦で出てくるから、ニュアンスを揃えて弾かないとね。テンションの持って行き方に迷って、どう弾いてよいかわからないcresc.もある。仲間に相談することで、あらためて方向性が見つかるのだ。
ベートーヴェンの交響曲4番の楽譜には、pp(ピアニシモ)やff(フォルテシモ)はあるけれど、mp(メゾピアノ)やmf(メゾフォルテ)が登場しない。そんな話になったのは野崎さんのいつの合奏の時だったか。中学生の音楽の教科書に、pp<p<mp<mf<f<ffと書いてあったような。ベートーヴェンの辞書はmezzo(やや)という表現が無いのだとしたら、白か黒か、0%か100%か、のall
or nothingな極端な物言いをする人だということ? いや、そうではなくて、pもppも絶対的な強弱が小さいのではなく、そういうニュアンスの、そんな雰囲気の、という幅を持った表現方法なのだろう。豆腐を素手で持つとき、力を入れたらぐしゃっと握りつぶしてしまうけれど、そぉっと持つ時も神経や配慮とともに力をも使う。ppとあってもエネルギーを注いで音を鳴らす箇所だってあるのだ。ベートーヴェンのppなんて、弱くて小さい音だけれど大事に大事に弾かないといけない。
では、ffは? 力一杯弾けばいい、ってものではない。力んで弾いても美しく鳴らない。そうはいっても楽器にも限界ってものがあるしねぇ。・・・と言い訳をしていたのだが、どうやらそうではなかった。弾き手が違えば、同じ楽器でもまた新たな音色を鳴らすのだ。それを聴くことができたのが、今日一番の発見かも。ベートーヴェンが、チャイコフスキーのようにffffやらfffffやら書かない人だったことに感謝。(な) |
|
|
|
| 2007年11月11日(日) |
| ひとり弾き |
|
武蔵野室内アンサンブルの”室内”とは、小編成=人数が少ない、という意味だ。どのぐらい少ないかというと、フル編成のオーケストラが70~80人を越すのに対して、うちの楽団は全員そろっても30数人。弦が20人余り、管打が10人余り。私を含めたメンバーのほとんどがフル・オケの経験者なので、大編成にはその良さがあり面白さや楽しさがあるのは充分承知しているけれど、小編成で演奏することの緊張感や難しさも、これはこれで結構捨てがたい。
そう、少人数は難しい。ひとりが出す音は、すぐに全体に作用する。誰かひとりがちょっと速めに、と1cmアクセルを踏んだだけで、あっという間に車全体がスピードアップするし、その逆もある。まっすぐ走るもジグザグ走行もぶち壊すのも、ひとりが出す音の作用で簡単に出来てしまうのだ。100人のオケとは、大型ダンプと軽トラぐらいに機動力が違うのでは。
さて、タイトルの”ひとり弾き”。私の高校時代、時々教えにきてくださった某指揮者先生は、”ひとり弾き(吹き)”をさせる方で有名だった。ということは、”ひとり弾き”って世間ではよっぽどのことなのか。けれど、武蔵野のような少人数では、パート単位で弾くのがすでに”ひとり弾き”同然のこともある。誰かに隠れて”弾いたつもり”になることはできないから、”ひとり弾き”でも”ふたり弾き”でも、”全員弾き”でも、同じなのだ。こんな積み重ねから、何があっても動じない度胸だけはしっかり身に付く。
高校生のSくんの”ひとり弾き”を後ろで見ながら、そんなことを考えていた。かくいう私も、今日は相棒がお休みだったので終始”ひとり弾き”。場数は踏んでいるので今更びびったりはしないけど、相棒がいないために自分にも他人にもバレバレのやばい箇所も多々発見。場数だけじゃ、何とかならないんだよねぇ。(な)
|
|
|
| 2007年10月28日(日) |
| 耳と目で見つける発見∞ |
|
今日は、メンバーのM氏(ティンパニ)の指揮による合奏。「ちょっとゆっくり目のテンポでいきましょう。」にホッとする。個人的な事情で恐縮だが、ここ2週間仕事が大詰めで、楽器に触っていないどころか、MozartもBeethovenも全然聴いちゃいないのだ。楽譜に鉛筆で書き込んであるメモ、えーと、これは何のことだっけ?
♪=数字の問題ではなく、”ゆっくりめ”と言われただけで気持ちにゆとりが生じる(実際はそんなに遅くないかも).。楽譜を追いながら、あぁ、これはこういう文脈のなかで強調する音だったんだっけ、と思い出す。思わぬところでファゴットが綺麗な対旋律を吹いている、と気がついて耳を傾ける。この音で和音が解決して、次にF-durへ転調する、と意識しながら弾くことができる。何となくrit.している(遅くなる)のではなく、次に続くフレーズが構造上大事だからだったんだ、と気がつく。
合奏の中で、自分の音を出しながら周りの音を聴く、というのは、耳も目も頭も気持ちもフル稼働する作業だ。周囲を聴きながら見ながら、自分の音を作るというのは、ある意味キャッチボールであり、会話であり、コミュニケーションだと思う。気がつかないと聴き過ごしてしまうことも多く、毎回毎回発見することがたくさんある。何回噛んでも、まだ味がする、オケって、スルメみたい。だから止められない止まらない。(な)
|
|
|
| 2007年10月14日(日) |
| 「響きを合わせて」野崎さんによる3回目の合奏 |
|
「みなさんがもうちょっと弾けるようになったら、いじりましょうね。」速い楽章の速いパッセージについて、前回いただいたコメント。つまり「もうちょっと弾けるんだったら、さらってきてね。」という宿題ですね。速い曲は速い方が気持ちいい。カイカ~ン!なのです。とはいうものの、速い=ヤバイ、と精神状態がテンパってくるのも現実。速さに追われるのではなく、速さを気持ちよくドライブできるように、なおかつヤバイところもそれなりに聴こえるように(弾けるように、とは申せません:汗)なりたいものです。
「響きを合わせて」今日の練習で、何度も聞いた言葉です。弦楽器全員で出す一発の和音。バランスやニュアンスや立ち上がりにちょっと気を配るだけで、後ろで聞いていた管楽器のメンバーが思わず「カッコイイ!」とつぶやくサウンドがしていたのを、弦のみなさん知ってますか? いつもそんな音が出せるようになると素敵なんだけど、なかなかそうはいきません。
そんなわけで、ほんの一瞬の輝きやワクワク感を内包しながらも、練習はさらに続いていきます。本番まであと2ヶ月。がんばりましょう。(な)
|
|
|
| 2007年10月7日(日) |
| ウェブサイトを立ち上げました |
「武蔵野室内アンサンブルのホームページを早急に立ち上げてください」という指令を受けたの約1ヶ月前。いやいや、半年以上前から、私が担当になっていたのです。ホームページ用のソフトを購入したものの、生来の”お尻に火がつかないとなかなか動かない性分”もあって、PCソフトの箱は開封されないまましばらく放置。その間、団内のいろいろな動きや変化があり、私に催促の矢が来ないのを良いことに、”ウサギと亀”の”ウサギ”よろしく、のんびり構えておりました。9月に入り、団も本格始動。”カチカチ山”の狸よろしく、私のお尻にもやっと火がつきました。
このホームページが、音楽を楽しむ仲間たちや聴いてくださるみなさんを応援する手がかりになれば、嬉しく思います。今後ともよろしくお願いします。(な) |
|
|
|

